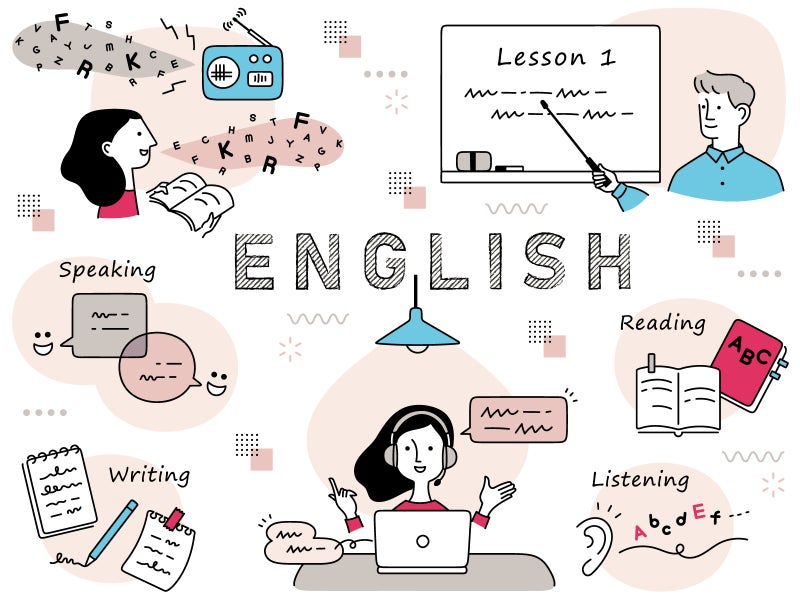☆ハーレム日記リバイバル☆ 第95号 ルームメイト
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十五号 04/13/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
*****ルームメイト*****
ニューヨークは周知のとおり家賃がとっても高い。まず家賃はハーレムでさえワンベッドルームで800ドルから1000ドルが相場。ミッドタウンやダウンタウンではワンルームが1000ドル以下では不可能。
1500ドルをゆうに越えるから、二人で家賃を分けても750ドルは払わなければならない。
住宅環境としては日本で最悪だと言われている東京以下。その上家賃は今でも、『欽ちゃんの全日本仮装大賞』テレビ番組の得点ボードがズンズン点滅しながら上がっていくようにズンズン上がりつづけている。
そのせいかルームメートを持つことが一般的だったりする。狭い日本では、どんなに狭くても一人暮らしが普通だから、見ず知らずの他人と同じ屋根の下に暮らすなんて想像を絶することだろう。
私は日本人のルームメートと3回同居した経験を持つ。1度目はハーレム日記にも何度も登場しているJちゃん。当時は私のことを『我がままなクソババア』と私が部屋を空けた時には、わら人形を柱に打ち付けた日もあったに違いないが、
彼のことは未だに目に入れても痛くないくらい実の弟のように愛しい。
次は、MちゃんとWちゃん。彼女たちとはブルックリンで女の合宿状態。『説
教部屋』もあって、酔っ払っては若手のWちゃんに説教をたれていた。可愛さあまって、彼女の父になった気分で変な虫がつかないように見張っていた。
前置きが長くなったが、この度ここに登場するのはハーレムで一人暮らしを決意する前に出会った。「苦手な女性」の物語である。
ブルックリンで暮らしていた頃、MちゃんとWちゃんが日本に帰ることにな
ったので、Kさんを紹介された。彼女はスタイルも良く色白な美人で、とにかくその美貌のせいからか、人に頼ることを当たり前のことだと思っているタイプだった。
トークもちょっぴりスローなトロ系の天然で、ナメクジのようにノロノロ動く様は、『博多の塩』をグウの音も出ないくらいにふりかけて、溶ける姿を楽しみたい気分にさせる要素を含んでいる。
引っ越して来た時、電話を自分専用に引きたいらしいが英語ができないからと、Mちゃんに電話会社に問合せをしてもらっていた。しかし、うまく通じなかったらしく、二人で私の会社に電話をかけてきた。
私もやはり親切な日本人、ここで「仕事が忙しいから。」などと断ることもできず、忙しい合間をぬって電話会社にKさんのフリをして契約を進めた。契約時には細かなサービスの説明やらなんやらを聞いたり、決めたりしなきゃあならんので30分は時間をとられる。
自宅に帰って、「Kさん、電話会社契約しといたよ。電話番号はこれね。来週の土曜日には工事しにくるらしいよ。」と話す。
「あのーぉーロングディスタンスはどこにしたんですか?」(当時は、ロングディスタンスだと別会社になってたの?だね。。。)
「あー適当に決めといたよ。」
「私ぃーXX会社の方が良かったんですけどぉー。」
てめぇー「ありがとうございます。」の礼を言う前に、クレームかい!
あたいはあんたの秘書やないんじゃーと叫びたいが、たこ焼きを口の中にくわえた瞬間、外側は冷えているのに中はアッチッチーで高温な上、パンツのゴムみたいにタフなタコが入っていて噛んでも噛んでも、のみこめない状態だった。
そんな彼女のお願い攻撃は、二人で同居が始まってからもエスカレート。
怒りに震えながら自分の部屋に引きこもり、本格的な引きこもりの状態になるのに1ヶ月を要さなかった。
「ひろえさぁーん、ここの火災報知機の電池が切れてるせいで変な音がするんですけどぉー、管理人に言ってもらえますかぁー?」と、私が仕事に行く直前でバタバタしてる時に言ってきた。
「そんなの自分で交換しろ。」って管理人に言われるに決まってると思ったが、とりあえず聞いてみようと思ったお人好しの私が馬鹿だった。
無愛想に「電池くらい自分で交換してください。」と管理人に言われ、
何で私が管理人と話してるの?よーく考えると言い出しっぺの彼女が説明すればよいことなのに、英語の問題をタテに使われている自分がそこに居た。
「愚か者」って書かれた白い紙を背中に貼られて知らずに歩いてる私。
その後は、意地をはってしばらく警報機の妙な音を我慢していたが、むしょうにイライラして結局、私が取り替えた。
更には、私が寝ている時に、Kさんは夜中の2時に外から電話をかけてきて第一声から、
「ひろえさぁーん。XXってクラブは何処ですかぁー?見つからないんですぅー。」
馬鹿やろー見つからんのなら、その辺で勝手に遊んでおれ。と寝起きでイライラして「知らん!」と言って切った。
もっともっとプライベートな悩みや、その他もろもろは掲載を控えておくが、とにかく私は精神的にも末期状態となり、エアーガンを所持していたら縄でくくりつけて彼女を撃ちまくってやるぜ〜くらい凶暴になっていた。
「ひろえさぁーん」の声を聞くごとに、もとい、彼女が帰ってきたとドアの音がする度に、全身の毛が逆立ち心臓がドクドクと暴れだす。
「私の名を呼ばないでくれぇー。」と、知らずに白いローソクに向かって訳のわからない念仏を唱えていた。
そうして、とうとう切れてしまった私は、不必要に会社に電話してきたKさんを火山がドッピュ−ンと噴火するかのごとく大声で罵倒し、ハーレムに移り住むこととなったのである。
だが、彼女と別れて住むことにならなければ「ハーレム日記」は存在し得なかったわけで、ある意味ハーレムに住むチャンスを、ライターとして存在し得る私を、創った女だったのかもしれない。Kさんに感謝だ!
人生で苦い経験も、後のチャンスに繋がる布石になっているものだ。
<弘恵・今週の格言より>
※今の時代はハーレムのStudioでも一月1800ドルはするだろうから、高くて住めない。。。
あと、ルームメイトは日本人同士が一番いいけど、合わない相手もいるってことだ。
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第94号さすらいのバーカウンター編 第二弾 怪しいネットワークアドミ
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十四号 04/11/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
〜☆〜☆〜☆〜さすらいのバーカウンター編 第二弾〜☆〜☆〜☆〜
*****怪しいネットワークアドミニストレーター*****
いつものようにスポーツクラブを終えて、帰宅途中に一杯飲んで帰ろうとグランドセントラルステーションにあるトゥー・ブーツ<閉店>に寄った。
ここは元来ピザ屋なんだけど、バー・カウンターもあって、軽く酒が飲める。ここのバーテンダーのオヤジは25年のキャリアの持ち主。
オヤジは無気力に銀色のシェーカーを横方向へシェークしてマティーニを一杯つくってくれた。確かマティーニってステアするんじゃなかったっけ?まったくアメリカンなバーテンダーだ。
しばらくすると、隣に座ってきたのは白人の男性二人、だが私の隣には1つしか席が空いてなかったので別の席に移動しちまった。そして、入れ替わりに座ったのがブラックのオヤジ。
くたびれたペパーミントグリーンのシャツはカビの色、モスグリーンへと化している。顔はドラマ「踊る大走査線」の湾岸警察署の刑事課長役、小野武彦さんにクリソツ。
新聞片手にピザをぱくつきながら、グラスに注がれたウォッカをあおる。
オヤジは私のグラスを見て2杯目は「同じものを」と、たいていは自分が飲んでるものと「同じものを」のはずが、私が飲んでるものと同じものをオーダーしやがった。それがきっかけで話し始めた。
以下は、会話の抜粋。
「僕は、アメリカン・バンクでネットワークアドミニストレーターをやってるんだ。」なぬ?どこかで聞いたことあるぞ。
「夫も同じ職業です。じゃぁかなり稼ぐんでしょう?」
「そうだね。僕はボスだから。世界中のネットワークをとりしきってるんだ。日本に行ってる部下もいるよ。」
「大学の頃からコンピューターを専攻されてたの?」
「僕等の時代にはコンピューターのクラスなんてなかった。仕事をしていくうちにコンピューターの必要性に駆られて自分で学んでるうちに、ここまでエキスパートになったんだ。」
「それは凄いですね。」
「シスコのラウターのコンフィギュレーションなんかもやってる。」
「サーバーは何を使ってるんですか?」
「ユニックスだよ。」
彼は、ロングアイランドで生まれ、現在は奥さんと共にウエストチェスター在住だという。子供二人はベビーシッターに預けている。
「僕は、これからメトロノースに乗って帰るんだけど、君も125丁目までなら僕がチケット買ってやるから、一緒に電車で帰ろうよ。地下鉄よりも、格別に速い。」
「では、お言葉に甘えて。」とホームへ。太った白人女性が一人座ってる5人がけの席に二人向かい合わせで座る。車掌の兄さんがチャキチャキと軽快な音を立てて切符を回収している。オヤジは、ちょっぴりオドオドした目で兄さんの姿を追った。
なぜにぃー?<フリオ・イグレシャスのナタリー風にどうぞ>
オヤジが財布の奥底から取り出したのは、くたびれた回数券と私のための5ドル札。それを受け取った車掌の兄さんは「お客様の分の5ドルも必要です。」と、すかさず言った。
オヤジは渋々5ドル追加する。「そんなに高いのか?」オヤジが軽く文句つけると兄さん、
「お客様の125丁目までの回数券は、既に有効期限が切れております。」
おいおい、オッサン125丁目に住んどるんやないけぃー。あっしを騙そうったってーそうは問屋が卸さないぜ。
オヤジは、ばつが悪そうに喋りまくった。
「5ドルは高いよな。まったく・・・どうなってんだか。」オッサン、ウエストチェスターまでは、随分前から5ドル徴収されてるぜ。
とオッサンの喋りを、うわの空で聞いていた私は125丁目で、そそくさとオヤジ残して下車。
私たちが乗ったのはエクスプレスだったから、次の停車は125丁目から20分ほどかかるウエストチェスター。オヤジは、そのまま電車に揺られて行っちまった。その後、折り返しのチケットを買って125丁目に戻ったに違いない。
まったく、自分を演出するためにコンピューター用語だけは熟知してるオヤジが出没するとは、けったいな世の中だ。
※今は、ProvaというPizza屋になってるようだ。バーもまだある。きっと高いだろうから、行かないけど。
最近のトレンドは、フードコートみたいな店のビールを飲むビジネスマンが増えている。昔は、ビルの1階にバーがあって、そういうちょっと高級なバーへ行く人がいたけど、高すぎるからか、あまり皆が行かなくなった気がする。
こういうところとかが流行っている。
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第93-2号 BAZAARニューヨーク特集号
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十三号 03/31/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
*****BAZAARニューヨーク特集号*****
BAZAARのニューヨーク特集5月号が発売され、その記事の纏め役を勤めた伊藤操さんと同誌にも登場したメークアップアーティスト吉村綾子さんが紀伊国屋書店にて講演を行った。
ニューヨークコレクションのスライドを見ながら今年の流行は、ミリタリー風で強い女をイメージしてメークも目元にポイントを置いたものが多いといった解説をしてくれる。
わざとビンテージに仕上げたレザージャケットなども多く登場したそうだ。
吉村さんは、アカデミー授賞式の際には女優ウィノナ・ライダーやヒラリー・スワンクのメークも手がける達人。ご本人もメークは落度なく、流れる石と書いて「さすが!」と唸る東洋人の美しさ。
墨絵で掛軸にして飾ってしまいたいほどだ。
質問コーナーで積極的に手をあげた私は、本当は吉村さんに「コレクションでモデルを塗ったくったギャラはいくらなのですか?」と質問したかったのだが、それではとっても失礼なので、
「モデルさんをメークするのに時間はどの位かかるのですか?」と質問。
「ヘアーさんとモデルを奪い合いになるくらいの凄まじい舞台裏。20分くらいで一人のメークを仕上げます。」ということだった。最近はウェットティッシュ系のメーク落しがあるから、かなり楽になったとも言っておった。
講演終了後、操さんが日本へBAZAARの編集長となるために帰国することから、関係者によるパーティーが開催されるという。ライターのE師匠と私は、躊躇しながらも<私は当然イケイケだったが>、パーティーに参加することとなった。
Dish of Saltというチャイニーズレストラン。かなりお洒落で高級感漂う会場にはダンディーが服を着て歩いてるような売れっ子フォトグラファーやら、マンハッタンの高層ビルの一室で、夜景を見ながらけだるそうにタバコを吹かすのが似合いそうなカッコいいライターの女性を中心に50人近く集まっている。
その他、講談社や共同通信やらのニューヨーク支店の編集長、その上ダナ・キャランを創った男・滝富夫さんなどと豪華キャスト。
突然参加したワシはE師匠から、おはよう子供ショーのムックみたいだと後ろ
指をさされる着ぐるみのような素材のオレンジなトレーナーにスニーカーと、チャイニーズのデリバリーの兄ちゃんみたいな姿なのだ。
バー・カウンターから早速、離れない私は「ねぇーボンベイ・サファイアはオーダーできないの?」と数杯飲んだ後チャイニーズのバーテンダーにしつこくおねだり。しかし、この酒は料金が高いのでバッフェスタイルの食事にはオアズケ。
「飲み放題は安酒のみだとぉー?そりゃー私のような大酒のみがいれば、採算が合わないかもしれん。だけどぉーよー一杯ぐらいいいじゃないかぁー」と粘る。
その姿はまるで、ギャンブルで有り金全てスッて一升瓶を片手に鼻の頭を赤くして憤るオヤジだった。
さておき、テーブルに座った際にも若い兄ちゃんをおびき寄せる。ハーレム在住者らしく逆ハーレムなバーチャル世界を現実のものとするのに一分とかからなかった。とにかく若手3人のフォトグラファーは男前な日本人男児。
「美味しそうだー。」と口走ったのは、チャイニーズフードではなく兄さんたちにむけて放った言葉だったことは付け加えておく。
が、しかし、BUT、隣のテーブルに座っていた場違いな雰囲気<人のことは言えんが>で、レッドスネークカモ〜ンのゼンジー北京さんを彷彿とさせる男性が、笹に巻かれたチマキをパンダのように、がっついていた。
彼は、ネットワークアドミニストレータ−で、プライベートに操さんのHPづく
りを手伝っているのだという。男前よりもコンピューターに軍配があがるのは早かった。
ゼンジー氏の隣に喰らいつき、「サイトを数人のライターで運営する予定だけど、サーバーは自分の家で持つべきかスペースをレンタルすべきか。」といった話題で盛り上がる。
もうライターな皆さんとは別の世界、ITなオーラでバリアを築いていた。
そうこうしてる内、パーティーも終盤に近づく。先ほどのカッコいい女性ライターが操さんに向けて詩を朗読。彼女が自分の居場所を確立するまでニューヨークで頑張ってきた生き様を綴っていた。
数人のライターは「いい詩だったわねぇー。涙しそうになったわ。」と感銘している。
だが残念ながら私には共感できなかった。貧乏が故、サンクスギビングの日に粥をすすって生活しようとも、イーストビレッジの地下室で楽しく暮らしていた御気楽人間な私と「彼女の詩」は縁遠い世界だと感じたせいだ。
彼女は、私なんかには、とうてい理解できない高貴なるプライドと確固たるスタイルと複雑なる精神構造を持ち合わせているようだ。脳天気な私は決してカッコいい種類の人間に溶け込むことができない。
「同じライターという職業であってもカッコいい自分になれる人が羨ましい。」
とE師匠にぼやくと「大将は、そのオヤジっぽい自分らしさが売りなんだよ。」と励まされた。
あーあーいつになったら、米つきバッタのようにペコペコしないで暮らせるくらいくらい売れっ子になれる日がくるのだろう。だけど、おそらく売れっ子になってもパーティーは居酒屋「りき」で行う予定だ。
2次会は勿論ウサギちゃんが行き交うバーで!
※ウサギちゃんはいないが、うさぎという銀座の高級クラブのようなピアノバーはいまだNYにある。この店を支える日本人がいることは大切だと思う。
<閉店>DISH OF SALT
133 West 47St <bet6-7Ave>
212-921-4242
オーナーのご主人は、アーティスト。壁に飾ってある斬新なアクリルで描かれたビビッドなカラーの大きな絵は圧巻。全てアンディー・ウォーホール風なタッチだ。
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第93-1号 さすらいのバーカウンター編 第一弾 ハーレムの裏情報
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十三号 03/31/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
〜☆〜☆〜☆〜さすらいのバーカウンター編 第一弾〜☆〜☆〜☆〜
*****ハーレムの裏情報*****
久々にレイ(夫)と喧嘩をしてしまい、気分転換にレノックス・ラウンジへ一杯飲みに行った。
125丁目を一人歩いていると、途中で赤いギラギラした反射鏡みたいなものが付いた大きなポラロイドカメラ調な古めかしいやつを首からぶら下げているブラックのオヤジに遭遇した。
「君を撮影させてくれ。」と言ったが、「金とるつもりでしょ。」と無視してラウンジに入った。
日曜日の9時過ぎだというのにカウンターは満席。ラム&コークをオーダーして立ったまま飲んでいた。奥の部屋ではジャズシンガーが歌ってる。あれ?日本の女の子だ。黒いロングヘアーに黒いドレス、壁に貼られたチラシにも日本名が。
さっきのカメラをぶら下げたオヤジが私の隣にやってきた。大きな身体をユサユサさせて、大きなバッグも一緒だ。
「あなたはフォトグラファーなの?どのくらいやってるの?」とオヤジに聞くと、
「プロで20年以上はやっているよ。この辺でオイラのことを知らない奴はいない。」
「今日は、日本のジャズシンガーが歌ってるんだね。」
「日本人客も最近とっても多いよ。日本から来たモデルやタレントもオイラが撮影したりするんだ。」
「私、この近所に住んでるの。」
「そうかぁー一人でこんな所にいたら、亭主にカンフーで技かけられるんじゃないのかい?」
「ジャマイカンなの。家の亭主はブラックよ。」
「そうかーてっきり日本人だと思っていたよ。オイラは一人暮らしなんだ。145丁目のレノックス。5つも部屋があるところに一人で住んでる。家賃は400ドル。」
「ひゃーっ、安い。」
「最高にイカした部屋なんだぜ。遊びにおいでよ。君は太目で僕のタイプだ。」
太目ってのは、ちょっとムカ〜っときたが、どうやら誉め言葉らしい。
「ところで中に入ってジャズ聞くと、いくらなの?」と、奥のジャズをやってる部屋に目をやる。入口のチケットを切るヨボヨボ爺さんにオヤジが「いくらチャージするんだっけ?」と問う。
「10ドルだよ。」
「10ドルもするんだ。だったら酒が2杯飲めちゃうから・・・。」と、この日はジャズを聴く心境でなかったので、オヤジと話しこんでいた。
するとショート・ドレッドの男前の兄ちゃんが、わけありな表情でオヤジの傍にやってきた。「パフィー<パフ・ダディーをブラックの人たちは、こう呼ぶ。>は、
やっぱりxxxxxにハメられたんだ。」と妙なことをオヤジに口走る。
「そうかー。」とオヤジもマジな顔つきで頷いている。
昨年タイムズスクエアのクラブでシューティングがあり、車で帰路へついたパフィーは警察に止められ、拳銃を所持していたことによって、この頃は裁判が続いていた。
結局無罪になったが、ハーレムの住人は彼の潔白を信じ無罪になることを願っていたようだ。
そういえばOJシンプソンの時も、ハメられたんだという噂がブラックの人々の一部で起こったことがある。まったくぅ〜本人にハメられたのかどうか真実を聞いてみたいものだ。
裏の世界では何が起こってるのか想像がつかないところが、恐ろしい。
裏の世界を知っているといえば、私は同姓なことから溝口敦というジャーナリストの密かなファン。彼の著書「チャイナマフィア」によると日本には、中国からの密航を仕切る人がいて、彼らを蛇頭と称するそうだ。
蛇頭は不正入国者から法外な渡航費をせしめる。
私は、てっきり中国<主に福建省>の人々が貧しいから日本や欧米に不正入国するのかと思っていたが、ジャーナリスト田中宇さんの「国際ニュース解説」を読むと、そうではないらしい。
渡航費だけでも、アメリカまで5万−6万ドル(500万-600万円以上)、西欧へ3万−4万ドル、日本へ1万−1万5000ドルも必要。それを蛇頭に支払うわけだから、貧乏人に支払い能力があるわけがない。
おまけに福建省は経済特区などもあり、中国で7番目に平均収入の多い地域で、不正移民を多く出している沿岸地域は、省内でも特に豊かな場所なのだという。
その福建では月に5000円も稼げれば良い方だが、ニューヨークのチャイナタウンの中華料理屋で必死に働けば、月に20万円になるから、出稼ぎにニューヨークへやって来るというわけだ。<田中宇さんの国際ニュース解説より一部引用>
http://tanakanews.com/a0911china.htm
余談だが、以前ニューヨークでは一部のチャイニーズが手軽な料金で簡単に人殺しを引き受けてくれるという噂もあって、時代劇・必殺仕事人みたいな稼業が本当に存在するのだと震えた。
過去プロの殺し屋に殺された日本人は、心の臓を小刀で一突きだったそうだ。
ハーレムのシュガーヒルは昔、リッチなジャズマンも住んでいる高級住宅地だった。が、1994年のウェズリースナイプス主演映画「シュガーヒル」では、同エリアを舞台に兄弟がドラッグディーラーとしてリッチに暮らしている。
その内兄はヘロイン中毒となってしまうのだが、痩せこけてジャンキーになってしまった兄の姿は、かなりエグイ。弟<スナイプス>はドラッグディーラーを抜け出すつもりが、モブ<ギャング>の抗争にもつれ込むというディープなもの。
それは映画の中の話だと思っていたが、ハーレム出身の友人<ブラック現在40代男性>によると、彼の幼なじみのほとんどが、若い頃にドラッグ絡みの抗争で亡くなっているという。
そんな過去をくぐり抜けてきたハーレムは、まだまだ完全に安心しきれない部分を今も残しているといえる。長く盛り場をウロついている平和な顔つきのフォトグラファーのオヤジは、意外に一般庶民の私などが知り得ない裏の世界を知っているのかもしれない。
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第92-2号 辛口コラムシリーズ第九弾 あなたはやらせ派?真実派?
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十二号 03/24/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
〜☆〜☆〜☆〜辛口コラムシリーズ 第九弾〜☆〜☆〜☆〜
*****あなたは「やらせ派」「真実派」?テレビ番組について*****
日本のテレビ番組というのは、裏表を感じさせないように作られている。それは、日本人の生真面目な気質が、そうさせるのだろう。見るほうも目に見えることを信じがちだ。
一文なしでヒッチハイクをして世界を旅した猿岩石というタレントが、「やらせ」問題で大騒動になったことは記憶に新しい。
それに対してアメリカでは、レイ(夫)曰く、たいていの人はテレビ番組を話半分で聞いているという。しかも番組の構成としても、明らかに「やらせ」だという番組と、そうでない番組に分かれている。
ジェリースプリンガーショーなんていうのは「やらせ」の象徴だ。カップルが出てきて、彼女の方が浮気をしてるという真実を告げると、彼氏は驚く、そして彼女の浮気相手が女だったりするのだ。その逆があったりもする。
口論が始まり、ピーッピーッ消音サウンドが鳴り響く。放送禁止用語の嵐となり、Fを頭文字にした罵声が飛び交う。挙句の果てには、つかみ合いや殴りあいになってスタッフが取り押さえるという茶番劇となって幕が下りる。
ある日レイがテレビを見ていると、ある報道番組にサイエンティストが二人出て、狂牛病について話をしていた。感染経路やら、菌の話をトクトクと聞かせたという。
最後に、インタビュアーが「あなた方は、レストランでビーフを食べますか?」と、さり気なく聞いた。
一人は直ぐに、「アメリカのビーフは安全です。私は当然、ビーフを食べます。」と答え。
しかしもう一人は、しばらく沈黙した後、「僕はビーフ以外をメニューか
ら選ぶよ。」と、口篭もりながら答えた。
「この危機感を与えるようなサイエンティストの意見をカットしないで放送するなんて、報道も捨てたもんじゃない。この番組を見てる人は皆、安全だって言葉を期待してたはずだ。僕だってそうだったんだから・・・」とレイは大声をあげて笑った。
アメリカのテレビは視聴者が、よーく判断しないと、真面目な番組でも視聴者が求めている答えを作りだす番組があることも確かだ。安全ではない。と、わかるとパニックになる人が多い国民性もあるからだと思う。
だから、わずかながらでも真実を放送する番組があることを本気で嬉しく思ったらしい。
よってアメリカでは、基本的にテレビ番組の全てを信じるべきではないと考えてる人も多いから真実を取捨選択するのは視聴者で、それは一人一人の意思に委ねられている。
日本のテレビ番組もバラエティーは「やらせ」が多いという事実を関係者から聞いた。しかし「やらせ」だと、わかってしまうと寂しい気もするので、「あまり実情を聞きたくない。夢を見ていたいの。」と私は耳を塞いでいた。
日本のバラエティーは幻想を抱かせてくれる点では最高の出来ばえだと思う。
アメリカでデビューしようと試みた歌手がニューヨークへ移住したエピソードなど、私は、お茶の間から応援していた。だが、それが真実を伝えるべき報道にまで毒されるのは、危険な状況かもしれない。
そういえば、このハーレム日記を書いた後、偶然、大前研一氏著のReBoot<PHP出版>を読んでいると、かつて日本でジャーナリストは、アウトローな人間がなる職業だったのに、いまでは官僚と同じ学校エリートがなる職業になってしまった為、
官僚と同じ発想をする。という意見があった。
私たち一人一人が日本の報道から真実を見極める力をつけておかなければならない情況は必至だといえよう。
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第92-1号 SWAMPウォーターってなんでしょう?
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十二号 03/24/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
*****SWAMPウォーターってなんでしょう?*****
今回、酒飲み隊<友人Aちゃんと私>が向かったのは80丁目のアムステルダム。
週末は若者でごった返すバーボン・ストリートも、さすがに月曜の夜ともなるとシケている。
ので、向かい側のバーに入った。BBQの看板を掲げているが、食事をしてるものはいない。白人や黒人の男性二人組みがバーカウンターにポツポツと座っているのみだった。ワシ等は、その間に割り込む。
カラフルな豚さんのついたキュートなTシャツを着た白人の若い姉さんが酒を注いでくれる。ノーメークでブスな私なんかに声をかけてくる男なんていないはずと踏んでいた私は、薄化粧をして小奇麗なAちゃんには申し訳ないと思いながらもグビグビとビールで喉を鳴らす。
女というものは、そんな貧相な自分を省みず別の女がやってくると対抗意識バリバリとなる。私らがビールを一杯飲み終えた後に入ってきたのは、ヘソ出しの真っ赤なタンクトップにブレードヘア<黒人女性がする編みこみスタイル>、ジーンズ姿もナイスボディーなアジア系の姉さん。
スゥーっと入ってくるなり隣の白人中年男性二人組みと会話を始めた。
「彼女はビッチ<ここでは尻軽女程度の意味>よきっと。」とAちゃん。
「本当だ〜なんだか、ビッチな女ってビッチな顔に、なっちゃうのが不思議よね。」
などと、勝手に見知らぬ初対面の女性をビッチ呼ばわりしている私達がいた。
静かに酒を飲みつづけている内、ビッチは空いている店内でヒップホップの曲に合わせてダンスを始めた。フンと鼻を鳴らし、私は彼女を横目で見る。こんな所で挑発的な女ねぇーまったく。
そんな時、これぞアメリカ!的、豪快な飲み物がバーカウンターに3つも並んだ。「キャー見て見てAちゃん、あのドリンク」
金魚鉢のような容器には、溢れんばかりに注がれた緑色の液体。古池の水のように濁った緑。赤いストローが10本程度刺さっている。これでもかなり大胆な飲みものなのだが、ここにアクセントは子供が風呂場で遊ぶようなプラスチックのオモチャのワニが突き刺してあるのだった。
「なになに?あのドリンク」バーメイドの姉ちゃんに聞くと、「Swamp <沼地>ウォーターよ。」と、まんまのネーミング。
「同じもので小さいグラスのやつは置いてる?」と聞くと「もちろん!」と作ってくれた。それにもスケルトンな緑の小さなワニのスティックが刺さっている。
これはウォッカ、パインジュース、ミドリで作ったカクテルだそうだ。
Aちゃんがトイレに行ってる間、私は一人Swampウォーターを飲み続ける。と、「あちらのお客様からよ。」と、もう一杯Swampウォーターがやってきた。なぬ?!
こんなブスな私に誰が?と、カウンターの先を見ると、ブラックの兄ちゃんの熱い視線がビーム光線となって煌いた。
Aちゃんと半分に分けて飲んでると、あちらのお客様がやって来た。銀縁のめがねをかけた小柄な兄さんだった。「ID見せるよ、僕は62年生まれなんだ。」と聞きもしないのに彼は免許証を見せた。
「僕は、カメラマンでボーグやグラマーなんかの仕事もやるよ。」
「ひゃーそれって有名なファッション雑誌じゃない。ビジネスカードは?」と、ライターな私はコネを作ろうと突然ビジネスビジネス〜躍起になる。
「僕は、遊ぶ時にはビジネスカードは持ち歩かないんだ。仕事のことを考えると楽しみが半減するからね。」
「えーカメラマンだなんて嘘なんでしょー。」と疑いはじめる私。
「それなら、君のビジネスカードは?」
私は、そそくさとカードを探すが都合よく見当たらない。
「あー私も持ってない。でも、本当にライターなのよ。」
ほろ酔いかげんで、すっかりリラックスムードとなった頃。
敵視していたビッチが、どういう人物なのか興味を持った私。
「彼女、なにやってる人なのかな?」と兄さんに問う。
「聞いてみなよ。」と兄さんが、お膳立てして彼女を呼んできた。
酔っ払って大胆になっている私は彼女の顔をマジマジと見た。年齢は私と同じくらいかな。
「あのー突然で失礼ですけど、何のお仕事をされてるんですか?モデルのようにスタイルがいいから。」と聞く。
「私は、仕事でバリからきてるんだけど、雑誌の編集やってるの。」
「そうなんですかぁー私はライターです。」
「同業なのねぇー。」とフレンドリーな笑顔の彼女。
「今夜が最後で、明日はバリに帰っちゃうの。」
「なんだービジネスカードがあれば渡したかったなぁーバリって日本人にとっても人気があって、私も行ってみたい場所の一つなんです。」
彼女はビッチじゃなかったと会話を続けながら勝手に敵視してしまう自分を反省していると、横から兄ちゃんが踊ろうと言い出した。軽く踊り、再びマティーニをゴチしていただく。
その後、電話番号やらEメールアドレスをくれた兄ちゃんは「ボーイフレンドはいるか?」と聞いてきた。夫はいるけど、ボーイフレンドはいないので「いない。」と答える。
私は金属アレルギーのため結婚指輪を着けないせいか「夫はいるか?」と聞かれることは滅多に無い。
タダ酒を数杯あおって、夜中になったので帰ることにした。兄ちゃんが「キャブで送っていくよ。」と何度も繰り返したが、そんな初対面な男に送ってもらうなんて危険すぎるぜイエローキャブ!<By家田荘子>
だが酔っ払って電車に乗った私は、ウエストサイドの125丁目に到着する1・9ラインに乗ってしまった。クロスタウンのバスが、なかなか来ないので、イーストサイドまで夜道をとぼとぼ歩いての帰宅。
仁王立ちのレイ様(夫)が目を剥いて待ち構えていたことは追記しておこう。ごめんなさい〜不良主婦なのね。
<閉店>Bourbon Street
407 Amsterdam Ave
New York, NY 10024
Phone: (212) 721-1332
レシピが見つかったので以下にて。
Swampwater Cocktail
The original recipe calls for 6 ounces of pineapple juice but I prefer a little less, 5 ounces. Feel free to adjust the amount to your taste.
Servings1 drink
- 1 1/2 ounces green Chartreuse
- 5 (or 6) ounces unsweetened pineapple juice
- 1/4 ounce freshly squeezed lime juice
- wedge or wheel of fresh lime
-
Stir together the Chartreuse, pineapple juice, and lime juice in a Collins glass or tumbler.
-
Add ice and garnish with lime wedge or wheel.
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第91-1号 Manhattan Style マガジンのパーティー
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十一号 03/17/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
*****Manhattan Style Magazineのパーティー*****
Manhattan Style Magazineのパーティーがあるというので、行ってきましたAu Bar。ファッションマガジンのパーティーってことで、有名なモデルやらがワンサカやってきて、飲めや歌えや踊れやラリパッパーという状態になることを期待。
いつもはコンウェイ<大量安物衣料品店>星人でダサめな私も、ここぞとばかりに踏ん張って、お洒落な格好をしていかなきゃと、おニューのジャケットで参上したのだった。
誘っていただいたライターのE師匠と、ファッションライターのAちゃん等と列に並んで入場。だが周囲には、さほどファッショナブルな人は見当たらない。
隣にいた女の子に話しかけると、「私はアーサー・アンダーセン<ビジネス・コンサルティングの会社>に勤めていて、友達がマガジンで働いているから誘われたの。」などと、ファッションとは関わりのない人も居るようだ。
中に入るとモデルっぽい人が数人座ってはいるものの、どこからどう見ても普通のクラブ状態。
「しょうがないタダ酒でも飲もうか。」とバーカウンターへ行くが、その人ごみが半端な数ではない。
ホームレスに食事を配られる配給所のようにタダ酒に群がる人だかり。バーメイドの姉さんは酒づくりの作業をカリカリしながら続けている。
前に並んでいるアジア系の女の子二人はピンク色のカクテルをグラスに2つと、メロン色のカクテルをグラスに2つと、オンザロックのウイスキーをグラスに2つとシャンペン・・・。
ちょっと待った〜あんたら、一人につき4杯もオーダーしとるやないの。
一杯のジントニックをすぐに飲干した私は、再び配給所へ列に並ぶ。と、そこには先ほどの4杯オーダー姉ちゃん二人組の姿。
「あんた等さっきの4杯、全部飲んだの?」と問う。「もちろん!こんな混んだ所に並ぶだけでも大変だから、一気にオーダーしなくちゃダメよ。」と元気いっぱいに答えた。
「ここの近くの広告会社に勤めてるの。」と二人ともフレンドリーな女の子。
「クラブは二人で、よく行くの?」と問う。
「そうねぇークラブより、レストランやバーに行ってることの方が多いかな。」
「ここのクラブは行ってみるべし。」と黒いカードをくれた。
「ここは地下にあって解りにくいけど・・・とにかくグッドなの。」
タダ酒タイム終了となったらしく、酒を受け取る人々は金を払っている。
「E師匠、こんなに混んだ所で金払ってまで酒飲まなくても・・・別のバーで飲みなおそうよ。」と外へ出ようとするが、コートを取り戻すのも一仕事。
もはや、満員電車と化したクラブはソファーの上に乗って踊る不届き者までいる始末。
「ひゃー最悪。」と人ごみで不機嫌そうなAちゃん。
「Aちゃんってさーファッションライターってくらいだから、クラブなんて行きまくってるのかと思ってた。」
「滅多に行きませんよー。」どうやら、私のイメージするファッションライターからは逸れているようだ。
ちなみにファッションライターAちゃん曰く、「今のトレンドはベルトですかねぇー。」
どうりで猟師がキツネ狩りで捕獲したキツネの尻尾みたいな妙なベルトを腰に巻いた女がパーティーにいたのだ。
そいつを目にした瞬間、北島サブちゃんが鼻を膨らませて「与作はぁ〜木ぃ〜を切るぅ〜ヘイヘイ・ホーヘイヘイ・ホー。」を歌う姿が頭の中をグルグル回り、クラブの中では、どんなラテン系のヒット曲が流れようとも与作ミュージックで動めいていた私。
プラザホテルで、飲みなおしタクシーに乗って帰った。タクシーのドライバーは10ドル渡したはずなのに、「君、一ドル渡したよ。」と一ドルをピラピラさせてニヤリと笑った。
こいつ〜酔ってるからって馬鹿にしやがって、絶対10ドル渡したのにぃ〜と思ったが、以前15ドルかかったのに5ドルしか持ってなくてトンずらしたことがあったので、渋々金を渡したのだった。<弘恵の格言・自分の悪事は自分に返ってくる>
ってなわけで、今回行ったパーティーは今ひとつトレンドの参考にならなかった。
<閉店>Au Bar
41 E 58th St <bet.Park-Madison>
New York, NY 10022
Phone: (212) 308-9455

☆ハーレム日記リバイバル☆ 第90-1号 ジャマイカンな週末
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第九十号 03/10/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
*****ジャマイカンな週末*****
ハーレム、ブルックリン。カリビアンはNYにたくさんいる。
前大統領クリントン氏が引っ越してくるオフィスビルから東へ、ほんの2ブロック。この辺りにもカリビアンが多い。
ついでに家に住んでいるレイ(亭主)もジャマイカンアメリカンである。だから週末の朝はカリビアンフードを食べるのがお約束だ。
カリビアンレストランSister's Cuisineは、12時近くになると教会から帰ってくる人々ですごい列ができるから、10時前には店に駆け込む。ソルトフィッシュ(魚を塩漬けして乾燥させたものを水で戻したもの)というものを大抵オーダーする。
これはトマトとオニオンと魚を油で炒めて調理してある料理でちょっとだけスパイシー。魚臭さはまったく無い。
同じ器に入っている円盤みたいな揚げパンは、砂糖も塩もついてない。フカフカしていて噛みしめた時に、ほのかな甘味が口に広がる。この薄味のパンとちょっと油でギットリした塩魚の炒め物がぴったりマッチする。
トマトの酸味もにくい。
私の場合はパラパラした白いご飯と、ねっとりしたオクラを細かく切って煮てあるものを、ソルトフィッシュのサイドでオーダーする。
日本人同様、基本的にはカリビアンもご飯が主食であるから、馴染みやすい。
ビーンズライスは日本のお赤飯みたいなもので、ジャークチキン(チキンにスパイスをふりかけてベークしてある。)やシチューチキン(甘辛く煮つめてある)とランチやディナーに食べたりする。
日本人だと、お茶碗に白いご飯、お椀に味噌汁、細長い皿に焼き魚。と区切りをつけて、口にするときに味をミックスするのが普通の状態だが、ジャマイカンフードは一枚の大きな皿にサイドからメインまで料理を全てのせて食べる。
しかも料理をよそってくれる姉さんが「グレービー(肉汁)をかける?」と聞いてくる。ご飯の上にトロリとかけられるグレービー。
「ニャンニャンまんまみたいねー。(猫の餌のこと)」初めて母がカリビアンフードを口にするときにコメントした。
この他、オックステールやカレーゴートなんかもメニューにあるが、匂いが苦手な私はオーダーしたことがない。
ロティーという食べ物が、同じくカリビアンレストランFlavored With One Loveでは好評だ。カリブでも小さな島、トリニダッドという国で主に食されているのだという。
クレープみたいな生地の中にチキン、カレーポテト、ビーンズ、野菜の炒め物。好きなものを包んでもらう。シュリンプを何度かオーダーしたが、メニューに書いてあるだけで、いつも売り切れ。
「本当にエビ仕入れてるの?」と首をかしげるが、チキンとカレーポテトでも十分満足できる。
この辺りにたむろするのは、アクセントのある英語をしゃべるカリビアンがほとんどだが、ドレッドヘアーにしたアメリカンも存在する。
「カリビアンでドレッドにしてるのは、アーティストがほとんどだよ。一般人はドレッドになんかしない。」と亭主から耳にタコができるほど聞かされている私。
白髪でドレッドにしているブラックの爺さんがひなたぼっこしていたので、
「カリビアン?」と問うと、
「アメリカンだ。」と肩をすぼめた。
「どうしてドレッドにしてるの?」と聞いたら、
「カッコイイから。」と子供のように素直に答えた。
レゲエのスタイルにあこがれるアメリカン、ジャマイカンのアクセントを真似て喋る者まで存在するのだという。
ハーレム日記に登場したカリビアンの店
Sister's Cuisine
124 Madison Ave.<124st bet.Mad-Park>
New York, NY 10016-7004
Phone: (212)410-3000
Flavored With One Love
1941 Madison Ave.<bet.124-125st>
New York, NY 10035-1801
Phone: (212)426-4446
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第89-2号 辛口コラムシリーズ 第八弾 英会話を学ぶなら
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第八十九号 03/03/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
〜☆〜☆〜☆〜辛口コラムシリーズ 第八弾〜☆〜☆〜☆〜
*****英会話を学ぶなら*****
ある日、地下鉄に乗っていると日本人の女の子二人が乗り込んできた、一人は私の横に座って、一人は私の前のポールを手にして立っている。
どうやら私を中国人と思ってるらしい。どうして中国人だと思ってるのかといえば、ガラガラに空いてる車両の中で、一人は横着にも私の顔に唾が飛んできそうなくらいの距離に立って大声で話し始めたからだ。
明らかに東洋人では日本人が一番偉いのよ。と、言わんばかりの態度だった。
「Yちゃんさぁー日本に帰るんだって、『帰るんだったら、何か頂戴』って言ったら、『全部、日本に送る』って言うの、ケチだと思わない?」
「そうなんだー。」相槌をうつ一人。
「さすがに植物は置いて帰るみたい。」
「植物は送れないわよね。」
「ポトスをサぁー貰おうかなぁーって思って。玄関の所に置くと、いい感じかなぁ。」
「でも植物は、あそこのアパートに元々ついてた物なんじゃない?」私は余計な世話だが肩がワナワナと震えてきた。ポトスぐらいテメーが買え!このドケチ。
ポトスなんて、茎や根の分け目から分離させて水につけておけば、成長して、いくらでも増えるのに、そんなことも知らん奴が植物なんて育てられるんかぁー。
と、頑固じいさんにように大声で怒鳴りたい衝動にかられながら、寝たふりをする私。
途中で席が空くとドケチ女が向かいの席に座って更に大きな声で話し始めた。
「ねぇーKちゃん、ここの英会話の学校って難しい?」「そうねー私にとっては難しい。」
「ところでさぁーon my wayの意味知ってる?」
「どこどこに向かってるとかって意味よ。例えばさぁー、電話で友達の家に向かってるときにI'm on my way.とかって使うの。」ちょっと待ったー。
てめーon my wayなんて中学生レベルの英語やないかぁーそんなんも知らんもんが、わざわざニューヨークまで英語習いに来るなー。
基本くらいは日本で勉強して来い。と再び、頭にガツンと一発、頑固オヤジの堅いゲンコツを食らわせてしまいそうな衝動にかられながら、あくびをするフリをした私。
こいつら、親から金出してもらってニューヨークに来てまでon my wayの意味を教わってるのかと思うと腹立たしい。そのせいで私の体内は、まさにストレスを受けてる反応が展開していた。
かなりアルコールで傷めつけられた胃袋にドクドクと胃酸が注ぎ込まれ、熱を帯びた胃酸が耳と鼻から溢れてきそうなまでの勢い。
この怒りを、どこにぶつけよう。そうだハーレム日記に書いてしまえ。
と、on myway…on my wayとダウンタウンでショッピングする間も彼女たちの言葉を忘れないよう繰り返していた。
英会話学生でも劣悪な奴にかぎって、日本に帰ったらニューヨークで英語を学びました。ニューヨーク帰りです。って気取ってるに違いない。
幸い、ハーレム日記を愛読してくださる学生の皆さんはレベルの高い人ばかりなので有り難い。
もっとも前述の女の子たちにはハイレベルなハーレム日記を理解できないかもしれない。
<自意識過剰になってみました>ちなみにハーレム日記の読者層はというと、コンピューター関係に勤める男性や、ニューヨークへ留学したいという女性からのメールが多い。
一度、男性読者と女性読者と職業のアンケートでもとってみようかなぁー。
☆ハーレム日記リバイバル☆ 第89-1号 レイ(夫)との出会い編
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
第八十九号 03/03/2001
Harlem日記
■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■
今日は、日本の主婦層を知るためにと、最近、日本の主婦が読んでいるという不倫モノ系エッチなレディースコミックなる本を購入したら、ビニ本だったため中が確認できずYOUという本を購入したが、ただの少女漫画だった。
どの本がエッチなコミックか教えてください神様。
*****レイ(夫)との出会い編*****
読者の中にレイと知り合った、きっかけを教えて欲しいとのメールをたくさんいただいているので、私事ながら書いてみましょう。
彼と出会ったのはバーンズ&ノーブルという本屋で、コンピューターの本を探しているときに・・・っていうのは嘘である。
一度、レイの大学時代の友人の結婚式に二人で行った時、「どこで二人は知り合ったの?」と聞かれ、
「あ〜それがぁ〜本屋でぇ・・・ってのは嘘でクラブで知り合った。」とレイが体裁を気にして、ついつい先に本屋と口走ったこともある。
が、実際は作家の山田詠美さんがニューヨークで、お気に入りのクラブとしてピックアップしていたらしいBentleyというクラブで知り合った。
今は、閉店してしまっているのだけど、グランドセントラルステーションの近くあるブラックの兄ちゃんばかりのゲットーな、とんでもないクラブだった。
一度などは、踊ってる最中に胴上げのように男性3人に抱え上げられて、襲われるんじゃないかと慌てて悲鳴をあげたこともある。
週末ともなると、ヒップホップとレゲエ中心のフロアは芋の子を洗うように混んでいた。
ブラックばかりなので、ともかくアジアの女は珍しく、声をかけられまくった。
だから、誰から声をかけられても、全て無視していたわけである。
レイは、「飲み物おごってあげるよ。」と言ってきた。「要らない!」と断った。レイは諦めた様子で、数分間、私からちょっと離れた所で静かにダンスフロアを観察しながら立っていた。
私は再びレイをマジマジと見る。ターミネーターの如く、Face OK…Style OK…Fashion ダメダメ!の文字が視覚モニターに描き出される。
5つ☆判定の結果、総合評価☆☆☆☆。とりあえず話してみようと、私はビーム光線を発散しながら攻撃態勢に入る。
「ジン・トニックが飲みたい。」と言えばレイが酒を買ってきた。
<今となっては、酒なんか買ってやれるもんか、このアルチュウワイフめぇーと断られている。>
酒を飲みながら会話をはじめた。ちなみにレイは酒を飲まないタバコも吸わない、ジャマイカンだからといってステレオタイプのマリファナ・スモーカーなんて口にしようものなら叱られるぜベイビー。
まずは氏名・年齢・職業・住まいといった懸賞つきテレビ番組の終わりに応募ハガキに書き込まなくてはならない事項を聞き出す。
住まいはNY郊外だという。<ボンボンじゃないか>仕事はコンピューター関連。
「アセンブラは使ったことがあるか?C言語はどう?UNIXは?」などなど、レイが以前はプログラマーだったこともあるということから、面接官のように細かいことを聞く。
年齢は27歳。「見た目からして、ティーンエイジャーじゃない本当なの?免許証見せて。」と婦人警官ばりにIDの提示を要求する。
「一人で来てるってことは彼女はいないの?」と聞き込みは大詰に入った。
そして、数曲ダンス。ブラックでも踊りの下手な奴がいる。
友人の彼氏だったブラックの男性は背が高くてハンサムだったが、踊らせるとデビュー当時の吉川晃司氏のバッタ・ダンスのように前傾姿勢で上半身を前後に揺すったり、下半身をバタバタさせたりという訳のわからないダンスを披露した。
それに比べるとレイはダンスもOK。
「僕、そろそろ帰らなくちゃ。」と電話番号だけ交換して、レイは早々に<といっても午前2時くらい>クラブを出た。
後談によると、彼は私のことをラテン系だと思っていたらしい。派手なシマウマ模様でラメ入りのタンクトップを着ていたせいだろうか?
そして、彼との初デートの話は次回に続きます。