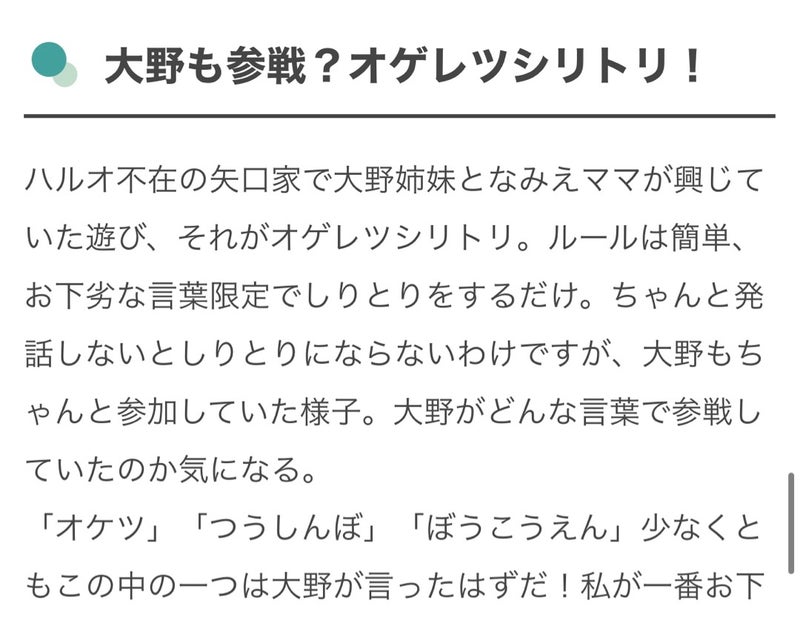「今日スト2しに行っていい?」
【ミニカーの走行距離 第6㌔】
ふっきゃとは中学3年で同じクラスになった。
名前は福山。あだ名がふっきゃ。
僕らの中学校では男子3人女子2〜3人で1つの班になるという班分けがあって、確か学期ごとに班は変わってたはずなのだが、ふっきゃと恵美須と僕と釜堀さんと小濱さんの5人の班だった時の記憶しか今の僕には残っていない。
子供がよく遊ぶゲームというものは時代によって移り変わっていくものだが、当時の僕らの主流となっていたのはとにもかくにもスーパーファミコンだった。
ここからはまだまだ据え置き型家庭用ゲーム機の時代が続き、スーパーファミコンの後はプレイステーションやセガサターンの時代になっていく。
スーパーファミコンの時代にもPCエンジンCD-ROM2なんてものもあったが、やはり圧倒的シェアを誇っていたのはスーパーファミコンであった。
スーファミが家にあるかないかで、友達が家に遊びに来る率が大幅に変わる。
そしてもちろん何のソフトがあるのかが重要で、流行っているソフトは大体なんでもあるなんて家は稀だった。
というか少なくとも僕の友達にはそんなボンボンはいなかった。
兄2人が高校生でバイトをしていたことにより、我が家には比較的多くのソフトが置いてあった。
ドラクエやFFシリーズは当然揃っていたし、むちゃくちゃ流行ったストリートファイター2もあった。
スト2はスーファミでの2作目にスト2ターボが出て、3作目のスーパースト2が出る少し前くらいの時期だったと思う。
僕は毎日高校の受験勉強もせずにスト2に明け暮れていた。
主にケン、ガイル、ブランカ、春麗を使っていた。
リュウは絶対に使わなかった。
当時さほど性能差はないのにケンを使っていたあたりからも、僕が当時から硬派なキャラよりも金髪ロン毛のチャラチャラしたキャラを好む傾向があったことが窺える。
そして僕のガイルはめちゃ強かった。
ソニック投げや待ちガイルと言われる卑怯な戦法も遠慮なく使っていた。
ブランカもローリングアタックが対空技として使えていた初期はかなりの強さを誇っていた。
自宅のスーファミ版で練習して、アーケード版の対戦台で腕試しするというのが当時のファイター達のスタイルだったように思う。
ちなみに春麗は弱かった。
スピニングバードキックを出してスタートボタンを押してストップしてきわどい春麗の股間を見るというのは、当時の思春期の男子ならば誰もが通る道だっただろう。
そして我が家にはまだマリオカートがなかった。
まだというのは、後から兄が買ってくることになるのだが、今から書くこの日にはまだ家にマリオカートがなかったということだ。
僕は友人の家でやらせてもらったマリオカートが面白すぎて、マリオカートやりたい病にかかっていた。
ふっきゃはマリオカートを持っていた。
ふっきゃはスト2は持っていなかった。
その日の放課後、ふっきゃは僕の家に来たがり、僕はふっきゃの家に行きたがった。
お互いに普段できないゲームがやりたい気持ちを譲れないでいた。
そんな僕らがとった解決策は、ふっきゃが一度家に帰ってマリオカートを持って僕の家に来るというものだった。
僕らは別々に家に帰り、僕はマリオカートを……ふっきゃを自宅で待つことになった。
ピーン………………ポーン。
当時僕が住んでいたマンションはオートロックで、入口の自動ドアは4桁の暗証番号を入力すると開く。
その暗証番号を既に知っていたマリオカー……ふっきゃは、玄関の前のインターホンを押す。
インターホンを押すとピーン、離すとポーンとなる我が家のインターホンを、この押し方するのは間違いなくマリオカート福山だった。
ピーンとポーンの間の3秒間のその刹那、彼は何を思っていたのだろうか。
今となっては知る由もない。
僕はロケットスタートで玄関へ駆けていく。
「うぇーい、あがってよー」と言う僕にふっきゃは第一声でこう言った。
「ごめん、マリオカート持ってきてない」
……何しにきたんだこいつは。
明らかにテンションダウンする僕を見て、ふっきゃは代わりにポテトチップスを持ってきたとか言い出す始末。
ポテチ食いながらスーファミのコントローラー持てんだろ。
おめーはポテチ食った手でひとんちのコントローラー持ってスト2するつもりだったのか。
「いや、持ってこようと思ったら弟がタイムアタックやりよったんよ」
理由もよくわからない。
「そこは兄ちゃんなんやけん、持ってくぜーとかで持ってこれんやったん?」
「いや、あいつのタイムアタック邪魔したらやべーよ」
どんな兄弟関係だよ。
仕方なく、僕はふっきゃとスト2を始める。
スト2に限らない事だが、対戦ゲームというのはある程度実力が近くないとどちらも面白くない。
僕はマリオカートができない怒りを、待ちガイルでソニックブームで牽制しつつ、ジャンプしてきた相手をサマーソルトキックで倒してからの起き上がりにソニックブームを置き、ガード硬直の間にバックドロップで投げるという初心者にはどうすることもできない戦法でふっきゃをコテンパンにすることで解消した。
1時間もするとふっきゃは「もうスト2やりたくない」と言い出した。
他のゲームをやろうにもRPG多めだった小車家では遊べそうなソフトもなく、ふっきゃの家に移動しようということになった。
「マ……マリオカートができる!」
当時よく自転車をパクられていた僕は自転車がなく、ふっきゃの自転車の後輪のところにハブステップと呼ばれた足場となる棒を取り付けて2人乗りでふっきゃの家に向かうことになった。
良い子のみんなは絶対に真似してはいけない。
私服に着替えていたふっきゃはリュックを背負っていて、後ろの僕はそれが邪魔で立ちにくかった。
僕のマンションからふっきゃの家に向かう時、最初に長い下り坂がある。
最初はそこまで急じゃないのだが、途中から角度がFUJIYAMAみたいになる。富士急行ったことないけど。
二人乗りでその坂を下り出したと思ったら、ふっきゃは突然ノーブレーキで坂を下り始めた。
「ふっきゃ!危ない危ない!死ぬ死ぬー!」
怖がる僕にふっきゃはクールに答える。
「死にやせんって」
そんなに僕のガイルが憎かったのか!
こういうのって運転してる方は意外と怖くなくて、後ろに乗ってる方が断然怖い。
自転車はFUJIYAMAゾーンに差し掛かり、トップスピードへと変わっていく。
FUJIYAMAゾーンを抜けると左側が車一台通るのがやっとくらいの細い道と、右側が開けた駐車場になっている分かれ道というか、その二つを隔てるブロック塀が現れる。
右はただの開けた駐車場なので行き先は左。
当然ふっきゃは左に重心をかける。
僕はあまりのスピードに怖がりすぎて、ここは右の開けた方に一旦逃げた方がいいと判断して右に重心をかけた。
そんな二人の思いが綺麗に相殺し、自転車はたった幅20cm程度のブロック塀の仕切りに猛スピードで真っ直ぐ進み衝突した。
ガシャーン!!
その辺に転げる二人と自転車。
「あはは……いってー。ふっきゃ大丈夫?」
僕はちょっと下腹部を打ったくらいでほぼ無傷。
ふっきゃの背負っていたリュックと、その中に入っていたポテトチップスがちょうどエアバッグのような感じになり、僕は余裕で笑っていられる程度だった。
後から聞いた話によるとリュックの中のポテチは破裂していたらしい。
「……大丈夫じゃない」
ふっきゃは顔面蒼白だった。
「え?」
「腕が痛い」
ふっきゃはそのたった20cm程度のブロック塀にあのナムさんの大技、天空×(ペケ)字拳をかましていたのだ。
動けないでいるふっきゃと立ちすくむ僕らの横を自動車が通りかかる。
運転手のお兄さんが降りてきて「大丈夫?」と声をかけられた。
結局ふっきゃはその人に家まで送ってもらうことになり、僕はふっきゃの自転車を押してふっきゃの家まで行った。
前輪が曲がっていて乗れる状態ではなかった。
自転車を送り届けると、ちょうどふっきゃが母親と車に乗って病院に行くと言っていた。
部屋の中からは微かにマリオカートの音楽が聴こえてきて、兄の一大事に弟はまだマリオカートをやっていることだけはわかった。
どんな兄弟関係だよ。
「死にやせんって」
ふっきゃの言葉が蘇る。
いつになくクールに決めたそのセリフは、まるで死亡フラグのように鮮やかだった。
次の日、学校に行くとふっきゃは元気よく登校してきたが、なんと両腕を骨折しており両腕にギブスをつけてきた。
確かに死にはしなかった。
周囲からは面白がってどうしたの?と聞かれまくっていたが、ふっきゃは「おぐしょう(僕のあだ名)の家にスト2しに行ったらこうなった」としか言わなかったため、ふっきゃはきっとベガのサイコクラッシャーのしすぎで骨折したんだろうと噂になった。
いや、似てるけど違う。
天空×字拳なんだ。