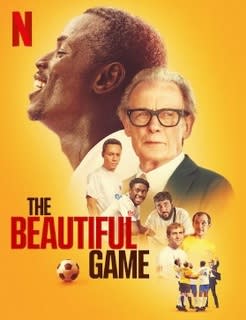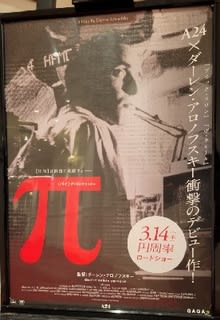(原題:WHISKY)2004年ウルグアイ=アルゼンチン=ドイツ=スペイン合作。監督のフアン・パブロ・レベージャとパブロ・ストールは“南米のアキ・カウリスマキ”と言われているそうで、冴えない中年男女を主人公にしている点や徹底的にストイックな作劇には共通点がある。だが、北欧の巨匠の作品群よりも上映時間は若干長く、それだけに登場人物の追い詰め方は堂に入っている。同年の東京国際映画祭でコンペティション部門のグランプリと主演女優賞を受賞。第57回カンヌ国際映画祭でも“ある視点”部門のオリジナル視点賞を獲得している。
ウルグアイの下町で零細な靴下工場を経営するユダヤ人の主人公ハコポは、控え目だが忠実な中年女性マルタを工場で雇い入れている。ハコポとマルタが一緒に仕事をするようになってから長い年月が経っているのだが、2人は必要最小限の会話しか交さない。そんな中、ブラジルで成功したハコポの弟エルマンから訪ねてくることになる。
ハコボは長らく疎遠になっていた弟が滞在する間、マルタに夫婦のフリをして欲しいと頼み込み、了承を得る。早速2人は偽装夫婦の準備を始め、結婚指輪をはめて一緒に写真を撮りに行く。こうしてエルマンを迎えることになるのだが、事態は思わぬ方向に転がり出す。
結局、人間は見かけはどうあれ中身は千差万別なのだ。ハコポとマルタは単調な日常を送るだけの退屈な人物に見えるが、エルマンの滞在を切っ掛けに、2人は実は正反対の性格だったことが明らかになるという、その玄妙さ。
陽気で如才ない弟から仕事を手伝いたいとの申し出を受け、それが自分の利益になることを分かっていながら、今までの単調な生活を崩したくないため断ってしまう主人公の被虐的なキャラクターと、チャンスさえあればどんどん外の世界に出て行きたいという欲求を抑えたまま生きてきたヒロインとの対比は、残酷なまでに鮮烈だ。
これがハリウッド映画ならば、二人は夫婦の真似事をするうちに相思相愛になるという手垢にまみれたハッピーエンドに持って行くところだろうが、本作はストーリーが進むほどにそんな予定調和から遠ざかってゆく。フィルムが断ち切られたようなラストも秀逸だ。ウルグアイとブラジルとの国情の違いや、ユダヤ人の“法事”みたいな風習が紹介されるのも興味深い。
アンドレス・パソスにミレージャ・パスクアル、ホルヘ・ボラーニといったキャストはもちろん馴染みが無いが、皆良い演技をしている。なおタイトルの意味は、日本では写真を撮影するときに被写体の人の笑顔を撮るため“チーズ”と言わせるが、南米ではそれが“ウィスキー”になるところに由来している。