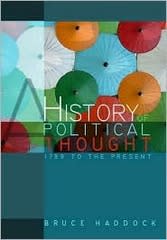7月の19日から21日まで、イタリアのフィレンツェにほど近いプラートという小さな街で開かれた表題の学会に行ってきました。
これはCollingwood Societyが2,3年ごとに開催している国際学会で、前回は2007年秋にモントリオールで開かれ、PhD1年目の初々しかった私も(笑)、発表はせずに半ば観光気分で参加したものです。今回はPhD終了直前でもあり、またこれまでに数回の発表を経てきた上でPhD論文の最終章の一部を発表するということもあり、ある意味でPhD時代の総決算とも言うべき学会でした。
今回は、ヨーロッパでの開催ということもあり、前回多く参加した北米の研究者は少なかったものの、英・伊・露・蘭・ポーランド・ハンガリーなどの欧州勢、米・加の北米、そして今回の主催者であるオーストラリアの研究者と、一応国際学会の名に値する多彩な顔ぶれとなりました。
私自身の発表は、コリングウッドの倫理思想の核心といえる義務の概念を、プリチャード、キャリット、ロスら当時のオックスフォード実在論者たちの議論の建設的な発展としてとらえ、コリングウッドが実在論者たちの議論をどのように発展させたのかという点を、コリングウッドの道徳哲学講義を中心に実在論者たちの著作を参照しながら明らかにしようという試みでした。オックスフォード実在論は、倫理的にはOxford Intuitionismとも呼ばれ、moral particularismなど現代倫理学においても再び脚光を浴びている思想群であるにもかかわらず、それらを批判的に吸収したコリングウッドの倫理学はこれまでほとんどオックスフォード実在論との関係で論じられたことがなかったため、今回の発表の扱うことにしました。そういう意味で、単にコリングウッド研究にとどまらず、moral particularismを媒介として現代倫理学においてコリングウッドをどう再評価できるかという問題の出発点を意図しました。
相変わらず発表の技術的問題は改善の余地があるものの、聴衆の反応は上々でした。PhD期間を通してかなりお世話になっているハル大のC教授からは、very interestingと興味を示していただき、君のPhD論文を私は読む必要がある、と言われました。さんざんお世話になっているので完成したら言われるまでもなく謹呈する予定です。また、米・カンザス大の大御所的なM教授を含め、多くの参加者からいい発表だったと言っていただきました。いい感触を得ることが出来たので、今後はこれを手直しし、よりメジャーなジャーナルへの投稿を目指したいと思います。
他の発表で私として興味深かったのは大きく2点ありました。
一つ目はコリングウッド研究内在的な問題で、後期コリングウッドにおけるA・J・エイヤーら論理実証主義の影響に関わる研究です。というのも、コリングウッド哲学には「急進的転向仮説」なるものがあって、実在論批判を徹底する前期とエイヤーらの批判を受けて実在論に説得されたという後期という説があります。私自身はコリングウッドの立場は根本的には一貫しているというものであり、PhD論文でも前期の彼の実在論批判の分析を元に後期の思想を紐解けばかなりいろんななぞが解けるのではないか、という期待に言及するのですが、そういう意味で、この点に注目している研究者が複数いたというのは、ひとつの課題として取り組む価値を再認識させるものでした。
もう一つは、今後の自分の研究の発展方向に関わって、政治哲学におけるrights recognitionの問題に取り組むというのはひとつの選択肢だということがはっきりした点です。これは私の指導教授の戦略でもあり今回も発表をしていたのですが、彼を含め何人かの研究者によるこの問題に絡んだ発表は、自分の研究の方向性として検討に値すると思いました。また、事前アブストラクトを見たのか、シェフィールド大のV教授に私がまだ発表していない段階で声をかけられ、君の研究はこの問題を考える上で興味深いと言われたこともあり、基本的な勉強をしてみようと思いました。
その他、さまざまな発表があり、国際的なレベルでコリングウッド研究の最前線の見取り図を得ることが出来ました。
今回の開催地であるプラートの、からっと晴れ渡った天候とアットホームでこじんまりとした雰囲気も手伝ってか、多くの参加者はとてもリラックスした表情で参加しており、普段英国で参加したときにはとても緊張したり気難しい雰囲気だった人たちも、とても陽気でフレンドリーになっていて、学会終了後のディナー時やそのあとの飲みなどで友好を深めることが出来たのも収穫でした。特に、前回モントリールの学会を主催していた日本人研究者の方と再会しさまざま相談をさせてもらったのもありがたい機会でした。
2年後の次回は再びカナダで、カルガリーとのこと。そしてハル大のC教授が、その次の4年後は日本でやろう!と冗談とも本気ともつかない提案を私にして来たのに面食らいつつ、でもそれができるだけの地位(職)・力量・経験を4年後までにはもっていないといけないという意味で捉え、その提案を実現できるような自分になっているように精進しようと心に期して帰ってきました。
これはCollingwood Societyが2,3年ごとに開催している国際学会で、前回は2007年秋にモントリオールで開かれ、PhD1年目の初々しかった私も(笑)、発表はせずに半ば観光気分で参加したものです。今回はPhD終了直前でもあり、またこれまでに数回の発表を経てきた上でPhD論文の最終章の一部を発表するということもあり、ある意味でPhD時代の総決算とも言うべき学会でした。
今回は、ヨーロッパでの開催ということもあり、前回多く参加した北米の研究者は少なかったものの、英・伊・露・蘭・ポーランド・ハンガリーなどの欧州勢、米・加の北米、そして今回の主催者であるオーストラリアの研究者と、一応国際学会の名に値する多彩な顔ぶれとなりました。
私自身の発表は、コリングウッドの倫理思想の核心といえる義務の概念を、プリチャード、キャリット、ロスら当時のオックスフォード実在論者たちの議論の建設的な発展としてとらえ、コリングウッドが実在論者たちの議論をどのように発展させたのかという点を、コリングウッドの道徳哲学講義を中心に実在論者たちの著作を参照しながら明らかにしようという試みでした。オックスフォード実在論は、倫理的にはOxford Intuitionismとも呼ばれ、moral particularismなど現代倫理学においても再び脚光を浴びている思想群であるにもかかわらず、それらを批判的に吸収したコリングウッドの倫理学はこれまでほとんどオックスフォード実在論との関係で論じられたことがなかったため、今回の発表の扱うことにしました。そういう意味で、単にコリングウッド研究にとどまらず、moral particularismを媒介として現代倫理学においてコリングウッドをどう再評価できるかという問題の出発点を意図しました。
相変わらず発表の技術的問題は改善の余地があるものの、聴衆の反応は上々でした。PhD期間を通してかなりお世話になっているハル大のC教授からは、very interestingと興味を示していただき、君のPhD論文を私は読む必要がある、と言われました。さんざんお世話になっているので完成したら言われるまでもなく謹呈する予定です。また、米・カンザス大の大御所的なM教授を含め、多くの参加者からいい発表だったと言っていただきました。いい感触を得ることが出来たので、今後はこれを手直しし、よりメジャーなジャーナルへの投稿を目指したいと思います。
他の発表で私として興味深かったのは大きく2点ありました。
一つ目はコリングウッド研究内在的な問題で、後期コリングウッドにおけるA・J・エイヤーら論理実証主義の影響に関わる研究です。というのも、コリングウッド哲学には「急進的転向仮説」なるものがあって、実在論批判を徹底する前期とエイヤーらの批判を受けて実在論に説得されたという後期という説があります。私自身はコリングウッドの立場は根本的には一貫しているというものであり、PhD論文でも前期の彼の実在論批判の分析を元に後期の思想を紐解けばかなりいろんななぞが解けるのではないか、という期待に言及するのですが、そういう意味で、この点に注目している研究者が複数いたというのは、ひとつの課題として取り組む価値を再認識させるものでした。
もう一つは、今後の自分の研究の発展方向に関わって、政治哲学におけるrights recognitionの問題に取り組むというのはひとつの選択肢だということがはっきりした点です。これは私の指導教授の戦略でもあり今回も発表をしていたのですが、彼を含め何人かの研究者によるこの問題に絡んだ発表は、自分の研究の方向性として検討に値すると思いました。また、事前アブストラクトを見たのか、シェフィールド大のV教授に私がまだ発表していない段階で声をかけられ、君の研究はこの問題を考える上で興味深いと言われたこともあり、基本的な勉強をしてみようと思いました。
その他、さまざまな発表があり、国際的なレベルでコリングウッド研究の最前線の見取り図を得ることが出来ました。
今回の開催地であるプラートの、からっと晴れ渡った天候とアットホームでこじんまりとした雰囲気も手伝ってか、多くの参加者はとてもリラックスした表情で参加しており、普段英国で参加したときにはとても緊張したり気難しい雰囲気だった人たちも、とても陽気でフレンドリーになっていて、学会終了後のディナー時やそのあとの飲みなどで友好を深めることが出来たのも収穫でした。特に、前回モントリールの学会を主催していた日本人研究者の方と再会しさまざま相談をさせてもらったのもありがたい機会でした。
2年後の次回は再びカナダで、カルガリーとのこと。そしてハル大のC教授が、その次の4年後は日本でやろう!と冗談とも本気ともつかない提案を私にして来たのに面食らいつつ、でもそれができるだけの地位(職)・力量・経験を4年後までにはもっていないといけないという意味で捉え、その提案を実現できるような自分になっているように精進しようと心に期して帰ってきました。