自分のブログに自費で観に行った公演の正直な感想をそれなりに根拠を添えて書いてすらクレームが来るなんて
あまりにもびっくりしてしまって、驚いている間になんと一年以上が経ってしまいました。
Madokakipがへこんでいるのかな、と心配してくださったのでしょうか、励ましのお言葉、
それからさりげなく記事のupにつながるような心配りで書いてくださったと思われる内容のコメントもいくつかコメント欄に頂きました。
その方々には心からのお礼と、そして長らくお返事を差し上げなかった非礼をお詫び申し上げます。
どうぞ、ご心配なきよう、あのようなコメントをいただきましても、”ああ、これまで書いていたことの本質が全く伝わっていない相手もいるんだな。
時間と労力かけて一生懸命書いていた私が馬鹿だったな。なんか、必死こいて記事を書くのがめんどくさくなったな。”と思うことはあれ、へこむというような脆弱なメンタリティは持ち合わせておりません!
仕事も忙しくなって来たし、これでフェードアウトもありかな、まあ、こうして放置していればだんだん閲覧件数も減っていくだろう、と思っていたのですが、
先日久しぶりに記事の編集ページに行ってみて、あまり閲覧件数が減っていないのにびっくりしまして、
よもやgooの閲覧カウンターが壊れているんじゃ、、、との思いも頭をよぎりましたが、もしかして、もしかすると、書き込みをして下さった方々をはじめとして、
いつかこのブログが復活するのではないかと思って時々のぞき続けて下さっている方がいるのかもしれない、、、と思うと、なんとも申し訳ない気持ちになって参りました。
それに、このブログに終止符を打つのであれば、人のブログに土足で踏み込んで、偉そうな値踏みをしていく輩にタイミングを決められて自然消滅するのではなく、
自分の意志できちんと皆様にご挨拶をして幕を引きたい、とも思いました。
オペラへの愛は子供のしつけに対する考え方と似ていると思います。
ある人は、愛情があるなら厳しいことを言わずにのびのびと育てればよい、と思うし、ある人は愛があるからこそ、厳しいことのひとつやふたつ、、、とも思う。
けれども、人の家にずかずかと入り込んで、あなたのしつけのやり方は子供に厳し過ぎるから、ゆえに子供を愛していない、というようなことを決め付けて、だからもっと優しく接しなさい、と押し着せてみたりだとか、
逆にあなたは甘やかし過ぎだから、もっと厳しくしなさい、なんてことをずけずけ言ってのけるのは、分をわきまえない失礼な行動であるということを自覚して欲しいと思います。
それは、その家の人間が本当に子供を愛している場合、なおさらで、ほんと、余計なお世話とはこのことです。
人の愛情の表現の方法は色々で、どれが絶対に正しいなんてことはないはずです。
他の事ならともかく、私のオペラに対する愛情を疑問視したり、オペラが好きならこういう行動をとるべきだと強制するようなコメントはここでは二度と見たくないので、よろしくお願いいたします。
それから、愛する対象への厳しい言葉は、それがどれほどきつくあろうとも『悪口』とは性質を異にしますので、そこの見分けもつかない方には、このブログは全く向いてないと思います。
他にもたくさんオペラについてブログに書いていらっしゃる方はおられると思いますし、その中にはお花畑のようなブログもあるでしょうから、どうぞそちらを楽しまれてください。
また、私がチエカさんのブログの一部の読者のグリゴーロバッシングに対して苦言を申し上げたのは、彼らがグリゴーロに対してネガティブなことを書いているからでは全くありません。
彼らが実際に公演に足を運んでそう感じられたなら、”ふーん。そういう見方もあるのか。”と思うだけです。
私が軽蔑するのは、実際の公演に足を運ぶことすらしないで(はい、私はどのサインネームの方が実際にグリゴーロの公演を見たこともないということを知る程度にはチエカさんのサイトを頻繁にチェックしています。)、
YouTubeやらでちょい聞きした程度で歌手の歌唱を”二流”と決めつけ、
関係のない歌手の話をしている時にまで、ことある毎にその歌手を引き合いに出して貶める、そういうオペラファンなのであって、そういう人たちは本当に”暇な人”だと思います。
だけど、実際に聴きにいった公演の、ある歌唱に対する印象が全くよくなかった、それをきちんと理由だてて、その公演、もしくはその公演と何らかの関係のある・比較が有効な公演の記事の中で説明するのは全く必要かつ当然なことだと思うし、
それをやったからと言って”その言葉、お返しした”いと言われる筋合いなんてどこにもないと思います。
さっき書きました禁止事項以外のことであれば、どれだけ私のある歌手への評価に反対!という意見であっても、
なぜそう思うのか(単純に声が好きだから、顔が好きだから、、、何でも構いません)を合わせて教えて頂けるのであれば大歓迎! 喜んでお話させて頂きたく思います。
というわけで、この一年は全く公演の感想の覚書もとってませんし、今となっては2013-14年シーズンに見た公演全部の感想をupするのは不可能なんですが、記憶の新しいものや記憶に残った度が高いものを中心に、
またメトのシーズンオフ中にもいくつか観に行く予定の他カンパニーの公演(オペラ以外にも、バレエやみやびさんがコメント欄で教えてくださった歌舞伎のNY公演も含め)がありますので、それらと合わせてメトのシーズン・オフ中も記事をupしていこうかな、と思っております。
で、とりあえず、記憶の新しいところから、またbchamaさんの不運をカバーすべく、フローレスが復帰した、シーズン第四回目の『チェネレントラ』となる5/2の公演のレポートで復活したいと思います。

メトの2013/14年シーズン中、最も話題だった歌手の一人がハヴィエ・カマレナです。
彼は2011/12年シーズンにすでに『セヴィリヤの理髪師』でメト・デビューしているのですが、今シーズンの活躍で一気に認知度が高まったような感があります。
シーズンの終盤は、ベル・カント・ラッシュと言ってもよい感があって、『夢遊病の女』、『清教徒』、そして『チェネレントラ』が前後して、もしくはほぼ同時期に上演されていました。
カマレナはもともと『夢遊病の女』のみにキャスティングされていたんですが、ダムラウと組んだその『夢遊病の女』での歌唱が非常に評価が高く、
それが買われたのか、もしくは元々彼がアンダースタディだったのか、体調不良のため『チェネレントラ』の最初の3回の公演を降板したファン・ディエゴ・フローレスの代役は彼がつとめることになりました。
ところが、その『チェネレントラ』での代役歌唱の評価がものすごく高くて、新しいスターを手ぐすねひいて待っているオペラファンの中には”もうフローレスの時代は終わった。これからはカマレナだ!”とか、
カマレナをパヴァロッティの再来!とまで呼ぶ声まで出て来ている始末です。
あまりに初日の評価が高かったので、ちょうど『チェネレントラ』のチケットを手配しようとしていた私は頭を抱えてしまいました。
なぜならば、現在色々な理由で多忙を極めているため、『チェネレントラ』の公演には一回しか行けそうにないからです。フローレス or カマレナ、どちらかを選ばなければならない、、。
とそこで、メトが、二幕のラミロの”そう、誓って彼女を見つけ出す Si, ritrovarla io giuro" をカマレナがドレス・リハーサルで歌っているところの抜粋映像をアップしてくれていることに気付きました。
いつも繰り返しますが、録音はあくまで録音でしかないので、これだけを頼りにして決めなければならないのは非常に心苦しいのですが、仕方ありません。
なるほど、、確かにベル・カントのレパートリーを歌うにしては強靭で、芯のある、がっちりした輪郭の声をしてるな、と思います。
しかも、高音にものすごく強いんですね、、、フローレスや2008/9年シーズンに同役を歌ったブラウンリーは普通にハイCで処理しているところを、そこにさらにDを重ねて、
その音も申し訳程度に、もしくは苦しげに、もしくは怪しげに、もしくは妙な音で鳴ってます、という感じでは全然なく、
それまでの音と全く遜色ない響きと土台の力強さのまま高い音にエクステンドして鳴り渡っています。
あ、それを言ったら今シーズンの『清教徒』はブラウンリーが歌っているんですが、彼は数年前にマチャイーゼと組んだ『連隊の娘』も安定感を欠いたあまりぱっとしない歌唱で、、
一時期の勢いがちょっとなくなってしまっているような感じを受けるのは残念です。
フローレスに続け!と期待も高かったんですが、そんなゆるいことをしている間に、このカマレナのような人が出てきてスポットライトを奪って行くわけで、
ベル・カントという限られたレパートリーの役を互いに競っていくわけですから、油断できません。
カマレナに話を戻すと、声のカラー、音色に関しては、私個人的にはパヴァロッティを彷彿とさせるものはあまり感じませんが、
安定感から来る力強い響き(実際に劇場で聴いた人の話ではすごく良く音が鳴るそうです)がパヴァロッティの歌唱を思わせるのかもしれません。
しかし、その一方でベル・カント好きの人間からするとちょっと気になる側面もあって、それは彼の歌は興奮度が優先する・させるあまり、
プレシジョン、正確性といったものが軽く犠牲になっているように感じられる部分があるのと、
高音以外の部分、たとえばフレージング全体の美しさとかメロディーのアークの取り方、言葉の音への乗せ方、とか、その辺りではまだまだフローレスの技術の高さには追いついていないかな、という風に思います。
”フローレスはピークを過ぎた、これからはカマレナ。”などという声があるなら余計、それだったら今のうちにフローレスのラミロを聴いとかにゃ、と思ってしまいます。
カマレナはこれからもどんどん聴く機会があるでしょう。その時までにそれらの部分がブラッシュアップされていることを期待することにします。
ということで、これはかなり頭を悩ます選択でしたが、フローレスの公演に決定~!

そこでまた神の思し召しか、フローレスが体調不良から復帰する最初の公演(通算ではシーズン4度目の公演)に、一席だけ、燦然とディレクター・ボックスの座席が残っているではありませんか!!
ディレクター・ボックスとは、グランド・ティアーの最も舞台下手(舞台に向かって座って、左手の側)に近い、ほとんどオケピを横から眺める感じのボックスです。
舞台の一部は見切れてしまいますが、歌手が舞台前方で歌っている限りはまるで手にとるようにその表情が見えるうえ、しかも指揮者やオケの様子もばっちり観察できるので、このボックスは大好きです。
ドン・マニフィコ一家は前回(2008/9年シーズン)と全く同じキャスティングで、ドン・マニフィコをアレッサンドロ・コルべりが、そして意地悪姉妹をレイチェル・ダーキンとパトリシア・リスリーが演じています。
当時の記事にも書いた通り、『チェネレントラ』がメトで初めて上演されたのは1997年のことなんですが(バルトリらが出演)、
2008/9年シーズン、それから今シーズンと、舞台監督を変えつつも、その1997年からの演出が今も引き続いて使用されています。
意地悪ファミリーのコンビは2008年からの記憶がまだきちんと残っているからか、演技・歌唱いずれのアンサンブルもすばらしく息の合ったそれで、
しかも、今回の舞台監督の手腕が良いのか、はたまた主演陣の歌唱のレベルの高さに感化されたのか、2008/9年の公演以上に生き生きとした、
それでいて必要以上のどたばたに陥らない、役の領分をわきまえた歌唱と演技で、主役陣をうまく盛り立てていたと思います。
コルべりはもう60歳を過ぎていますし、声のパワーは以前と比べて衰えている部分はありますが、
もともと声自体は軽めでパワーや音色で聴かせる人では全くなく、安心して観て・聴いていられる歌唱力とタイミングの良いコメディックな演技力(特に後者)に強みがある人だと思います。
特に、自分も舞踏会に連れて行って欲しい、と懇願するチェネレントラを、王子やダンディーニの目前で、虐待すれすれのやり方(ディドナートをステッキで羽交い絞め!)で脅し、いじめ、阻止する”だめ父”ぶりは、
本人が他の場面以上に生き生きと演じていて、実に楽しそうですらあります。

チェネレントラ役のジョイス・ディドナートは、以前からこのブログでも折りあるごとに触れてきた通り、素もすごくチャーミングでポジティブ・オーラに溢れたアーティストです。
彼女の声の少し独特な音色と歌唱技術の長所(特に早いパッセージでの上手さ)のコンビネーションから、個人的には一番ロッシーニのレパートリーが向いていると思っているのですが、
彼女の地のキャラクターとどことなく通じる雰囲気のあるチェネレントラはその中でも特に彼女に向いた作品なのでは?と推測していました。
というのも、彼女の"Non più mesta"はメト・オケのコンサート等で単独で聴いたことはありますが、彼女のチェネレントラを全幕で鑑賞するのは今回が初めてなのです。
彼女は元々あまり高音に強いメゾではなく、レパートリーの最高音域を軽くアタックしてすぐに降りてくるような時は綺麗な音を出すのですが、
フルブラストで長い音を鳴らす時になると少し音にすかすかしたブリージーな感触が混じることがあり、以前はそれでも気合で押してそれをあまり気にならないレベルに押しとどめていたんですが、
メトで『マリア・ストゥアルダ』を歌ったあたりからその傾向が以前よりさらに顕著になり、以前に増して高音が出にくくなっているような印象を持ちます。
大体同時期と思われる2012年のグラミー賞の場でも、"Non più mesta"を披露しましたが、その歌唱にも似た感想を持ちましたし、今日の歌唱もやはり、似た印象でした。
また、少しお疲れモード、もしくは声のコンディションがあまり良くなかったんでしょうか、全体的に声がドライで、
マリア・ストゥアルダの最高音域以外で鳴っていた、劇場にたゆたうような美しい響きがあまり今日は聴かれなかったのが残念です。
2008/9年にチェネレントラを歌ったエリーナ・ガランチャはその点、彼女と全く対照的なタイプの歌手と言ってもよく、彼女はメゾとしては楽々と高音を出しますし、
また低音域から高音域までの統制のとれた均一な響きはトップクラスの歌手の中でもさらに上位何パーセントというようなレベルのそれです。
また声そのものの美しさも印象的で、ディドナートが早いパッセージでちゃきちゃきとした魅力を発するとすれば、ガランチャの方はむしろ、ややゆっくり目のパッセージ、
ラストの部分で言うと、Non più mestaよりは、その前のNacqui all'affannoの部分の美しさで私などは、”おお!”と感嘆してしまったのでした。
ちなみに、その2008/9年の公演での彼女の歌唱はこちら。
また、作品通しで、歌唱技術全体を見て隙がないのももしかするとガランチャの方かもしれないな、と思います。
私は過去にガランチャの歌でしかこの作品を生鑑賞したことがないので、その記憶がかなり鮮明に残っていて、意識しなくとも、ついそれと比較してしまいます。
そうすると、ガランチャに比べると、ディドナートは、より”人間らしい”処理の仕方で歌っている箇所もあったりして(たとえば細かくはありますが、音の粒の揃い方とか、、ガランチャは半分ロボットみたいに正確なので、、)、
「あれ?」と思ったりもするのですが、それではディドナートのチェネレントラはガランチャのチェネレントラよりだめなのか、と言われると、その答えがNoでないところが実にオペラです。
高音の安定感、声そのものの圧倒的な美しさ、低音域から高音域にかけての音色のなめらかな統一性、これらの側面でほんの数ミリガランチャに譲っているディドナートですが、
ディドナートのチェネレントラには言葉では説明の難しい、これぞ役との相性、とでも言うしかないソウルとかハートとでも呼びたくなるようなものがあるため、
全幕を見終わった後でどちらが”ああ、チェネレントラを見たなあ。”という実感が強いかというと、ディドナートだったりするんです。
チェネレントラってよく考えてみると、その行動に結構自信家で図太いところもあったりして、下手すると同性に嫌われやすいタイプではないかと思うんですが、
そんな逞しさを感じさせつつも、それを嫌味でなく、女性から見てもチャーミングにディドナートは表現してくれます。
また、ガランチャは出身地(ラトヴィア)も関係があるのか、若干この役にはウェットで、じとーっと王子が彼女を探し出してくれるのを待っているような雰囲気が漂っているんですが、
ディドナートのチェネレントラはもっとドライでパワフル。
美しく変身した姿で腕輪の片割れをラミロに渡した後に、灰かぶり娘状態に戻ってももう一方の腕輪を身につけ、気高く、
ほとんど自信に溢れた様子でラミロの登場を信じているかのような佇まいは、より現代的で、若い世代のオーディエンスにも共感しやすい役作りなんじゃないかな、と思います。

ガランチャの女性らしい声質・歌唱スタイルに比べて、ディドナートの少し野太目な音色、それから早いパッセージでのばりばり感(ここはガランチャにはないディドナートの最高の強みだと思います)は、
そんな彼女のチェネレントラ像をよく補完していると思います。
2008/9年の公演も良かったんですが、それに増して今回の公演はチェネレントラ役だけに限らず、全体としてもより良くまとまったコヒーシブな舞台だな、と好印象を持ったんですが、
それにはディドナート以外のメインの役における配役の妙があったと思います。

まず、家庭教師アリドーロ。
この演出では、アリドーロって本当に人間の家庭教師なのか、それともこの世の物でない存在なのか(なぜか天使みたいな格好だし、、、)よくわからない感じがあるんですが、
前回の公演で同役を歌ったジョン・レリエは、ばりばりと低音の良く響く声と背が高くて男性っぽいたたずまいのせいか、人間・家庭教師の雰囲気もそれなりに保っているため、
天使みたいなコスチュームも、コスプレ好きな家庭教師が仕組んだ遊び、みたいな雰囲気もあり、それはそれで面白かったのですが、今回キャスティングされている、ルカ・ピサロ二。
彼は以前から、なんか面白い歌手だな、と思っているんですが、ますますその印象を強くしました。
まず、ピサロニは愛犬家で知られていて、飼っている二匹の犬の片方がダックスフントである、という、その点からしてすでに、私個人的にはかなりポイントが高いんですが、
(今回の公演のために、わん二匹もヨーロッパからNYに同行して、随分NYライフを満喫されたようです。FaceBookで確認できるこの親ばかぶりは、私に負けてません。)
それを抜きにしても、彼はアーティストとして、非常に面白い個性を持っているな、と思って注目してます。その彼の個性とは”良い意味で個性がないこと。”
普通メトに登場する位の歌手になってくると、それなりに本人のカラーが前面に出ている人が多く、人によってはそれこそ何の役を歌っても○○だな、と思わされることがあったりもするものですが、
ピサロニはこれまでメトでいくつかの舞台を拝見してますが(『フィガロの結婚』のフィガロ、、『ドン・ジョヴァンニ』のレポレッロ、『魔法の島』のキャリバン、そして、今回のアリドーロ)
毎回カメレオンのように雰囲気が変わるので本人がどんな人なのか、今もって皆目不明なくらいです。
それでいて、どの役も結構器用に説得力を持って歌うんです。キャリバンなんか、ものすごいモンスター姿で本来の顔すらわからないような状態だったのに、
あの激厚メークの下からきちんと表現の意図の伝わってくる演技と歌唱を披露していましたし、
かと思うと、グランデージの演出がプレミエした際は、ちょっとワイルドな男臭いレポレッロも上手く演じてました。
(下はメトのHDの『ドン・ジョヴァンニ』からのカタログの歌の歌唱です。)
声や歌唱には、嫌味な癖がなくて、素直でクリーン、といった言葉が真っ先に浮かんでくるのですが、何色にも染まっていないというか、
演技と同様、歌唱から受けるイメージも毎回役によって違う雰囲気の出てくる不思議な人です。
で、そのピサロニが今回演じたアリドーロは、『ドン・ジョヴァンニ』のレポレッロ役で見せたマッチョな雰囲気とまるで同じ歌手に思えないほどか細く、
ほとんどフェミニンな、それこそその場で消えてしまいそうな、この世のものでない的雰囲気を一人醸しだしてました。
レリエが天使のフリをした家庭教師だったとすると、ピサロニは家庭教師のフリした天使、そんな感じの違いです。

ダンディーニ役はドン・マニフィコ役と共に喜劇的な屋台骨を支える大事な役。
2008/9年の公演では、アルベルギーニが同役にキャスティングされていましたが、王子とそう年の変わらない雰囲気で歌い演じていてそれはそれでなかなかに良かったです。
今回の公演でこの役を歌ったのはピエトロ・スパニョーリ。今シーズンのこの『チェネレントラ』がメト・デビューになります。
アルベルギーニがちょっと突っ走り系おっちょこちょい、だけど根は優しくて憎めないダンディーニだったのに対し、
スパニョーリの方はかなり親父っぽく、突っ走っているというよりは何事につけあまりやる気がなく、ちょっととぼけてる感じの役作りなんですが、、
その親父っぽい風采のおかげで、ラミロと再度アイデンティティ交換を行って、本来の従者の姿に戻った後のドン・マニフィコとのやり取りになんともいえないリアリティが漂ったのが素敵でした。
万時やる気なさげなダンディーニに突然訪れた王子のフリとそれに伴う興奮という”超日常”という楽しみの終焉、
そして、再び従者としての際限ない退屈な繰り返しの”日常”&やる気ないモードに戻らなければならない、という寂寥感とアパシーがドン・マニフィコとの間に感じられて、
チェネレントラはものすごい幸運をつかんでしまいすが、99.9%の人間にとってはこの退屈な日常が普通。
私も間違いなくそういう一般ピープルの一人ですので、それがまたちょっとせつないというか、しかし、それでいて愛しいというか、、、意外なところが美しい場面になりました。
スパニョーリはメトのような大箱で聴いてもよく声の通る人だな、という印象です。
ただ、この役はそれほど奥行きのある役でも繊細な役でもカリスマが必要な役でもないので、
それらが必要とされる役を歌う時にどれ位の力を持っているのか、というのは、また再びメトに戻ってくれる時にじっくり聴いて確認したいと思っています。

そして最後になってしまいましたが、ラミロ王子役のフローレス。
もう第一声が出て来た時のこの色気!これがやはり特別な歌手を特別なものにする一番の要素なんだ、と本当に思います。
カマレナの声のような強さはないですが、さっと広げた上質の絹のような味わいと感触があります。
いくら歌唱技術が優れていようが、どんなに高い音が出ようが、この生まれもった声 ~別にスタンダードな意味での美声でなくてもいいですが、
何か一声でオーディエンスの心に訴えかけてくるようなそんな力を持った声~ これはやはり”色気”としかいいようがないんでしょうが、それがいかに大事かというのを思い知らされます。
告白してしまいますと、実は今日の公演で私が一番驚いたのは、ビジュアル的にフローレスが老けたことです。
いや、もともと若々しい人なので、老けたと言ったら言い過ぎなんですが、以前とは雰囲気が変わったな、と思いました。
私が彼をメトで最後に見たのは2011/12年シーズンの『オリー伯爵』だと思うんですが、あの頃くらいまでは、彼特有の”永遠の青年”的な佇まいを保っていたように思うのですが、
やはりお子さんが出来た(確かオリーのHDの日当日の朝方近くに赤ちゃんが生まれた、というような話だったはずです)ことが関係しているのか、
よく言えばパパらしく、悪くいえばちょっとおじさんっぽくなったな、と思います。
でも、私がれっきとしたおばさんだから言うのではないですが、これもまた素敵なことだと思います。
フローレスはトーク・イベントに参加した時に受けた印象からも、すごく感じがよくて決して傲慢な人ではないですが、
やはり、若い時というのは”自分ががんばらねば!”というのが前面にでてしまうものです。
ましてや、ロッシーニ作品をはじめとしたベル・カントの主役テノールに求められるアクロバティックな歌唱を毎回コンスタントに繰り出さなければいけないのはすごい重圧だし、
それが成功したら”どうだ!”という気持ちになって当然だと思います。
でも今回の彼はなんというのか、、自分のことより何より、周りのキャストへのまなざしがあたたかくて、それは本当に素敵だな、と思いました。
昨シーズンか昨々シーズンだったかに、オペラ・ギルドのトークのイベントで、自分の声が変化して来ているから、色々実験している、というような趣旨のことを言っていたような記憶があるのですが、
その時は正直、へー、そんなことをやっているのか、とちょっとびっくりした記憶があります。
当時は公演を聴く限り、私にはまだまだ以前通り、十分軽く、また高音もしっかり鳴っているように聴こえていたので。
彼の声が以前と同じでないな、というのをはっきり意識したのは今日の公演がはじめてです。
この10年以上、ベル・カント、特にロッシーニ作品の主役テノールとしてほとんど彼はアンタッチャブルな地位をキープして来ましたが、
その理由の一つは彼のゆるぎのない、何があっても失敗するなんてことは絶対にありえないと思えるほどセキュアな高音とその音色の魅力でした。
しかし、彼の声の変化が一番如実に出ているのが、まさにその高音での音の響き・テクスチャーです。
最初の公演三つをキャンセルしているので、コンディションの問題も多少はあるのかもしれませんが、
しかし、そこに至るまでの音域では以前と変わらず全く綺麗な音でインタクトですし、
それに彼は以前、『連隊の娘』の土曜のマチネのラジオ放送で、”風邪引いてます”と堂々宣言していました(たしかダムラウとの共演で、彼女と二人で風邪をひいていたと記憶してます)が、
その時の感じともまたどこか違っていますので、私自身は風邪ではなく、より長期的な変化によるものの可能性が高いと思っています。
一言で平たく言うと、高音に以前ほどの輝きがなくなった、と言えるのかもしれません。
で、そのあたりを指して、フローレスは終わった、みたいな失礼なことを言う人が出て来るんでしょう。
しかし、あなたが高音の音の響きしか聴かないハイC馬鹿でもない限り、そんな断定は無用、
彼の歌はまだまだキング・オブ・ベル・カントの名に恥じないすばらしい内容のものです。
”必要は発明の母”という言葉がある通り、高音が以前のような音で出しにくくなっている、ということが理由になってもいるのかもしれませんが、
彼のフレージング美へのこだわりと、そのエグゼキューションレベルの高さは感動ものですらあります。
高音とかトリッキーな音型、迅速さをもとめられるパッセージは、ともすると、それ自体が手段でなく目的になってしまいがちですが、
彼の今日のラミロ役の歌唱を聴くと、それらが目的には全くなっていなくて、常に役の表現、音楽、といった”全体”が優先されていることがよくわかります。
そのために、(高音はある程度年齢等によって避けがたい部分もありますが)あらゆる歌唱部分は磨きに磨かれ、どんなに難しいフレーズでもいとも簡単に歌いこなしてしまうので、
なんだか、すごく簡単なパートを歌っているような気がしてくるのがなんともおそろしいところです。
以前、アンジェラ・ミードの歌についても同じようなことを書いたのですが、このタイプの歌唱・歌手の損なところはこのマスタリー度の高さゆえに、
かえって、どれほど大変なことを成し遂げているか、あまりオペラやベル・カントになじみのないオーディエンスにはわかってもらいづらい部分がある点です。
大変だ、ということがもはやわからないまでに、歌唱を極める。
それをやってのけているアーティスト達は損得なんて全くもって考えていないのでしょうが、
この彼らのやっていることの素晴らしさ・すごさが通じない相手がいるのを見るにつけ、それが痛いほどわかる人間は臍をかむというものです。
どれ位高い音が出るか、とか、それをどれ位のばせるか、とかだけでなく、こういうところへのこだわり、あくなき探究心、歌いまわしや言葉の乗せ方のセンスとそれを可能にするための鍛錬、
それらこそ、これからフローレスに続く若いベル・カント歌いたちに見習って欲しい点です。

フローレスが出演する公演には最低一公演、時には複数公演、足を向けているにもかかわらず、私がいつも彼のアンコールを逃し続けて来たことはこのブログを継続して読んで下さっている方ならご存知の通り。
あまりに運が悪いので、もう私は死ぬまで生でフローレスのアンコールを聴くことはないのだわ、という悟りに至ってしまって、今日はすっかりそんなことも忘れてしまっていました。
自分の代役で歌ったカマレナの評判については当然フローレスの耳にも入っていたはずですが、
しかし、キング・オブ・ベル・カントにも意地ってものがありますから、ここは彼も負けてられません。
そんな意地が昇華して、”そう、誓って彼女を見つけ出す Si, ritrovarla io giuro"ではものすごい気合が伝わってきました。
彼がこんな気合で歌う時は、素晴らしい内容にならないわけがなく、歌唱後、ト書きにそった退場のため、扉の向こうに出て行くフローレスを追いかけ、
そして、彼をもう一度舞台にひっぱりださん、と、まきあがる大喝采と大歓声と拍手の嵐。すごい観客の熱狂ぶりです。
そうしたら、しばらくして再び扉があいてフローレスが挨拶のため、再登場。
観客のアンコールおねだりの歓声がすごいことになっていて、そこで、”あ、そうだ、ここでアンコールすることもあるんだった。”とようやく気付く私なのでした。おそっ。
まったくもってやみそうのない歓声の嵐に、どういう風にフローレスがコミュニケートしたのかいまだにわからないんですが
(あんなに至近距離に座っていても、特にフローレスから指揮者に何かサインが出たような感じはキャッチできなかったのですが)、
指揮のルイージがオケのメンバーに”楽譜、少し前に戻って。”という手サインを出しているのが見えるではありませんか!
うそ?うそ?まじで????アンコール??????(Madokakip、感涙 )
)
ああ、もう夢のようです。何年も夢見たアンコールがこんなにあっさりと起こっていいものなんでしょうか?!
しかも、今日はディレクター・ボックスゆえに、手の届きそうな距離のところでフローレスが歌っている、、あまりにもシュールで気を失いそうです。
彼の歌が素晴らしいのはもう当然のことなんですが、今回この『チェネレントラ』という演目で彼の出演する側の公演を選んで本当に良かった、、と思いました。
それは、彼のルックスです。フローレスって以前より少しおじさんっぽくなったといっても、やっぱり王子役がよく似合う。
ダンディーニと身分の取替えをしても、”こちらが王子です。”というのが歴然と伝わってくるし、
チェネレントラがずっと従者だと思っていた相手が実は王子だった!という、文字通りの”シンデレラ・ストーリー”的インパクトが、フローレスみたいな歌手が王子役だと、100倍にも200倍にも膨れ上がる感じです。
『シンデレラ』に初めてふれる女児の多くは、いつか自分にもこんなハンサムで身分の高い男性が現れるのだ!と、目をハートにするわけで、ハンサムx身分が高い、この二点が入っていることがポイントです。
2008/9年のブラウンリーのラミロ王子は歌は非常によくがんばっていると思いましたが、片方がおっこちている点で(すまない、ブラウンリー、、、)、
彼が王子だと判明しても、今ひとつ子供の時に感じた”いいなあ、シンデレラ~”という羨望の思いを感じない。
むしろ、これでいいのか、シンデレラ?とすら、思ってしまう(重ねて、すまない、ブラウンリー、、、)
申し訳ないが、カマレナでも、その点では似た感じになると思います。
でも、フローレス!
彼のラミロ役でこの作品を見ると、私の奥に眠っていた5歳当時のMadokakipが”うおー!!シンデレラ、うらやまし~!!”と叫びまくって、それはもう大変でした。
やっぱりシンデレラの物語はこうでなければ。
しかし、ふと、こうも思いました。
なんか、こんなこと思ってしまう私って、フランスのエロじじい化してる、、?
そこで、彼に”私がいつの日かあなたとそっくりなことを言い出すことになるとは、誰が想像したでしょう?”という言葉を書き添えて、
フローレスのルックスのおかげで、どれほどシンデレラ・ストーリーがリアルなものに感じられたか、正直に書いてメールしてみました。
そうするとすぐに彼から返事が。
”そうだよ、君もやっとわかってきたようだね。”
でも、言っときますが、フローレスは歌唱も超一級ですから!!
今日の指揮は先にも書いた通り、ルイージ。
ヴェルディとかワーグナーの作品での彼の指揮については、近年個人的には失望続きでしたが、
この『チェネレントラ』のような、猛烈なエモーションを感じさせる必要はないが、娯楽性とかつデリケートさや繊細さが必要な演目での彼の指揮はとっても良いと思います。
音楽が自然に流れていて、とても楽しめました。
しかし、ある方から、彼の『蝶々夫人』もすごく良かった、と聴いてかなりびっくりしてます。
バタフライほどエモーショナルな演目もないですからね、、、うーん、聴いておきたかったです。(聴きのがしました。)
Joyce DiDonato (Angelina, known as Cenerentola)
Juan Diego Flórez (Don Ramiro)
Pietro Spagnoli (Dandini)
Alessandro Corbelli (Don Magnifico)
Luca Pisaroni (Alidoro)
Rachelle Durkin (Clorinda)
Patricia Risley (Tisbe)
Conductor: Fabio Luisi
Production: Cesare Lievi
Set & Costume design: Maurizio Balò
Lighting design: Gigi Saccomandi
Choreography: Daniela Schiavone
Stage direction: Eric Einhorn
Grand Tier DB Front
OL
*** ロッシーニ ラ・チェネレントラ Rossini La Cenerentola ***
あまりにもびっくりしてしまって、驚いている間になんと一年以上が経ってしまいました。
Madokakipがへこんでいるのかな、と心配してくださったのでしょうか、励ましのお言葉、
それからさりげなく記事のupにつながるような心配りで書いてくださったと思われる内容のコメントもいくつかコメント欄に頂きました。
その方々には心からのお礼と、そして長らくお返事を差し上げなかった非礼をお詫び申し上げます。
どうぞ、ご心配なきよう、あのようなコメントをいただきましても、”ああ、これまで書いていたことの本質が全く伝わっていない相手もいるんだな。
時間と労力かけて一生懸命書いていた私が馬鹿だったな。なんか、必死こいて記事を書くのがめんどくさくなったな。”と思うことはあれ、へこむというような脆弱なメンタリティは持ち合わせておりません!
仕事も忙しくなって来たし、これでフェードアウトもありかな、まあ、こうして放置していればだんだん閲覧件数も減っていくだろう、と思っていたのですが、
先日久しぶりに記事の編集ページに行ってみて、あまり閲覧件数が減っていないのにびっくりしまして、
よもやgooの閲覧カウンターが壊れているんじゃ、、、との思いも頭をよぎりましたが、もしかして、もしかすると、書き込みをして下さった方々をはじめとして、
いつかこのブログが復活するのではないかと思って時々のぞき続けて下さっている方がいるのかもしれない、、、と思うと、なんとも申し訳ない気持ちになって参りました。
それに、このブログに終止符を打つのであれば、人のブログに土足で踏み込んで、偉そうな値踏みをしていく輩にタイミングを決められて自然消滅するのではなく、
自分の意志できちんと皆様にご挨拶をして幕を引きたい、とも思いました。
オペラへの愛は子供のしつけに対する考え方と似ていると思います。
ある人は、愛情があるなら厳しいことを言わずにのびのびと育てればよい、と思うし、ある人は愛があるからこそ、厳しいことのひとつやふたつ、、、とも思う。
けれども、人の家にずかずかと入り込んで、あなたのしつけのやり方は子供に厳し過ぎるから、ゆえに子供を愛していない、というようなことを決め付けて、だからもっと優しく接しなさい、と押し着せてみたりだとか、
逆にあなたは甘やかし過ぎだから、もっと厳しくしなさい、なんてことをずけずけ言ってのけるのは、分をわきまえない失礼な行動であるということを自覚して欲しいと思います。
それは、その家の人間が本当に子供を愛している場合、なおさらで、ほんと、余計なお世話とはこのことです。
人の愛情の表現の方法は色々で、どれが絶対に正しいなんてことはないはずです。
他の事ならともかく、私のオペラに対する愛情を疑問視したり、オペラが好きならこういう行動をとるべきだと強制するようなコメントはここでは二度と見たくないので、よろしくお願いいたします。
それから、愛する対象への厳しい言葉は、それがどれほどきつくあろうとも『悪口』とは性質を異にしますので、そこの見分けもつかない方には、このブログは全く向いてないと思います。
他にもたくさんオペラについてブログに書いていらっしゃる方はおられると思いますし、その中にはお花畑のようなブログもあるでしょうから、どうぞそちらを楽しまれてください。
また、私がチエカさんのブログの一部の読者のグリゴーロバッシングに対して苦言を申し上げたのは、彼らがグリゴーロに対してネガティブなことを書いているからでは全くありません。
彼らが実際に公演に足を運んでそう感じられたなら、”ふーん。そういう見方もあるのか。”と思うだけです。
私が軽蔑するのは、実際の公演に足を運ぶことすらしないで(はい、私はどのサインネームの方が実際にグリゴーロの公演を見たこともないということを知る程度にはチエカさんのサイトを頻繁にチェックしています。)、
YouTubeやらでちょい聞きした程度で歌手の歌唱を”二流”と決めつけ、
関係のない歌手の話をしている時にまで、ことある毎にその歌手を引き合いに出して貶める、そういうオペラファンなのであって、そういう人たちは本当に”暇な人”だと思います。
だけど、実際に聴きにいった公演の、ある歌唱に対する印象が全くよくなかった、それをきちんと理由だてて、その公演、もしくはその公演と何らかの関係のある・比較が有効な公演の記事の中で説明するのは全く必要かつ当然なことだと思うし、
それをやったからと言って”その言葉、お返しした”いと言われる筋合いなんてどこにもないと思います。
さっき書きました禁止事項以外のことであれば、どれだけ私のある歌手への評価に反対!という意見であっても、
なぜそう思うのか(単純に声が好きだから、顔が好きだから、、、何でも構いません)を合わせて教えて頂けるのであれば大歓迎! 喜んでお話させて頂きたく思います。
というわけで、この一年は全く公演の感想の覚書もとってませんし、今となっては2013-14年シーズンに見た公演全部の感想をupするのは不可能なんですが、記憶の新しいものや記憶に残った度が高いものを中心に、
またメトのシーズンオフ中にもいくつか観に行く予定の他カンパニーの公演(オペラ以外にも、バレエやみやびさんがコメント欄で教えてくださった歌舞伎のNY公演も含め)がありますので、それらと合わせてメトのシーズン・オフ中も記事をupしていこうかな、と思っております。
で、とりあえず、記憶の新しいところから、またbchamaさんの不運をカバーすべく、フローレスが復帰した、シーズン第四回目の『チェネレントラ』となる5/2の公演のレポートで復活したいと思います。

メトの2013/14年シーズン中、最も話題だった歌手の一人がハヴィエ・カマレナです。
彼は2011/12年シーズンにすでに『セヴィリヤの理髪師』でメト・デビューしているのですが、今シーズンの活躍で一気に認知度が高まったような感があります。
シーズンの終盤は、ベル・カント・ラッシュと言ってもよい感があって、『夢遊病の女』、『清教徒』、そして『チェネレントラ』が前後して、もしくはほぼ同時期に上演されていました。
カマレナはもともと『夢遊病の女』のみにキャスティングされていたんですが、ダムラウと組んだその『夢遊病の女』での歌唱が非常に評価が高く、
それが買われたのか、もしくは元々彼がアンダースタディだったのか、体調不良のため『チェネレントラ』の最初の3回の公演を降板したファン・ディエゴ・フローレスの代役は彼がつとめることになりました。
ところが、その『チェネレントラ』での代役歌唱の評価がものすごく高くて、新しいスターを手ぐすねひいて待っているオペラファンの中には”もうフローレスの時代は終わった。これからはカマレナだ!”とか、
カマレナをパヴァロッティの再来!とまで呼ぶ声まで出て来ている始末です。
あまりに初日の評価が高かったので、ちょうど『チェネレントラ』のチケットを手配しようとしていた私は頭を抱えてしまいました。
なぜならば、現在色々な理由で多忙を極めているため、『チェネレントラ』の公演には一回しか行けそうにないからです。フローレス or カマレナ、どちらかを選ばなければならない、、。
とそこで、メトが、二幕のラミロの”そう、誓って彼女を見つけ出す Si, ritrovarla io giuro" をカマレナがドレス・リハーサルで歌っているところの抜粋映像をアップしてくれていることに気付きました。
いつも繰り返しますが、録音はあくまで録音でしかないので、これだけを頼りにして決めなければならないのは非常に心苦しいのですが、仕方ありません。
なるほど、、確かにベル・カントのレパートリーを歌うにしては強靭で、芯のある、がっちりした輪郭の声をしてるな、と思います。
しかも、高音にものすごく強いんですね、、、フローレスや2008/9年シーズンに同役を歌ったブラウンリーは普通にハイCで処理しているところを、そこにさらにDを重ねて、
その音も申し訳程度に、もしくは苦しげに、もしくは怪しげに、もしくは妙な音で鳴ってます、という感じでは全然なく、
それまでの音と全く遜色ない響きと土台の力強さのまま高い音にエクステンドして鳴り渡っています。
あ、それを言ったら今シーズンの『清教徒』はブラウンリーが歌っているんですが、彼は数年前にマチャイーゼと組んだ『連隊の娘』も安定感を欠いたあまりぱっとしない歌唱で、、
一時期の勢いがちょっとなくなってしまっているような感じを受けるのは残念です。
フローレスに続け!と期待も高かったんですが、そんなゆるいことをしている間に、このカマレナのような人が出てきてスポットライトを奪って行くわけで、
ベル・カントという限られたレパートリーの役を互いに競っていくわけですから、油断できません。
カマレナに話を戻すと、声のカラー、音色に関しては、私個人的にはパヴァロッティを彷彿とさせるものはあまり感じませんが、
安定感から来る力強い響き(実際に劇場で聴いた人の話ではすごく良く音が鳴るそうです)がパヴァロッティの歌唱を思わせるのかもしれません。
しかし、その一方でベル・カント好きの人間からするとちょっと気になる側面もあって、それは彼の歌は興奮度が優先する・させるあまり、
プレシジョン、正確性といったものが軽く犠牲になっているように感じられる部分があるのと、
高音以外の部分、たとえばフレージング全体の美しさとかメロディーのアークの取り方、言葉の音への乗せ方、とか、その辺りではまだまだフローレスの技術の高さには追いついていないかな、という風に思います。
”フローレスはピークを過ぎた、これからはカマレナ。”などという声があるなら余計、それだったら今のうちにフローレスのラミロを聴いとかにゃ、と思ってしまいます。
カマレナはこれからもどんどん聴く機会があるでしょう。その時までにそれらの部分がブラッシュアップされていることを期待することにします。
ということで、これはかなり頭を悩ます選択でしたが、フローレスの公演に決定~!

そこでまた神の思し召しか、フローレスが体調不良から復帰する最初の公演(通算ではシーズン4度目の公演)に、一席だけ、燦然とディレクター・ボックスの座席が残っているではありませんか!!
ディレクター・ボックスとは、グランド・ティアーの最も舞台下手(舞台に向かって座って、左手の側)に近い、ほとんどオケピを横から眺める感じのボックスです。
舞台の一部は見切れてしまいますが、歌手が舞台前方で歌っている限りはまるで手にとるようにその表情が見えるうえ、しかも指揮者やオケの様子もばっちり観察できるので、このボックスは大好きです。
ドン・マニフィコ一家は前回(2008/9年シーズン)と全く同じキャスティングで、ドン・マニフィコをアレッサンドロ・コルべりが、そして意地悪姉妹をレイチェル・ダーキンとパトリシア・リスリーが演じています。
当時の記事にも書いた通り、『チェネレントラ』がメトで初めて上演されたのは1997年のことなんですが(バルトリらが出演)、
2008/9年シーズン、それから今シーズンと、舞台監督を変えつつも、その1997年からの演出が今も引き続いて使用されています。
意地悪ファミリーのコンビは2008年からの記憶がまだきちんと残っているからか、演技・歌唱いずれのアンサンブルもすばらしく息の合ったそれで、
しかも、今回の舞台監督の手腕が良いのか、はたまた主演陣の歌唱のレベルの高さに感化されたのか、2008/9年の公演以上に生き生きとした、
それでいて必要以上のどたばたに陥らない、役の領分をわきまえた歌唱と演技で、主役陣をうまく盛り立てていたと思います。
コルべりはもう60歳を過ぎていますし、声のパワーは以前と比べて衰えている部分はありますが、
もともと声自体は軽めでパワーや音色で聴かせる人では全くなく、安心して観て・聴いていられる歌唱力とタイミングの良いコメディックな演技力(特に後者)に強みがある人だと思います。
特に、自分も舞踏会に連れて行って欲しい、と懇願するチェネレントラを、王子やダンディーニの目前で、虐待すれすれのやり方(ディドナートをステッキで羽交い絞め!)で脅し、いじめ、阻止する”だめ父”ぶりは、
本人が他の場面以上に生き生きと演じていて、実に楽しそうですらあります。

チェネレントラ役のジョイス・ディドナートは、以前からこのブログでも折りあるごとに触れてきた通り、素もすごくチャーミングでポジティブ・オーラに溢れたアーティストです。
彼女の声の少し独特な音色と歌唱技術の長所(特に早いパッセージでの上手さ)のコンビネーションから、個人的には一番ロッシーニのレパートリーが向いていると思っているのですが、
彼女の地のキャラクターとどことなく通じる雰囲気のあるチェネレントラはその中でも特に彼女に向いた作品なのでは?と推測していました。
というのも、彼女の"Non più mesta"はメト・オケのコンサート等で単独で聴いたことはありますが、彼女のチェネレントラを全幕で鑑賞するのは今回が初めてなのです。
彼女は元々あまり高音に強いメゾではなく、レパートリーの最高音域を軽くアタックしてすぐに降りてくるような時は綺麗な音を出すのですが、
フルブラストで長い音を鳴らす時になると少し音にすかすかしたブリージーな感触が混じることがあり、以前はそれでも気合で押してそれをあまり気にならないレベルに押しとどめていたんですが、
メトで『マリア・ストゥアルダ』を歌ったあたりからその傾向が以前よりさらに顕著になり、以前に増して高音が出にくくなっているような印象を持ちます。
大体同時期と思われる2012年のグラミー賞の場でも、"Non più mesta"を披露しましたが、その歌唱にも似た感想を持ちましたし、今日の歌唱もやはり、似た印象でした。
また、少しお疲れモード、もしくは声のコンディションがあまり良くなかったんでしょうか、全体的に声がドライで、
マリア・ストゥアルダの最高音域以外で鳴っていた、劇場にたゆたうような美しい響きがあまり今日は聴かれなかったのが残念です。
2008/9年にチェネレントラを歌ったエリーナ・ガランチャはその点、彼女と全く対照的なタイプの歌手と言ってもよく、彼女はメゾとしては楽々と高音を出しますし、
また低音域から高音域までの統制のとれた均一な響きはトップクラスの歌手の中でもさらに上位何パーセントというようなレベルのそれです。
また声そのものの美しさも印象的で、ディドナートが早いパッセージでちゃきちゃきとした魅力を発するとすれば、ガランチャの方はむしろ、ややゆっくり目のパッセージ、
ラストの部分で言うと、Non più mestaよりは、その前のNacqui all'affannoの部分の美しさで私などは、”おお!”と感嘆してしまったのでした。
ちなみに、その2008/9年の公演での彼女の歌唱はこちら。
また、作品通しで、歌唱技術全体を見て隙がないのももしかするとガランチャの方かもしれないな、と思います。
私は過去にガランチャの歌でしかこの作品を生鑑賞したことがないので、その記憶がかなり鮮明に残っていて、意識しなくとも、ついそれと比較してしまいます。
そうすると、ガランチャに比べると、ディドナートは、より”人間らしい”処理の仕方で歌っている箇所もあったりして(たとえば細かくはありますが、音の粒の揃い方とか、、ガランチャは半分ロボットみたいに正確なので、、)、
「あれ?」と思ったりもするのですが、それではディドナートのチェネレントラはガランチャのチェネレントラよりだめなのか、と言われると、その答えがNoでないところが実にオペラです。
高音の安定感、声そのものの圧倒的な美しさ、低音域から高音域にかけての音色のなめらかな統一性、これらの側面でほんの数ミリガランチャに譲っているディドナートですが、
ディドナートのチェネレントラには言葉では説明の難しい、これぞ役との相性、とでも言うしかないソウルとかハートとでも呼びたくなるようなものがあるため、
全幕を見終わった後でどちらが”ああ、チェネレントラを見たなあ。”という実感が強いかというと、ディドナートだったりするんです。
チェネレントラってよく考えてみると、その行動に結構自信家で図太いところもあったりして、下手すると同性に嫌われやすいタイプではないかと思うんですが、
そんな逞しさを感じさせつつも、それを嫌味でなく、女性から見てもチャーミングにディドナートは表現してくれます。
また、ガランチャは出身地(ラトヴィア)も関係があるのか、若干この役にはウェットで、じとーっと王子が彼女を探し出してくれるのを待っているような雰囲気が漂っているんですが、
ディドナートのチェネレントラはもっとドライでパワフル。
美しく変身した姿で腕輪の片割れをラミロに渡した後に、灰かぶり娘状態に戻ってももう一方の腕輪を身につけ、気高く、
ほとんど自信に溢れた様子でラミロの登場を信じているかのような佇まいは、より現代的で、若い世代のオーディエンスにも共感しやすい役作りなんじゃないかな、と思います。

ガランチャの女性らしい声質・歌唱スタイルに比べて、ディドナートの少し野太目な音色、それから早いパッセージでのばりばり感(ここはガランチャにはないディドナートの最高の強みだと思います)は、
そんな彼女のチェネレントラ像をよく補完していると思います。
2008/9年の公演も良かったんですが、それに増して今回の公演はチェネレントラ役だけに限らず、全体としてもより良くまとまったコヒーシブな舞台だな、と好印象を持ったんですが、
それにはディドナート以外のメインの役における配役の妙があったと思います。

まず、家庭教師アリドーロ。
この演出では、アリドーロって本当に人間の家庭教師なのか、それともこの世の物でない存在なのか(なぜか天使みたいな格好だし、、、)よくわからない感じがあるんですが、
前回の公演で同役を歌ったジョン・レリエは、ばりばりと低音の良く響く声と背が高くて男性っぽいたたずまいのせいか、人間・家庭教師の雰囲気もそれなりに保っているため、
天使みたいなコスチュームも、コスプレ好きな家庭教師が仕組んだ遊び、みたいな雰囲気もあり、それはそれで面白かったのですが、今回キャスティングされている、ルカ・ピサロ二。
彼は以前から、なんか面白い歌手だな、と思っているんですが、ますますその印象を強くしました。
まず、ピサロニは愛犬家で知られていて、飼っている二匹の犬の片方がダックスフントである、という、その点からしてすでに、私個人的にはかなりポイントが高いんですが、
(今回の公演のために、わん二匹もヨーロッパからNYに同行して、随分NYライフを満喫されたようです。FaceBookで確認できるこの親ばかぶりは、私に負けてません。)
それを抜きにしても、彼はアーティストとして、非常に面白い個性を持っているな、と思って注目してます。その彼の個性とは”良い意味で個性がないこと。”
普通メトに登場する位の歌手になってくると、それなりに本人のカラーが前面に出ている人が多く、人によってはそれこそ何の役を歌っても○○だな、と思わされることがあったりもするものですが、
ピサロニはこれまでメトでいくつかの舞台を拝見してますが(『フィガロの結婚』のフィガロ、、『ドン・ジョヴァンニ』のレポレッロ、『魔法の島』のキャリバン、そして、今回のアリドーロ)
毎回カメレオンのように雰囲気が変わるので本人がどんな人なのか、今もって皆目不明なくらいです。
それでいて、どの役も結構器用に説得力を持って歌うんです。キャリバンなんか、ものすごいモンスター姿で本来の顔すらわからないような状態だったのに、
あの激厚メークの下からきちんと表現の意図の伝わってくる演技と歌唱を披露していましたし、
かと思うと、グランデージの演出がプレミエした際は、ちょっとワイルドな男臭いレポレッロも上手く演じてました。
(下はメトのHDの『ドン・ジョヴァンニ』からのカタログの歌の歌唱です。)
声や歌唱には、嫌味な癖がなくて、素直でクリーン、といった言葉が真っ先に浮かんでくるのですが、何色にも染まっていないというか、
演技と同様、歌唱から受けるイメージも毎回役によって違う雰囲気の出てくる不思議な人です。
で、そのピサロニが今回演じたアリドーロは、『ドン・ジョヴァンニ』のレポレッロ役で見せたマッチョな雰囲気とまるで同じ歌手に思えないほどか細く、
ほとんどフェミニンな、それこそその場で消えてしまいそうな、この世のものでない的雰囲気を一人醸しだしてました。
レリエが天使のフリをした家庭教師だったとすると、ピサロニは家庭教師のフリした天使、そんな感じの違いです。

ダンディーニ役はドン・マニフィコ役と共に喜劇的な屋台骨を支える大事な役。
2008/9年の公演では、アルベルギーニが同役にキャスティングされていましたが、王子とそう年の変わらない雰囲気で歌い演じていてそれはそれでなかなかに良かったです。
今回の公演でこの役を歌ったのはピエトロ・スパニョーリ。今シーズンのこの『チェネレントラ』がメト・デビューになります。
アルベルギーニがちょっと突っ走り系おっちょこちょい、だけど根は優しくて憎めないダンディーニだったのに対し、
スパニョーリの方はかなり親父っぽく、突っ走っているというよりは何事につけあまりやる気がなく、ちょっととぼけてる感じの役作りなんですが、、
その親父っぽい風采のおかげで、ラミロと再度アイデンティティ交換を行って、本来の従者の姿に戻った後のドン・マニフィコとのやり取りになんともいえないリアリティが漂ったのが素敵でした。
万時やる気なさげなダンディーニに突然訪れた王子のフリとそれに伴う興奮という”超日常”という楽しみの終焉、
そして、再び従者としての際限ない退屈な繰り返しの”日常”&やる気ないモードに戻らなければならない、という寂寥感とアパシーがドン・マニフィコとの間に感じられて、
チェネレントラはものすごい幸運をつかんでしまいすが、99.9%の人間にとってはこの退屈な日常が普通。
私も間違いなくそういう一般ピープルの一人ですので、それがまたちょっとせつないというか、しかし、それでいて愛しいというか、、、意外なところが美しい場面になりました。
スパニョーリはメトのような大箱で聴いてもよく声の通る人だな、という印象です。
ただ、この役はそれほど奥行きのある役でも繊細な役でもカリスマが必要な役でもないので、
それらが必要とされる役を歌う時にどれ位の力を持っているのか、というのは、また再びメトに戻ってくれる時にじっくり聴いて確認したいと思っています。

そして最後になってしまいましたが、ラミロ王子役のフローレス。
もう第一声が出て来た時のこの色気!これがやはり特別な歌手を特別なものにする一番の要素なんだ、と本当に思います。
カマレナの声のような強さはないですが、さっと広げた上質の絹のような味わいと感触があります。
いくら歌唱技術が優れていようが、どんなに高い音が出ようが、この生まれもった声 ~別にスタンダードな意味での美声でなくてもいいですが、
何か一声でオーディエンスの心に訴えかけてくるようなそんな力を持った声~ これはやはり”色気”としかいいようがないんでしょうが、それがいかに大事かというのを思い知らされます。
告白してしまいますと、実は今日の公演で私が一番驚いたのは、ビジュアル的にフローレスが老けたことです。
いや、もともと若々しい人なので、老けたと言ったら言い過ぎなんですが、以前とは雰囲気が変わったな、と思いました。
私が彼をメトで最後に見たのは2011/12年シーズンの『オリー伯爵』だと思うんですが、あの頃くらいまでは、彼特有の”永遠の青年”的な佇まいを保っていたように思うのですが、
やはりお子さんが出来た(確かオリーのHDの日当日の朝方近くに赤ちゃんが生まれた、というような話だったはずです)ことが関係しているのか、
よく言えばパパらしく、悪くいえばちょっとおじさんっぽくなったな、と思います。
でも、私がれっきとしたおばさんだから言うのではないですが、これもまた素敵なことだと思います。
フローレスはトーク・イベントに参加した時に受けた印象からも、すごく感じがよくて決して傲慢な人ではないですが、
やはり、若い時というのは”自分ががんばらねば!”というのが前面にでてしまうものです。
ましてや、ロッシーニ作品をはじめとしたベル・カントの主役テノールに求められるアクロバティックな歌唱を毎回コンスタントに繰り出さなければいけないのはすごい重圧だし、
それが成功したら”どうだ!”という気持ちになって当然だと思います。
でも今回の彼はなんというのか、、自分のことより何より、周りのキャストへのまなざしがあたたかくて、それは本当に素敵だな、と思いました。
昨シーズンか昨々シーズンだったかに、オペラ・ギルドのトークのイベントで、自分の声が変化して来ているから、色々実験している、というような趣旨のことを言っていたような記憶があるのですが、
その時は正直、へー、そんなことをやっているのか、とちょっとびっくりした記憶があります。
当時は公演を聴く限り、私にはまだまだ以前通り、十分軽く、また高音もしっかり鳴っているように聴こえていたので。
彼の声が以前と同じでないな、というのをはっきり意識したのは今日の公演がはじめてです。
この10年以上、ベル・カント、特にロッシーニ作品の主役テノールとしてほとんど彼はアンタッチャブルな地位をキープして来ましたが、
その理由の一つは彼のゆるぎのない、何があっても失敗するなんてことは絶対にありえないと思えるほどセキュアな高音とその音色の魅力でした。
しかし、彼の声の変化が一番如実に出ているのが、まさにその高音での音の響き・テクスチャーです。
最初の公演三つをキャンセルしているので、コンディションの問題も多少はあるのかもしれませんが、
しかし、そこに至るまでの音域では以前と変わらず全く綺麗な音でインタクトですし、
それに彼は以前、『連隊の娘』の土曜のマチネのラジオ放送で、”風邪引いてます”と堂々宣言していました(たしかダムラウとの共演で、彼女と二人で風邪をひいていたと記憶してます)が、
その時の感じともまたどこか違っていますので、私自身は風邪ではなく、より長期的な変化によるものの可能性が高いと思っています。
一言で平たく言うと、高音に以前ほどの輝きがなくなった、と言えるのかもしれません。
で、そのあたりを指して、フローレスは終わった、みたいな失礼なことを言う人が出て来るんでしょう。
しかし、あなたが高音の音の響きしか聴かないハイC馬鹿でもない限り、そんな断定は無用、
彼の歌はまだまだキング・オブ・ベル・カントの名に恥じないすばらしい内容のものです。
”必要は発明の母”という言葉がある通り、高音が以前のような音で出しにくくなっている、ということが理由になってもいるのかもしれませんが、
彼のフレージング美へのこだわりと、そのエグゼキューションレベルの高さは感動ものですらあります。
高音とかトリッキーな音型、迅速さをもとめられるパッセージは、ともすると、それ自体が手段でなく目的になってしまいがちですが、
彼の今日のラミロ役の歌唱を聴くと、それらが目的には全くなっていなくて、常に役の表現、音楽、といった”全体”が優先されていることがよくわかります。
そのために、(高音はある程度年齢等によって避けがたい部分もありますが)あらゆる歌唱部分は磨きに磨かれ、どんなに難しいフレーズでもいとも簡単に歌いこなしてしまうので、
なんだか、すごく簡単なパートを歌っているような気がしてくるのがなんともおそろしいところです。
以前、アンジェラ・ミードの歌についても同じようなことを書いたのですが、このタイプの歌唱・歌手の損なところはこのマスタリー度の高さゆえに、
かえって、どれほど大変なことを成し遂げているか、あまりオペラやベル・カントになじみのないオーディエンスにはわかってもらいづらい部分がある点です。
大変だ、ということがもはやわからないまでに、歌唱を極める。
それをやってのけているアーティスト達は損得なんて全くもって考えていないのでしょうが、
この彼らのやっていることの素晴らしさ・すごさが通じない相手がいるのを見るにつけ、それが痛いほどわかる人間は臍をかむというものです。
どれ位高い音が出るか、とか、それをどれ位のばせるか、とかだけでなく、こういうところへのこだわり、あくなき探究心、歌いまわしや言葉の乗せ方のセンスとそれを可能にするための鍛錬、
それらこそ、これからフローレスに続く若いベル・カント歌いたちに見習って欲しい点です。

フローレスが出演する公演には最低一公演、時には複数公演、足を向けているにもかかわらず、私がいつも彼のアンコールを逃し続けて来たことはこのブログを継続して読んで下さっている方ならご存知の通り。
あまりに運が悪いので、もう私は死ぬまで生でフローレスのアンコールを聴くことはないのだわ、という悟りに至ってしまって、今日はすっかりそんなことも忘れてしまっていました。
自分の代役で歌ったカマレナの評判については当然フローレスの耳にも入っていたはずですが、
しかし、キング・オブ・ベル・カントにも意地ってものがありますから、ここは彼も負けてられません。
そんな意地が昇華して、”そう、誓って彼女を見つけ出す Si, ritrovarla io giuro"ではものすごい気合が伝わってきました。
彼がこんな気合で歌う時は、素晴らしい内容にならないわけがなく、歌唱後、ト書きにそった退場のため、扉の向こうに出て行くフローレスを追いかけ、
そして、彼をもう一度舞台にひっぱりださん、と、まきあがる大喝采と大歓声と拍手の嵐。すごい観客の熱狂ぶりです。
そうしたら、しばらくして再び扉があいてフローレスが挨拶のため、再登場。
観客のアンコールおねだりの歓声がすごいことになっていて、そこで、”あ、そうだ、ここでアンコールすることもあるんだった。”とようやく気付く私なのでした。おそっ。
まったくもってやみそうのない歓声の嵐に、どういう風にフローレスがコミュニケートしたのかいまだにわからないんですが
(あんなに至近距離に座っていても、特にフローレスから指揮者に何かサインが出たような感じはキャッチできなかったのですが)、
指揮のルイージがオケのメンバーに”楽譜、少し前に戻って。”という手サインを出しているのが見えるではありませんか!
うそ?うそ?まじで????アンコール??????(Madokakip、感涙
 )
)ああ、もう夢のようです。何年も夢見たアンコールがこんなにあっさりと起こっていいものなんでしょうか?!
しかも、今日はディレクター・ボックスゆえに、手の届きそうな距離のところでフローレスが歌っている、、あまりにもシュールで気を失いそうです。
彼の歌が素晴らしいのはもう当然のことなんですが、今回この『チェネレントラ』という演目で彼の出演する側の公演を選んで本当に良かった、、と思いました。
それは、彼のルックスです。フローレスって以前より少しおじさんっぽくなったといっても、やっぱり王子役がよく似合う。
ダンディーニと身分の取替えをしても、”こちらが王子です。”というのが歴然と伝わってくるし、
チェネレントラがずっと従者だと思っていた相手が実は王子だった!という、文字通りの”シンデレラ・ストーリー”的インパクトが、フローレスみたいな歌手が王子役だと、100倍にも200倍にも膨れ上がる感じです。
『シンデレラ』に初めてふれる女児の多くは、いつか自分にもこんなハンサムで身分の高い男性が現れるのだ!と、目をハートにするわけで、ハンサムx身分が高い、この二点が入っていることがポイントです。
2008/9年のブラウンリーのラミロ王子は歌は非常によくがんばっていると思いましたが、片方がおっこちている点で(すまない、ブラウンリー、、、)、
彼が王子だと判明しても、今ひとつ子供の時に感じた”いいなあ、シンデレラ~”という羨望の思いを感じない。
むしろ、これでいいのか、シンデレラ?とすら、思ってしまう(重ねて、すまない、ブラウンリー、、、)
申し訳ないが、カマレナでも、その点では似た感じになると思います。
でも、フローレス!
彼のラミロ役でこの作品を見ると、私の奥に眠っていた5歳当時のMadokakipが”うおー!!シンデレラ、うらやまし~!!”と叫びまくって、それはもう大変でした。
やっぱりシンデレラの物語はこうでなければ。
しかし、ふと、こうも思いました。
なんか、こんなこと思ってしまう私って、フランスのエロじじい化してる、、?
そこで、彼に”私がいつの日かあなたとそっくりなことを言い出すことになるとは、誰が想像したでしょう?”という言葉を書き添えて、
フローレスのルックスのおかげで、どれほどシンデレラ・ストーリーがリアルなものに感じられたか、正直に書いてメールしてみました。
そうするとすぐに彼から返事が。
”そうだよ、君もやっとわかってきたようだね。”
でも、言っときますが、フローレスは歌唱も超一級ですから!!
今日の指揮は先にも書いた通り、ルイージ。
ヴェルディとかワーグナーの作品での彼の指揮については、近年個人的には失望続きでしたが、
この『チェネレントラ』のような、猛烈なエモーションを感じさせる必要はないが、娯楽性とかつデリケートさや繊細さが必要な演目での彼の指揮はとっても良いと思います。
音楽が自然に流れていて、とても楽しめました。
しかし、ある方から、彼の『蝶々夫人』もすごく良かった、と聴いてかなりびっくりしてます。
バタフライほどエモーショナルな演目もないですからね、、、うーん、聴いておきたかったです。(聴きのがしました。)
Joyce DiDonato (Angelina, known as Cenerentola)
Juan Diego Flórez (Don Ramiro)
Pietro Spagnoli (Dandini)
Alessandro Corbelli (Don Magnifico)
Luca Pisaroni (Alidoro)
Rachelle Durkin (Clorinda)
Patricia Risley (Tisbe)
Conductor: Fabio Luisi
Production: Cesare Lievi
Set & Costume design: Maurizio Balò
Lighting design: Gigi Saccomandi
Choreography: Daniela Schiavone
Stage direction: Eric Einhorn
Grand Tier DB Front
OL
*** ロッシーニ ラ・チェネレントラ Rossini La Cenerentola ***













 )
)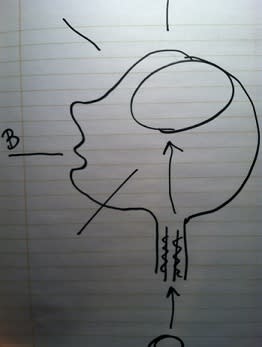




















 とし、いつも通り、直訳ではなく大意を再構成します。
とし、いつも通り、直訳ではなく大意を再構成します。










 ”
”








 で表示します。
で表示します。

 )の後に
)の後に








