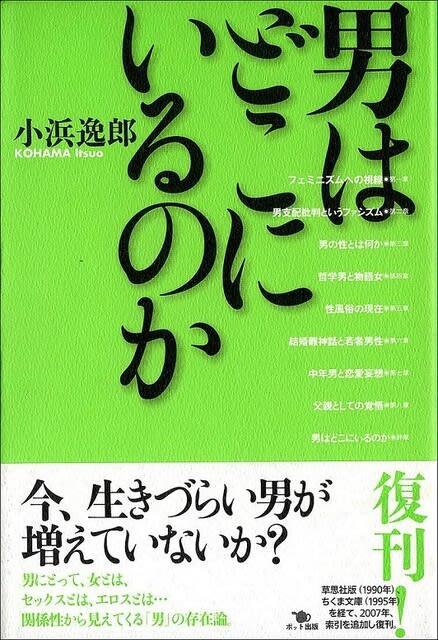メインテキスト:小浜逸郎『倫理の起源』(ポット出版プラス令和元年)
サブテキスト:和辻哲郎『倫理学』(初版は岩波書店全三巻昭和12~24年。岩波文庫全四巻平成19年)
前回は、『倫理の起源』の結論部分に即応して愚考を述べました。これはやや性急過ぎて、小浜の論の魅力的なところを取りこぼしてしまったようです。今回と次回、改めて、各種共同体の相関・相克関係や、公私の別について、小浜の言説をきちんとお浚いして、自分なりに感じる問題点を提出してみようと思います。
Ⅳ 和辻倫理学の継承と批判 往還の相と信頼
第一のテーゼと言うべきもの。重要なのは常に共同態なのだ。共同態があるからこそ、善がある。また、ある共同態がまずます平和に、幸福に営まれているなら、そこに善は実現されている。
では、悪とは何か。その共同態が乱れ、さらには失われること、ということになるだろう。
共同態のための場所である共同体がほぼ完全に消失する場合、BC1世紀ローマ帝国に滅ぼされたカルタゴとか、16世紀スペインのコンケスタドールに征服されたインカ帝国などの例は、今後も起こらないとは言えないが、倫理は共同体内部の人間の在り方を考えるものだ。
人は共同態の中で生まれ育って初めて人となる、共同態以前にいかなる個人もない、というのは、いわば発生論。元はそうでも、人が太郎とか花子とか固有名を持ち、一個の人格として扱われ、他者とは違う自分を意識したら、それだけで既存の共同性からは微妙に逸れている。
最も重要なのは、この逸れた個人がもう一度共同態に復帰すること。というよりは、共同性の核(それが何かは少し曖昧だが)を保存したまま、新たに創り上げていく、と言ったほうがいいだろう。
ある家庭の息子や娘が成長して結婚し、今度は自分が父母になって、子どもを産み育てる。今でも三世帯同居など、大家族はあるけれど、それでもそれは、元の「家」とは別のものになっている。子どもが結婚して嫁さんなり婿さんなりが入ってくるだけでも元とは違う。そこに新たな子どもが誕生すればまた違ってくる。
それでも、子育てなどの基本的なモデルは代々ずっと受け継がれた部分が大きく、それこそ共同態なのだが、親子が別居した場合でも、そのような無形の部分の継承はなされている。
小浜が、というより彼が最も影響を受けたと認める和辻哲郎の倫理学は、このような過程を共同態からの「往還」と呼ぶ。
個人が、反抗期とか何かで、意識的にもせよ無意識的にもせよ、共同態から背き離れるのが「往」、それからまた共同態に復帰するのが「還」、これが人間の、生活の歴史を形成する。
それで、「往」が悪の過程で、「還」が善の過程なのだが、いつかまた還る運動の過程にあるなら、「往」も全き「悪」とは呼べない。行ったっきりで戻る道が見つからない、あるいは完全に否定するとしたら、それこそが「悪」になる。
これでもう贅言は要さないかも知れないが、和辻―小浜が最重要と考えたのは、現にある家庭とか国家とかを保ち守ることよりむしろ、個々人が他者と共有し共生できるだけの、精神的なものを含めた場を創ることで、「他人への思いやり」と言えば、ほぼ尽きている。
小浜が悪の代表と考えるのは、個人の自由を重んじるあまり、「自分が正しいと信ずるなら、人を殺してもいい」なんて思うこと。ドストエフスキー「罪と罰」の主人公ラスコーリニコフはこの状態に陥ってしまった。
文学からまた別例を探すなら、ロビンソン・クルーソーは、事故で共同体からは離れてしまったが、それまで同胞とともに生きてきた英国社会の共同性から身につけたマナー(考え方と行動のパターン)は保っているので、共同性を失ったわけではない。それは、食人の習慣がある南米の原住民を野蛮人とみなすprejudice(偏見、だけど、元義は、「前もってする判断」)を含めての話ではあるが。
別様に表現すると、人間は関係性によって形成される、関係的な存在である。しかし、関係的存在であることを認識するところに自己が現れる。そして、それゆえにまた、人としての正道と言えば、関係性を自ら背負うところにある。つまり、関係性こそが倫理となるのである。【キルケゴールの「自己とは関係がそれ自身に関係する関係である」はそういうことではないかと私は思っている。】
ここまでなら特に異論はない。しかし実は倫理上の実際の問題は、この次からなのである。
小浜逸郎は和辻哲郎の倫理学を高く評価し、自分はその後継者を目指す者であることも認めている一方で、その弱点も厳しく指摘している。小浜の倫理学は、この弱点の克服を目的としている、と言っても過言ではない。
以下、小浜の和辻批判を私なりに言葉をやや変えて紹介すると。
(1)和辻は、共同体の中心核となる感情は信頼だと言う。それはそうで、成員同士に信頼感がなかったらいかなる共同体も成り立たないのは自明。ただ、それだけで共同体が保たれるかと言えば、これまた明らかに違う。
和辻がそう言っているわけではない。が、共同性こそ人倫の基礎という割には、共同性につきまとう諸問題にはあまり言及していない。
小浜の言い方だと、和辻は「ザイン」(現にあるもの・現実)と「ゾレン」(あるべき存在・当為)をちゃんと区別していないようだ。別言すれば「倫理学は、生の暗黒面という現実を直視しつつ、しかも最終的には「ゾレン」を追究する学であるという姿勢を一貫するのでなくてはならない」(pp.308~309)とすると、和辻にはその直視が足りないと言わざるを得ない。
例えば和辻『倫理学』第三章「人倫的組織」中の第4節「地縁共同体」における、村落の共同労働や祝祭における絆の深さについての記述など、現実にはまず存在しない、いいことずくめである。それから、第5節「経済的組織」では、そこでの人倫精神の要は「奉仕」というキーワードで語られてい、これではブラック企業の経営者が喜ぶばかりだろう。
(2)共同体相互の関係。上に一部示したように、和辻は人間社会の「人倫的組織(=共同体)」を、家族・親族・地域共同体・経済的組織(企業など)・文化共同体(ある、一定、と見なし得る文化、例えば日本文化を共有していること)・国家、に分類している。近代人はこの全部、あるいは少なくともいくつかには属しているのが普通である。
それぞれの共同体には固有の論理と倫理があり、すべて相俟って人間社会を支えている。しかし、すべてが矛盾なく並び立つ、なんてことはない。それはかつての徴兵制があった時代の戦争を考えただけで明らかだろう。
男たちは基本的に、自分や家庭や地域の都合とは関係なく、国家の命令で戦地に赴き、最悪の場合には命を落とした(これが前回採り上げた「永遠の0」の主題)。今でも、企業人としての激務に追われ、家庭や親族間ではほとんど長期不在状態が続き、最悪その共同体の崩壊に繋がることもある。
こういう場合、最小のもの(家族)から最大のもの(国家)まで、共同体の範囲が広くなるのは当然だが、その分価値も高くなるように感じられるのは、功罪相半ばする、というか、当然なところと危険なところがある。
Ⅵ 改めて、国家とは何か
小浜は、現存する最大の共同体である国家については、その幻想性を語るところから始めている。
国家とは実体ではなく、人々があると思っているからある。ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』、吉本隆明『共同幻想論』、古くはカール・マルクス『ドイツ・イデオロギー』にも同じ考えはある。
一理あるが、殊更に「幻想」と呼ぶと、他所に何か実体があるような印象を与える。「しかし少し考えてみればわかるように、その程度はさまざまであれ、およそ人間が作る共同性は、すべてある意味で「想像」によって成り立ち、「幻想」を媒介としたものであることを免れない」(P.405)
これは「少し考えてみればわかる」ことではないかも知れない。例えばこういうことだろう。結婚して新たな家庭という共同体を創る場合、自分及び相手に対する幻想、と言って言葉が強すぎるなら、ある種の思い込み、あるいは期待、がなくて結婚生活は始めるケースは稀だろう。前述の〈信頼〉も、結局はこれに基づく。
だから、他のより小さな共同体に比べて、国家とは単なる幻想であり擬制だ、とは言えないのだが、しかし、その幻想―信頼の質そのものが、他とは決定的に違うものであることなら、誰にでも直感的にわかる。
小浜は国家を次のように定義している。「近代国民国家とは、人々がさまざまな形で共有する土着的・伝統的な同一性、同質性を基礎にしながら、それらを一つの統治構造によってまとめ上げていこうとする虚構であり、運動なのである」(P.407)
ポイントは〈運動〉とその〈作用〉というところにある。この着眼と表現は、たいへん適切なものだと思う。
第一に、国家は個々の政府機関のような実体なのではなくある統合性をもつ力の作用(はたらき)である。したがって第二に、その作用(はたらき)が有効に機能するために、統合を維持するに足る象徴性を必要とする(たとえば皇室や憲法や国旗や国籍のような)。そうして第三に、メンバー全員の間に、その象徴性に対して、たとえ無意識的にではあれ、同意と承認を与える心のシステムが成立しているのでなくてはならない。(P.410)
そうである以上、「愛国」という言葉は今もあるけれど、国家への〈愛〉とは、普通に使われるこの言葉の示す心の働きとはずいぶん違う。前回述べたことをもう少し詳しく言うと。
人は生まれ育った土地、いわゆる故郷に愛着を感じることはある。「忘れ難きふるさと」ということで。しかしそれは、唱歌の中でも、「兎追ひしかの山/小鮒つりしかの川」と歌われているように、風景や、そこで共に過ごした人々の具体的なイメージと結びついている。国全体となると、大きすぎて、各人が各人の想像力を使って思い浮かべるしかない。
保守派の論客が愛国心教育のためにとよく持ち出す日本文化も、非常に多様で曖昧な諸概念である。他国と比較すると、特徴が際立つようにも思えるのだが、日本国内で普通に暮らしていて、何が「日本的」かなどめったに意識することはないし、もちろんそれでよい。
逆から見ると、何が国の価値であって、どうすればそれを〈愛する〉ことになるのか、かなり好き勝手に言えることになる。サミュエル・ジョンソンの警句の通り「愛国心は悪党の最後の逃げ場」(もっともこの場合の愛国心はnationalismではなくて、patriotismだから「愛郷心」のほうが適当)になり得る。
これらを要するに、あらゆる共同体がフィクションではあるが、国家、特に近代国家は、人間が成長するにつれて自然に身につく情感や知見とは最も遠い、という意味で、最も人工性、つまりフィクション性が高い。
そもそもなぜ人類はこういうものを必要としたのか、小浜の論述から少し離れて、素朴なモデルを示しておくのも無駄ではあるまい。
例えば老子は、「小国寡民」こそが理想的な社会だとした。一番大事なのは、そこで暮らす人々が、小さな共同体の中で完全に自足し、今ある以上のものは求めないこと。ならば、他所と交通する意欲もなく、他人を羨むことも、争うこともない。すると、文明の進歩はない。文明は、人々に快適をもたらすが、それ以上に不幸をもたらすものだというわけなのだろう。一理ある。が、人類は、西洋でも東洋でも、ほとんどこの道を採らなかった。
今以上を求めるから、産業も商業も発展するのだが、一方、自分たちにはなくてよそにあるものを妬む心から、争いへとつながることは避けられない。争いはほとんど直ちに暴力に結びつき、他より立ち勝り、できれば支配するために、暴力の手段(兵器)も集団(軍隊)も発達する。これが野放図に横行したりしたら、明らかに安定した生活はない。
対応策として、ある集団が揮う暴力のみを正当(公的)として、他のすべてを禁ずる、といってもなくすことなどできないので、不当・不法として取り締まる、という方式が選ばれた。そのために国家という機関ができた、とさえ考えられる。
マックス・ウェーバーの有名な定義「国家とは、ある一定の領域内部で、正当な物理的暴力行使の独占を(実効的に)要求する人間共同体」(「職業としての政治」)はたとえ言い過ぎだとしても、それこそ、つまり暴力の管理こそは国家の枢要な仕事の一つであることはまちがいない。
ただし、暴力は悪なので、押さえるためには、それを上回る暴力がなくてはならない、というのは、矛盾に見える。そこでその暴力の正当化の根拠として、国家の正当性が宣揚された。先の引用文中の「土着的・伝統的な同一性、同質性」さらにそれを簡明にした「象徴性」が動員される。「この国は、神に選ばれた偉大な民族である我々が建てたのだ」というような。時には、このような神話とも呼ばれるフィクションが新たに創られる場合もある。
そして、暴力が最大限に発揮される場である対外戦争が仕上げをする。
ヨーロッパ中世期では、戦争は王侯貴族がやるもので、一般庶民は、無理矢理駆り出されたか、他は金で雇われた傭兵が大部分で、命がけで戦う義理など感じていなかった。戦局が剣呑になれば、すぐに逃げ出した。マキャベリ「君主論」には、合計二万の軍勢が四時間戦いながら、戦死者は一人だけ、それも落馬した時の怪我がもと、という例も書かれている。
徴兵制はフランス革命の産物だ。革命が自国に飛び火することを恐れたヨーロッパの諸王国は連合してフランスを攻撃した。フランスの国民公会は、これに対抗するために、様々な曲折の後、ルイ16世とマリー・アントワネットが処刑された年である1793年に「国民総動員令(または、「国民総徴兵法」)」を成立させ、18歳から25歳までの国内青年男子を動員し、百万人規模の軍隊を作った。この〈国民軍〉はその後ナポレオンに引き継がれ、戦時には民兵を指揮し、平時には軍事訓練に事とする専門の軍人によるいわゆる常設軍もできる。
これはその後すぐに西欧世界全体に広がり、ここに、〈国民〉とナショナリズムが歴史の前面に躍り出た。以前に書いたように、あらゆる共同体が〈内〉と〈外〉を分けるもので、程度の差こそあれ、排他的になる。この力学をさかさまにして、〈外〉の脅威とそれによる危機感を煽って、〈内〉の結束を強めるのもよくある手法である。
強大な外の脅威に対抗するには全力を挙げて戦わねばならない。戦争はいまや苛烈を極めたものとなり。何人もの人が命を落とす。すると、これまた逆転して、何人もが命懸けで保ち守ろうとしたからこそ、そこには価値がある何かが存在する、とも感じられる。それが即ち、(近代)国家である。
しかも国家の価値は、根拠は怪しい分だけ、巨大でダイナミックである。その一部として、その存続を懸命に保ち守ろうとすることで、個人の背丈を遙かに超えた歴史の過程に参入した感じになれる。
幻想だと言って侮る勿れ、その高揚感は、安定した日常生活では得られないものだ。20世紀の多くの若者を捉えた「革命」への熱情も、たとえ旧来の国家の廃絶を唱えたとしても、質的には同じである。いや、民主主義で、一国の政治に責任を感じて主体的に関わるように求められるなら、誰もがこの心性と無縁ではない。
現代では、欧米のいわゆる先進国の多くは、常設軍はあっても、徴兵制は廃止している。20世紀末に冷戦が終わり、デタント(緊張緩和)が訪れた結果なので、ウクライナ戦争でロシアの脅威が再び高まったので、また導入が検討される場合も稀ではないようだ。それでも、成人前の(たいてい)男子に兵役に就く気があるかどうか答えさせるのがせいぜいで、つまり、いやだと言えばそれまで、無理矢理兵士として使役するまではとてもやれないのが実際らしい(六辻彰二「徴兵制はなぜオワコンか――ウクライナ戦争でもほとんど‘復活’しない理由」)。
個人の意思の尊重をたてまえとする民主主義国ではそれが当然だろう。ただそれも、ヨーロッパの情勢次第ではどうなるかわからない。
戦後日本は徴兵どころか正式な軍隊もない。そもそも、国家意識に非常に乏しいと言われる。それでいて、国際性がどうのこうのと言っても、その「国際(各国の関係性)」の概念が他国の標準とは合っていないのではないかと思えるのだが、それはここで扱えるような問題ではない。
小浜も、上の意味の国家意識には乏しいと言えるだろう。国家とはそれ自体が愛憎の対象になる価値なのではなく、機能なのだ、としている。人類が今更小国寡民の原始時代に戻れない以上、現在の生産と流通の状態を維持するために、統括のための巨大組織が必要になる。犯罪の取り締まり。即ち警察力もなくてはすまない。ここに国家の実際的な存在意義もある。
(前略)近代国家の精神は、個人個人の愛国感情によって支えられるよりも、はるかに大きく、そこに属する住民の福祉と安寧とをいかに確保するかという機能的・合理的な目的意識によって支えられているからである。
このことは軍事・外交・安全保障にかかわる施策や行動においても例外ではない。もちろん実際の戦闘時の士気を維持することにとって参加メンバーの愛国心は大いに寄与しているように見えるが、それはよく個々のメンバーの行動心理に照らしてみれば、個人の愛国の情の力の集積というよりも、大きな目的を合理的に理解した上での、各部署における職業倫理と責任意識であり、同じ目的を追求していることから生じる同朋感情であり仲間意識なのである。これらがうまく機能するとき、「強い・負けない」国家はおのずと現れる。(pp.417~418、下線部は原文傍点部)
従ってここでも、何よりも各人が家庭や職場でそれぞれ具体的な責任を果たすことが重要であり、国家サイドからすると「身近な者たちへの愛が損なわれることのないような社会のかたち(秩序)をいかに練り上げるかという理性的な「工夫」」(P.420)こそが肝要と言うことになる。ここから前回掲げた「生活を共有する身近な者たちがよりよい関係を築きながら強く生きるという理念を核心に置き、その理念が実現する限りにおいてのみ、国家への奉仕も承認する」(p.466)という理念も出てくる。
私も国家の第一の目的は国民の安寧秩序を守るところにあるのは同意する。そのための国家は、できるだけ理性的・合理的に営まれるべきなのも、そうであろう。しかしその道は幾重にも折れ曲がっている。ナショナリズムというかなり非合理な感情一つとっても、そう簡単には決着がつかない。
そういうことに拘るのは、私が、小浜よりもっと、人間の暗黒面が気にかかる傾向があるからだ、ということは認めつつ、もう少し歩を進めたい。