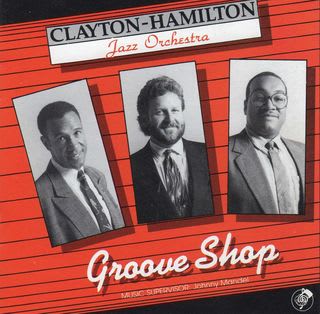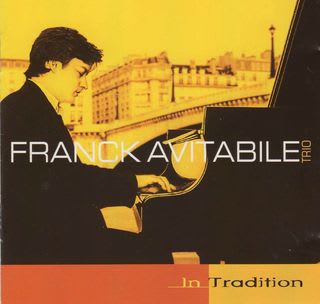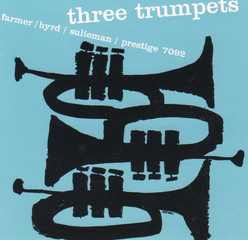High Heel Sneekers / Doug Lawrence
ベイシーオーケストラのサックスセクションのソリストといえば昔からテナーが要だ。古くはレスターヤングに始まり、黄金期のフランクフォスター、その後もエディーロックジョーデイビス、エリックディクソンと、多少スタイルが違ってもベイシーオーケストラのスイング感と良くマッチしたテナープレーが必須だ。
今のサックスセクションのメンバーはバリトン以外固定しているが、テナーは大柄のダグローレンス、そして小柄の方がダグミラー、どちらも味のあるソロを聴かせてくれる。今回の来日時も、920Specialでは二人でテナーバトルを繰り広げていた。このダグローレンスも、いつの間にかベイシーオーケストラに加わってから10年以上経ち、レギュラーメンバーとして要になっている。

数年前、ベイシーのライブを聴いてこのローレンスの演奏をもう少し聴いてみたいと思い、ベイシー以外のグループでの演奏を探したら、たまたま持ち合わせていたブッチーマイルスのアルバムに加わっていた。このアルバムを最初に聴いた時には、あまり意識せずに聴いていたが、ベイシーオーケストラの卒業生のブッチーマイルスと一緒ののびのびとした演奏も好演だ。
それではリーダーアルバムは?と思って、探して入手したのがこのアルバム。オルガンとギターを加えたクインテット編成だが、60年代のジミースミスを始めとしたファンキーなオルガンアルバムの雰囲気の演奏だ。ローレンスのテナーもスタンレータレンタイン風となり、いつもよりグルービーだ。
このローレンス、父親がミュージシャン6人兄弟の末っ子に生まれた。兄たちも皆ミュージシャンになったので、子供の頃から音楽には慣れ親しんで育ったそうだ。体が大きかったせいもあり13歳の時から父親のバンドに加わり演奏活動を始め、名門ノーステキサス州立大学のスカラーシップを得たにも関わらず、一方で地元のバンドのオーディションに受かったのでプロでの活動を優先した。ところがバンドが解散し、ラスベガスで仕事をしていた兄を頼ってテキサスを離れる。ところが、1975年当時のラスベガスはミュージシャンとっては働く場所がどんどん減っていた時期で、そこでも仕事にありつけず、止む無くニューヨークに行くことに。若い頃はあまり恵まれたキャリアではなかったようだ。
ニューヨークでは、ベニーグッドマン、バッククレイトンといったスイング系のバンドでプレーをする一方で、ワイルドビルデイビスのグループのレギュラーメンバーとなった。ローレンスにとってはこれがオルガンとの出会いで、このオルガンを加えたスタイルでの演奏がすっかり気に入ったそうだ。
という理由で、自分のグループで演奏する時は、このオルガンを加えた編成が多いようだ。
今回の来日時も、新しいアルバムのサイン会をやっていたので、中身も確かめずに記念に一枚購入したが、これも同じようにオルガンを加えた演奏。どうやら、ローレンスのスイング感の源は、このオルガンをバックにしたファンキーなプレーにあるようだ。
1. The Lamp Is Low P. DeRose / M. Parish / M. Ravel / B. Shefter 6:32
2. Get Out of Town Cole Porter 7:08
3. High Heel Sneakers Doug Lawrence 4:47
4. Crazy She Calls Me Bob Russell / Carl Sigman 6:03
5. The Masquerade Is Over H. Magidson / A.Wrubel 6:15
6. The Moon Was Yellow F. E. Ahlert / E. Leslie 4:45
7.Doug's Dilemma Adam Scone 6:50
8. Savoy Blues Doug Lawrence 5:38
9. Detour Ahead Lou Carter / Herb Ellis / John Freigo / Johnny Frigo 5:58
10. El Shakey John Webber 3:58
11. The Way You Look Tonight Dorothy Fields / Jerome Kern 6:30
Doug Lawrence (ts)
Peter Bernstein (g)
Adam Scone (org)
Dennis Irwin (b) 1,2,4,5,7,8,9,11
John Webber (b) 3,6,10
Willie Jones Ⅲ (ds)
Produced by Don Mikkeisen
Recording Engineer : Nihar Oza
Recorded at Fable Studios, New York on January 8 & 12 1998
ベイシーオーケストラのサックスセクションのソリストといえば昔からテナーが要だ。古くはレスターヤングに始まり、黄金期のフランクフォスター、その後もエディーロックジョーデイビス、エリックディクソンと、多少スタイルが違ってもベイシーオーケストラのスイング感と良くマッチしたテナープレーが必須だ。
今のサックスセクションのメンバーはバリトン以外固定しているが、テナーは大柄のダグローレンス、そして小柄の方がダグミラー、どちらも味のあるソロを聴かせてくれる。今回の来日時も、920Specialでは二人でテナーバトルを繰り広げていた。このダグローレンスも、いつの間にかベイシーオーケストラに加わってから10年以上経ち、レギュラーメンバーとして要になっている。

数年前、ベイシーのライブを聴いてこのローレンスの演奏をもう少し聴いてみたいと思い、ベイシー以外のグループでの演奏を探したら、たまたま持ち合わせていたブッチーマイルスのアルバムに加わっていた。このアルバムを最初に聴いた時には、あまり意識せずに聴いていたが、ベイシーオーケストラの卒業生のブッチーマイルスと一緒ののびのびとした演奏も好演だ。
それではリーダーアルバムは?と思って、探して入手したのがこのアルバム。オルガンとギターを加えたクインテット編成だが、60年代のジミースミスを始めとしたファンキーなオルガンアルバムの雰囲気の演奏だ。ローレンスのテナーもスタンレータレンタイン風となり、いつもよりグルービーだ。
このローレンス、父親がミュージシャン6人兄弟の末っ子に生まれた。兄たちも皆ミュージシャンになったので、子供の頃から音楽には慣れ親しんで育ったそうだ。体が大きかったせいもあり13歳の時から父親のバンドに加わり演奏活動を始め、名門ノーステキサス州立大学のスカラーシップを得たにも関わらず、一方で地元のバンドのオーディションに受かったのでプロでの活動を優先した。ところがバンドが解散し、ラスベガスで仕事をしていた兄を頼ってテキサスを離れる。ところが、1975年当時のラスベガスはミュージシャンとっては働く場所がどんどん減っていた時期で、そこでも仕事にありつけず、止む無くニューヨークに行くことに。若い頃はあまり恵まれたキャリアではなかったようだ。
ニューヨークでは、ベニーグッドマン、バッククレイトンといったスイング系のバンドでプレーをする一方で、ワイルドビルデイビスのグループのレギュラーメンバーとなった。ローレンスにとってはこれがオルガンとの出会いで、このオルガンを加えたスタイルでの演奏がすっかり気に入ったそうだ。
という理由で、自分のグループで演奏する時は、このオルガンを加えた編成が多いようだ。
今回の来日時も、新しいアルバムのサイン会をやっていたので、中身も確かめずに記念に一枚購入したが、これも同じようにオルガンを加えた演奏。どうやら、ローレンスのスイング感の源は、このオルガンをバックにしたファンキーなプレーにあるようだ。
1. The Lamp Is Low P. DeRose / M. Parish / M. Ravel / B. Shefter 6:32
2. Get Out of Town Cole Porter 7:08
3. High Heel Sneakers Doug Lawrence 4:47
4. Crazy She Calls Me Bob Russell / Carl Sigman 6:03
5. The Masquerade Is Over H. Magidson / A.Wrubel 6:15
6. The Moon Was Yellow F. E. Ahlert / E. Leslie 4:45
7.Doug's Dilemma Adam Scone 6:50
8. Savoy Blues Doug Lawrence 5:38
9. Detour Ahead Lou Carter / Herb Ellis / John Freigo / Johnny Frigo 5:58
10. El Shakey John Webber 3:58
11. The Way You Look Tonight Dorothy Fields / Jerome Kern 6:30
Doug Lawrence (ts)
Peter Bernstein (g)
Adam Scone (org)
Dennis Irwin (b) 1,2,4,5,7,8,9,11
John Webber (b) 3,6,10
Willie Jones Ⅲ (ds)
Produced by Don Mikkeisen
Recording Engineer : Nihar Oza
Recorded at Fable Studios, New York on January 8 & 12 1998
 | High Heel Sneakers |
| クリエーター情報なし | |
| Lightyear |