2016年1月16日(土)-4月3日(日) 東京都美術館

公式サイトはこちら
この展覧会は非常に混雑するだろうと思い、始まって1週間後くらいに足を運びました。しかしながら、≪ヴィーナス誕生≫や≪春≫が来るわけじゃないし、出品数もそれほど多くなさそうだから、さらっと観られるのではないかと安直に構えていたのですが・・・。
甘かった。実は東博の「始皇帝と大兵馬俑展」とはしごしたのですが、大混雑の東博でかなり集中力と体力を消耗していた身にはちょっと濃すぎる内容でありました。
何せ、私が勝手に本展の目玉だろうと高をくくっていた≪ラーマ家の東方三博士の礼拝≫が、最初の部屋に入るなりいきなり登場するのですから。この作品をしょっぱなに持ってくるところに主催者の本気モードが伝わってくるようです。
その≪ラーマ家の東方三博士の礼拝≫の左方にはロレンツォ豪華王の巨大なブロンズ像が鎮座し、さっきまで紀元前3世紀の中国大陸にどっぷりつかっていた私の頭は、瞬時にルネッサンス美術の咲き誇る15世紀のフィレンツェへ切り替わることとなりました。
このように時空を自由に旅できる美術館や博物館が集まる上野の山は、やはりすごいところですね~。
さて本題ですが、下記の各章のタイトルが示す通り、本展ではボッティチェリ本人の作品のみならず(と軽く言いましたが、ボッティチェリの真筆が20点も一堂に会するなんて凄いことです)、師匠のフィリッポ・リッピ、弟子のフィリピーノ・リッピ(フィリッポ・リッピの息子)、そして同時代の画家たちの作品も含め、計78点が並びます:
1章 ボッティチェリの時代のフィレンツェ
2章 フィリッポ・リッピ、ボッティチェリの師
3章 サンドロ・ボッティチェリ、人そして芸術家
4章 フィリッピーノ・リッピ、ボッティチェリの弟子からライバルへ
個人的に興味深かった作品を何点か挙げてみます:
≪書斎の聖アウグスティヌス(あるいは聖アウグスティヌスに訪れた幻視)≫ 1480年頃

フィレンツェには2回ほど行ったことがありますが、オニサンティ聖堂をついぞ訪ねることができず、観ることが叶わなかった作品です。まさか先方から東京に会いに来てくれるなんて夢のよう。だって、これ結構大きなフレスコ画ですよ。よくぞはるばる日本まで運んで下さいました。しかも、美術館でこうして展示されている方が、美術作品としては聖堂内より近くでじっくりと鑑賞できるのではないでしょうか。というわけで、聖人のお顔をはじめ隅から隅までゆっくりと拝見しました。
≪聖母子(書物の聖母)≫ 1482~83年頃

もう10年も前の話ですが、この作品の所蔵元であるミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館には一度行ったことがあって、確かにこの作品を観た記憶はあります(ポストカードも買っていますし)。しかし、この美術館に行く前に巨大なブレラ美術館を歩き回っていたせいでヘトヘトに疲れ、頭の中はすでに飽和状態。
というわけで、今回改めてこの作品の前に立ち、その美しさが心に沁み込んだような次第です。聖母のまとう深みのある青いマント、光輪や金糸装飾の繊細な描き込み。高級な顔料がふんだんに用いられ、全体的にもしまった画面構成で、ボッティチェリが高い集中力を注ぎこんだことが伺える作品です。
≪胸に手をあてた若い男の肖像≫ 1482-85頃 *2月25日までの期間限定展示

忽然と現れた流し目のイケメンにちょっとドキドキ。ボッティチェリの作品は遠近法などはさほど重視されず、輪郭線を描きこむ画法が日本の伝統的な絵画にも通ずるのではと言われますが、私はやはり小学生の頃読んでいた少女マンガが浮かんできます。
以前ウフィツィ美術館のボッティチェリ作品の展示室に入り、彼の描く美少年たち(天使たち)に囲まれた時、その余りの美しさになんだか涙が出てしまったのですが、今思えば小学校時代の少女マンガのノスタルジーが幾分作用したのかもしれません。
輪郭線といえば、私はボッティチェリの人体のパーツの描き方で昔から目がいってしまうポイントが二つあります。一つは、時にいびつなほど長い特徴ある足の指。もう一つは、くっきり平坦に描かれた手足の爪です。師リッピの作品からはあまり感じられない要素で、ボッティチェリ独自の表現に見えます。
≪温和なミネルウァ(女神パラス)≫ 1494-1500年頃
ボッティチェリの原寸大下絵をもとに織られた大きなタペストリー。中央には女神パラスが立っていますが、風になびく長い髪と衣、右足に重心を置くS字気味のポーズは一目でボッティチェッリ作とわかります。彼の甘美な女性像を織物に仕立てるのも、絵画とは異なる趣があってなかなかいいものだと思いました。
≪オリーヴ園の祈り≫ 1495-1500年頃

修道士サヴォナローラに傾倒した後の作品は、ロレンツォ・イル・マニーフィコとつるんでいた頃の、ふんわりと優美な作風とは打って変わってギスギスしたものとなりますが、本作はまるでフランドル絵画。色彩は鮮やかですが、禁欲的と言いますか、登場人物の表現よりも画題ありきといった仕上がりです。これがボッティチェリの筆による作品かと驚きました。
以上、ボッティチェリの作品ばかり挙げましたが、アントニオ・デル・ポッライオーロの≪竜と戦う大天使ミカエル≫も来ていましたし、素描類が観られるのも貴重です。
ボッティチェリはやはり春がお似合いです。本展はあと1週間足らずで終わってしまいますが(4月3日まで)、はらはらと舞う上野の山の桜の花びらを受けながら足を運ぶのもいいかもしれませんね。

公式サイトはこちら
この展覧会は非常に混雑するだろうと思い、始まって1週間後くらいに足を運びました。しかしながら、≪ヴィーナス誕生≫や≪春≫が来るわけじゃないし、出品数もそれほど多くなさそうだから、さらっと観られるのではないかと安直に構えていたのですが・・・。
甘かった。実は東博の「始皇帝と大兵馬俑展」とはしごしたのですが、大混雑の東博でかなり集中力と体力を消耗していた身にはちょっと濃すぎる内容でありました。
何せ、私が勝手に本展の目玉だろうと高をくくっていた≪ラーマ家の東方三博士の礼拝≫が、最初の部屋に入るなりいきなり登場するのですから。この作品をしょっぱなに持ってくるところに主催者の本気モードが伝わってくるようです。
その≪ラーマ家の東方三博士の礼拝≫の左方にはロレンツォ豪華王の巨大なブロンズ像が鎮座し、さっきまで紀元前3世紀の中国大陸にどっぷりつかっていた私の頭は、瞬時にルネッサンス美術の咲き誇る15世紀のフィレンツェへ切り替わることとなりました。
このように時空を自由に旅できる美術館や博物館が集まる上野の山は、やはりすごいところですね~。
さて本題ですが、下記の各章のタイトルが示す通り、本展ではボッティチェリ本人の作品のみならず(と軽く言いましたが、ボッティチェリの真筆が20点も一堂に会するなんて凄いことです)、師匠のフィリッポ・リッピ、弟子のフィリピーノ・リッピ(フィリッポ・リッピの息子)、そして同時代の画家たちの作品も含め、計78点が並びます:
1章 ボッティチェリの時代のフィレンツェ
2章 フィリッポ・リッピ、ボッティチェリの師
3章 サンドロ・ボッティチェリ、人そして芸術家
4章 フィリッピーノ・リッピ、ボッティチェリの弟子からライバルへ
個人的に興味深かった作品を何点か挙げてみます:
≪書斎の聖アウグスティヌス(あるいは聖アウグスティヌスに訪れた幻視)≫ 1480年頃

フィレンツェには2回ほど行ったことがありますが、オニサンティ聖堂をついぞ訪ねることができず、観ることが叶わなかった作品です。まさか先方から東京に会いに来てくれるなんて夢のよう。だって、これ結構大きなフレスコ画ですよ。よくぞはるばる日本まで運んで下さいました。しかも、美術館でこうして展示されている方が、美術作品としては聖堂内より近くでじっくりと鑑賞できるのではないでしょうか。というわけで、聖人のお顔をはじめ隅から隅までゆっくりと拝見しました。
≪聖母子(書物の聖母)≫ 1482~83年頃

もう10年も前の話ですが、この作品の所蔵元であるミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館には一度行ったことがあって、確かにこの作品を観た記憶はあります(ポストカードも買っていますし)。しかし、この美術館に行く前に巨大なブレラ美術館を歩き回っていたせいでヘトヘトに疲れ、頭の中はすでに飽和状態。
というわけで、今回改めてこの作品の前に立ち、その美しさが心に沁み込んだような次第です。聖母のまとう深みのある青いマント、光輪や金糸装飾の繊細な描き込み。高級な顔料がふんだんに用いられ、全体的にもしまった画面構成で、ボッティチェリが高い集中力を注ぎこんだことが伺える作品です。
≪胸に手をあてた若い男の肖像≫ 1482-85頃 *2月25日までの期間限定展示

忽然と現れた流し目のイケメンにちょっとドキドキ。ボッティチェリの作品は遠近法などはさほど重視されず、輪郭線を描きこむ画法が日本の伝統的な絵画にも通ずるのではと言われますが、私はやはり小学生の頃読んでいた少女マンガが浮かんできます。
以前ウフィツィ美術館のボッティチェリ作品の展示室に入り、彼の描く美少年たち(天使たち)に囲まれた時、その余りの美しさになんだか涙が出てしまったのですが、今思えば小学校時代の少女マンガのノスタルジーが幾分作用したのかもしれません。
輪郭線といえば、私はボッティチェリの人体のパーツの描き方で昔から目がいってしまうポイントが二つあります。一つは、時にいびつなほど長い特徴ある足の指。もう一つは、くっきり平坦に描かれた手足の爪です。師リッピの作品からはあまり感じられない要素で、ボッティチェリ独自の表現に見えます。
≪温和なミネルウァ(女神パラス)≫ 1494-1500年頃
ボッティチェリの原寸大下絵をもとに織られた大きなタペストリー。中央には女神パラスが立っていますが、風になびく長い髪と衣、右足に重心を置くS字気味のポーズは一目でボッティチェッリ作とわかります。彼の甘美な女性像を織物に仕立てるのも、絵画とは異なる趣があってなかなかいいものだと思いました。
≪オリーヴ園の祈り≫ 1495-1500年頃

修道士サヴォナローラに傾倒した後の作品は、ロレンツォ・イル・マニーフィコとつるんでいた頃の、ふんわりと優美な作風とは打って変わってギスギスしたものとなりますが、本作はまるでフランドル絵画。色彩は鮮やかですが、禁欲的と言いますか、登場人物の表現よりも画題ありきといった仕上がりです。これがボッティチェリの筆による作品かと驚きました。
以上、ボッティチェリの作品ばかり挙げましたが、アントニオ・デル・ポッライオーロの≪竜と戦う大天使ミカエル≫も来ていましたし、素描類が観られるのも貴重です。
ボッティチェリはやはり春がお似合いです。本展はあと1週間足らずで終わってしまいますが(4月3日まで)、はらはらと舞う上野の山の桜の花びらを受けながら足を運ぶのもいいかもしれませんね。


















 部分
部分

 部分
部分 右隻・部分
右隻・部分 左隻・部分
左隻・部分 左隻・部分
左隻・部分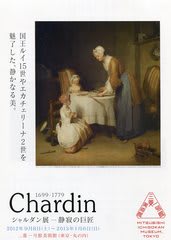



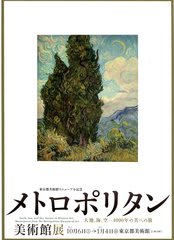





 (部分)
(部分)