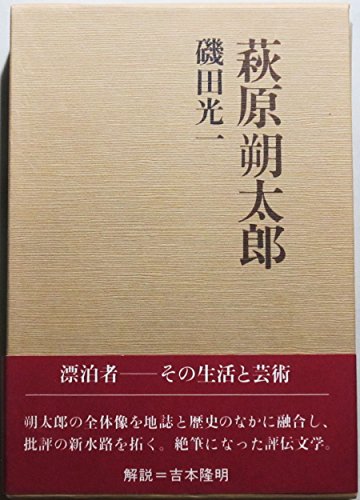室生犀星の『蒼白き巣窟』を読みながら連想されたのは、石川啄木の桑原武夫編訳『ローマ字日記』(岩波文庫)であった。
これは磯田光一の『萩原朔太郎』(講談社)において、あらためて教えられたのだが、朔太郎と啄木がともに明治十九年生まれであり、朔太郎が四十三年に出され啄木の『一握の砂』(東雲堂書店)を強く意識していたということである。そしてそこには次の一首が含まれていた。
わが泣(な)くを少女等(をとめら)きかば
病犬(やまいぬ)の
月(つき)に吠(ほ)ゆるに似(に)たりといふらむ
近代文学館の複刻版を確認してみると、最初の「我を愛する歌」のセクション、すなわち十一ページ、十八首目にそれを見出せる。「東海の小島の磯の白砂に」や「いたく錆びしピストル出でぬ」といった著名なフレーズに紛れて、記憶に残っていなかったものだ。しかしその巻末広告を見ると、やはり同年に若山牧水の『別離』、北原白秋の『思ひ出』も出されていたとわかる。それに前者は拙稿「西村陽吉と東雲堂書店」(『古本探究』所収)で言及しているし、後者はこれもまた日本図書センターによって複刻されているので、容易に参照できる。
それらはともかく、磯田は続けて四十四年のニーチェの生田長江訳『ツアラトウストラ』(新潮社)に見える月光のもとでの野犬の存在を示し、大正六年の『月に吠える』のタイトルとイメージの起源がこれらによっているのではないかと指摘していた。そうした事実を通じて、啄木、朔太郎、犀星、白秋が同時代人で、それぞれの詩集が相互影響していたことを示唆してくれる。それに『月に吠える』も『愛の詩集』も、「序」に当たる一文は白秋によって書かれていたし、犀星や朔太郎と同様に、啄木にとっても、白秋の『邪宗門』はインパクトをもたらしたはずで、実際に献本されていたのである。それらを『ローマ字日記』から抽出してみる。いずれも1909年=明治四十二年のものだ。

 (『月に吠える』)
(『月に吠える』)
 (『愛の詩集』)
(『愛の詩集』) (『邪宗門』)
(『邪宗門』)
[4月3日]
キタハラ君のおばさんがきた。そしてかれの新詩集“邪宗門”を1冊もらった。(中略)
夜2時まで“邪宗門”を 読んだ。美しい、そして特色のある本だ。キタハラは幸福な人だ!
ぼくも なんだか詩を書きたいような心持になって ねた。
[4月6日]
(前略)
キタハラ君を たずねようかと思ったが、そのうちに12時ちかくになったので、こぶさたの おわびをかねて 『邪宗門』についての手紙をやった。――“邪宗門”には まったく新しい ふたつの特長がある:そのひとつは“邪宗門”ということばの有する連想 といったようなもので もうひとつは この詩集にあふれている 新しい感覚と情緒だ。そして、前者は 詩人ハクシュウを解するに もっとも必要な特色で、後者は 今後の新しい詩の基礎とをなるべきものだ・・・・・・。
それから啄木は手元不如意となり、5月8日から13日の間に「キタハラからおくられた“邪宗門”も売ってしまった」のである。
犀星の場合、前々回記しておいたように、明治四十二年の金沢にあって、同じ頃啄木とは逆に、『邪宗門』を取り寄せ、買い求めていたのである。そのようにして二人は同時代に白秋の『邪宗門』の読者だったわけだが、共通するのはそれだけでなく、啄木もまた同じく十二階下の「蒼白き巣窟」の探訪者だったのだ。彼は4月10日付で記している。「いくらかの金のあるとき、予は なんのためろうことなく、かの、みだらな声にみちた、狭い、汚い町に行った。(中略)そして10人ばかりの、インバイフを買った」と。そしてこの後によく知られた具体的なフィストファッキングの実際が語られていくのである。それはヨーロッパ世紀末のミソジニーの系譜に連なる男には「女を殺す権利がある!」という告白を伴いながら。
5月1日にも「また行くのか?」と自問しながら浅草に出かけている。
“行くな! 行くな!”と思いながら 足はセンゾクマチへ向かった。ヒタチ屋の前を ソッとすぎて、キンカ亭という 新しい角のうちの前へ行くと 白い手がコウシのあいだから出て 予のソデをとらえた。フラフラとして入った。
ああ、その女は! 名はハナコ、年は17。ひと目見て 予はすぐそう思った。
“ああ! コヤッコだ! コヤッコをふたつみつ若くした顔だ!”
「コヤッコ」とは啄木が北海道時代に馴染んだ芸者小奴のことである。また「センゾクマチ」とは槌田満文編『東京文学地名辞典』(東京堂)によれば、浅草区千束町のことで、浅草公園から吉原へ向かう通路に当たり、二丁目が最もにぎやかで、よく知られた牛店米久を始めとして、料理や、貸席、芸妓家、待合、銘酒屋などが多かった。また「十二階」と俗称された凌雲閣がそびえていたのも二丁目だった。その周辺は私娼が多く、「十二階下」と呼ばれていたのである。

『ローマ字日記』には「十二階」なる言葉は使われていないが、『蒼白き巣窟』には復元された部分に「十二階の塔が、六角に創り上げた尖端を深い暗い空につきぬけて聳立している」との一文が見えていた。啄木の時代は前述したように明治四十二年、『蒼白き巣窟』は明治四十五年とあるので、ほぼ同時代の「十二階下」に啄木も犀星も出没していたことになろう。
[関連リンク]
過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら