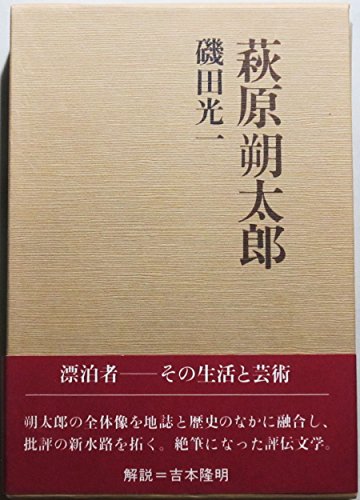前回の『十二階崩壊』に見られる今東光の「十二階」への否定的見解とは対照的な思いを描いていた同時代人もいたにちがいない。その一人は江戸川乱歩であり、「十二階」を舞台装置として昭和四年(『新青年』六月号)に「押絵と旅する男」を発表している。
米沢嘉博構成『乱歩の時代』(「別冊太陽」)において、「押絵」はカラー実物が示され、次のように定義されている。「厚紙で人物などを作り、綿などを入れてふくらみをつけ、布をかぶせて作る。武者人形など、歴史物語のヒーローが登場する。明治から大正にかけての子どもたちの玩具」だと。ここでの「押絵と旅する男」のテキストは『江戸川乱歩集』(『日本探偵小説全集』2、創元推理文庫)所収を参照しているのだが、念のために、本の友社復刻版『新青年』の当月号も見ている。それには竹中英太郎による「十二階」と押絵の挿画も掲載され、この巻頭の短編のリアルタイムでの読書体験の実際を伝えているかのようだ。またその編集後記に当たる「戸崎町だより」には「東京市内の某書店では毎号発売後旬日ならずして千部近い部数を売り尽くす程」だと述べられている。これは「一記者」とあって、編輯兼発行人の森下岩太郎=雨村の筆によるものではないけれど、昭和四年時の探偵小説ブームを示唆していよう。
「押絵と旅する男」は「この話が私の夢か私の一時的狂気の幻でなかったなら、あの押絵と旅していた男こそ狂人であったに違いない」と始まっている。「私」は魚津に蜃気楼を見に出かけた帰りの上野行の汽車で、西洋の魔術師のような風采の男が持っている額に興味を覚え、それを見せてくれと頼む。するとその額には歌舞伎芝居の御殿に似た背景の中で、押絵細工の二人の人物が浮き出て、黒ビロードの古風な洋服を着た白髪の老人と十七、八の結い綿の美少女が芝居の濡れ場に類する画面を形成していた。それに奇妙なことに二人は生きているようでもあった。さらに男は古風な双眼鏡を取り出し、これで見るようにと「私」に差し出すので、そうすると、押絵の娘は生気に満ち、一方で、老人は苦悶の相を現わし、別世界で奇妙な生活を営んでいるかのようだった。
そして男の口から押絵の老人=兄の身の上話が語り出される。それは明治二十八年四月の浅草の十二階が出来たばかりの頃で、毎日のように兄は凌雲閣にあの遠眼鏡を手にして登っていたのである。
「あなたは、十二階へお登りなすったことがおありですか。ああ、おありなさらない。それは残念ですね。あれは一体、どこの魔法使いが建てましたものか、実に途方もない変てこれんな代物でございましたよ。表面はイタリーの技師のバルトンと申すものが設計したことになっていましたがね。まあ考えてごらんなさい。その頃の浅草公園といえば、名物がまず蜘蛛男の見世物、娘剣劇に、玉乗り、源水のコマ廻しに、のぞきからくりなどで、せいぜい変ったところが、お富士さまの作りものに、メーズといって、八陣隠れ杉の見世物ぐらいでございましたからね。そこへあなた、ニョキニョキと、まあとんでもない高い煉瓦造りの塔ができちまったんですから、驚くじゃござんせんか。高さが四十六間と申しますから、一丁に少し足りないぐらいの、べらぼうな高さで、八角型の頂上が唐人の帽子みたいにとんがっていて、ちょっと高台へ登りさえすれば、東京中どこからでも、その赤いお化けが見られたものです。」
乱歩が「押絵と旅する男」を発表したのは先述したように、昭和四年だったことからすれば、関東大震災による十二階崩壊からすでに六年が過ぎていた。そうした時の流れと過去の記憶は、凌雲閣の十二階をして、「魔法使いが建て」た「赤いお化け」と称されるファンタスティックな塔へと昇華させられていたことになる。
それはともかく、兄の身の上話に戻れば、彼は遠眼鏡を手にして以来、毎日どこかに出かけるようになり、やつれて青ざめ、気でもちがったのではないかと心配された。そこで弟が兄のあとをつけると、兄は浅草に向かい、凌雲閣の十二階の中へ姿を消してしまった。当時は日清戦争の生々しい血みどろの油絵が壁に並べられていたので、「兄はこの十二階の化物に魅入られたんじゃないか」と弟は考えたりもした。しかしそれらの絵の中を上がっていくと頂上に達し、兄が遠眼鏡を目に当て、観音様の境内を眺め廻している姿を認め、弟は「兄さん何を見ていらっしゃいます」と声をかけた。
すると兄はようやく胸のうちの秘密を打ち明けてくれた。一ヵ月前にこの十二階から遠眼鏡で観音様の境内を眺めていたら、「ひとりの娘の顔」、それも「この世のものとは思えない美しい人」を見た。ところがその娘にすっかり心を乱され、遠眼鏡を外してしまい、もう一度見ようとしても探し出せなかった。それから兄はこの美しい娘が忘れられず、毎日十二階に昇り、遠眼鏡をのぞいていたのである。
そこに何かの前兆のように、赤や青や紫の無数の風船が立ち登り、ちょうどその時、兄は娘を見つけたらしく、それは観音様の裏手の大きな松のところの広い座敷にいたという。だが娘の姿も影も形もなかった。そこで兄と別れて探し回ったが、兄は一軒の覗きからくり屋の覗きめがねを見て、夢を見ているかのように、「私たちが探していた娘さんはこの中にいるよ」といった。それは八百屋お七の覗きからくりで、お七が吉三にしなだれかかっている絵だった。その絵は光線をとるために上の方があけてあり、そのために十二階の頂上からに見えたにちがいない。からくり屋の夫婦がしわがれ声で「膝でつっつらついて、眼で知らせ」と歌っていた。
兄はいう。「たとえこの娘さんがこしらえものの押絵だとわかっていても、私もどうもあきらめられない。(中略)たった一度でいい。私もあの吉三のように、押絵中の男になって、この娘さんと話がしてみたい」。そして兄はいつまでも立ちつくし、すっかり日も暮れてしまった。すると兄は突然遠眼鏡をさかさにして、「そこから私を見ておくれでないか」と頼む。そうすると、兄の姿が小さくなり、闇の中に消えてしまった。覗きめがねを見ると、兄は押絵となり、吉三の代わりに、「嬉しそうな顔をして、お七を抱きしめていた」のである。
それから弟のほうはその覗き絵を手に入れ、兄と一緒に旅するようになった。だが娘は年をとらないけれど、兄は寿命のある人間ゆえに老人となり、悲しげで苦しそうな顔をさらすようになってきたのである。
そして押絵の額を携えていた老人も、山間の小駅の闇の中に消えていったのだ。
[関連リンク]
過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら