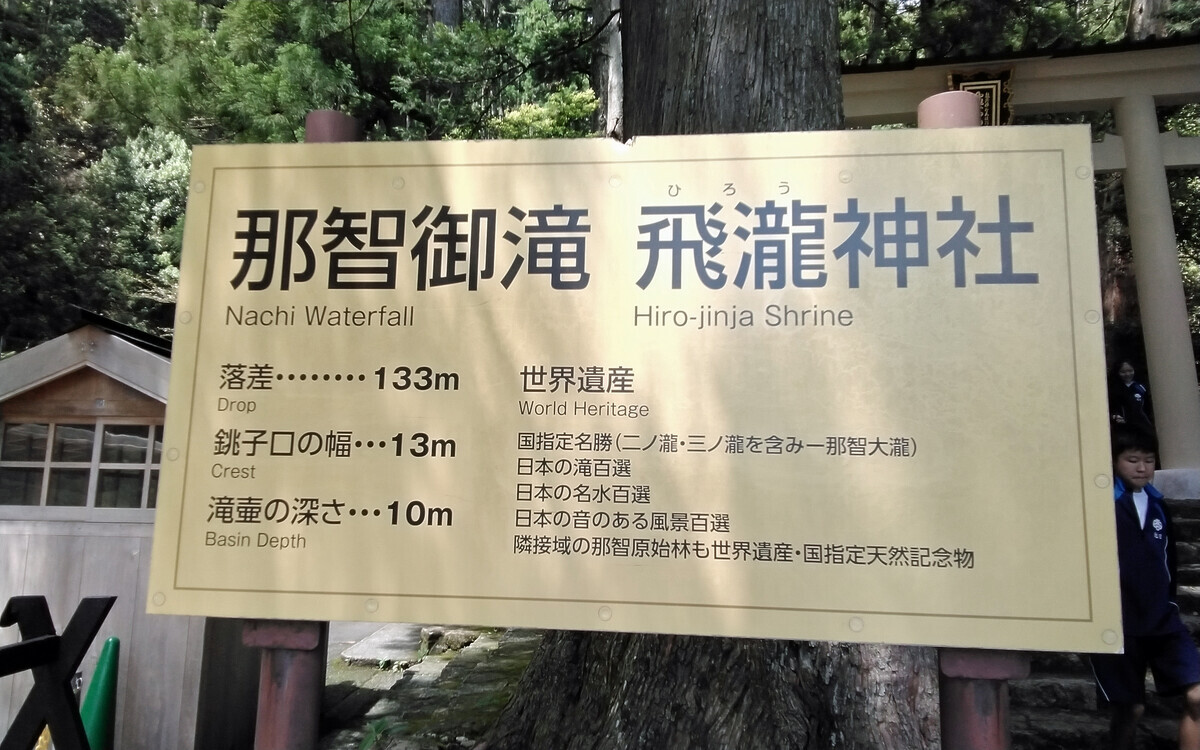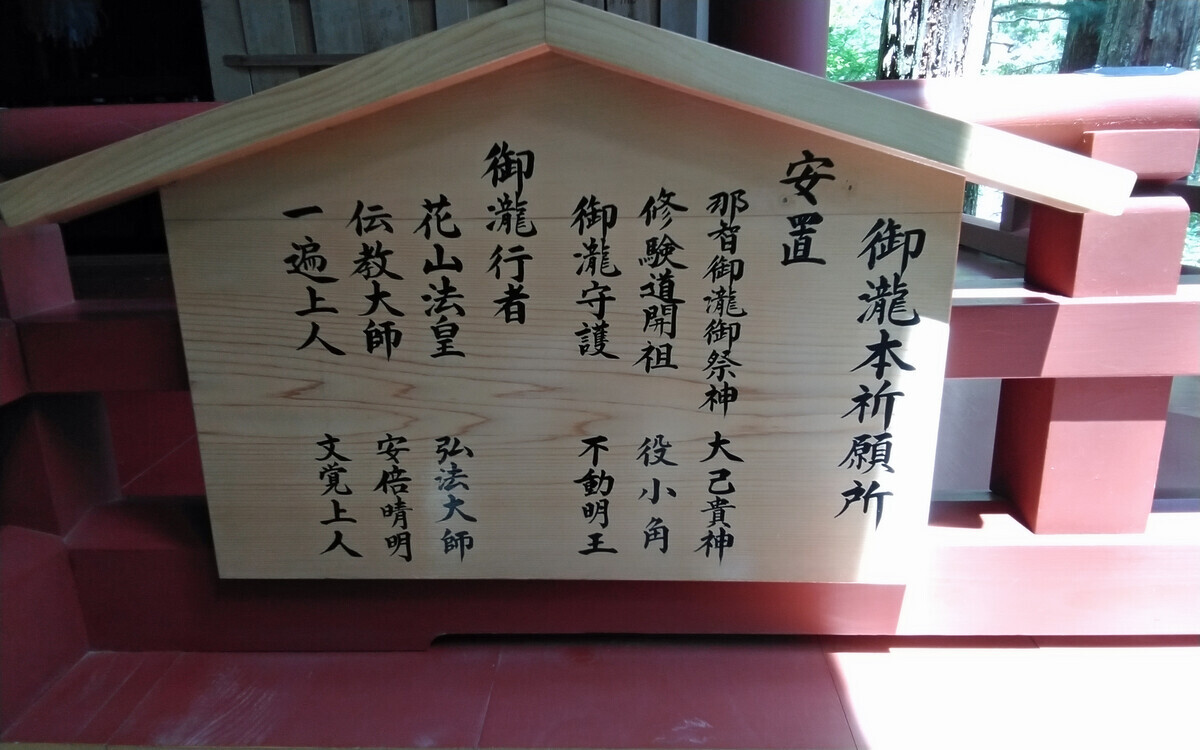久々にスコンと腹落ちする整体の本に出合いました。
『痛みが消える自力整体』(矢上裕・新星出版社・1,500円)です。
著者は体の不具合を「歪み」と「疲労の蓄積」と喝破しています。
著者も若い頃は「よく食べ、よく運動する」ことが健康を維持する方法だと思い込んでいたので、毎日2万歩以上歩いていたそうです。
ところが47歳の時に突然ギックリ腰で動けなくなりました。
「歩くのをやめたら足腰が弱る」という強迫観念のために、長時間歩いていたわけですが、そのために骨盤を歪めてしまっていたのです。
整体の先生として“とても”恥ずかしい思いをし、それ以降は180度考えを変え「できるだけ筋力を温存して、足腰にゆがみや疲れを溜めない」を実践しているとのこと。
「鍛えて疲れるより、体を左右対称に整える方が先」と指導し、実際に多くの人に良い結果が出ているそうです。
「老化が進んでいる」は「疲労が蓄積している」と同じ意味ということなのです。
私は昼食を抜き1日2食にしてから劇的に体調が良くなったのですが、この著者は1日1食。
筋肉や内臓を使い過ぎないことがポイントで、使い過ぎたら「疲労ゼロ」に戻すことが大事だということです。