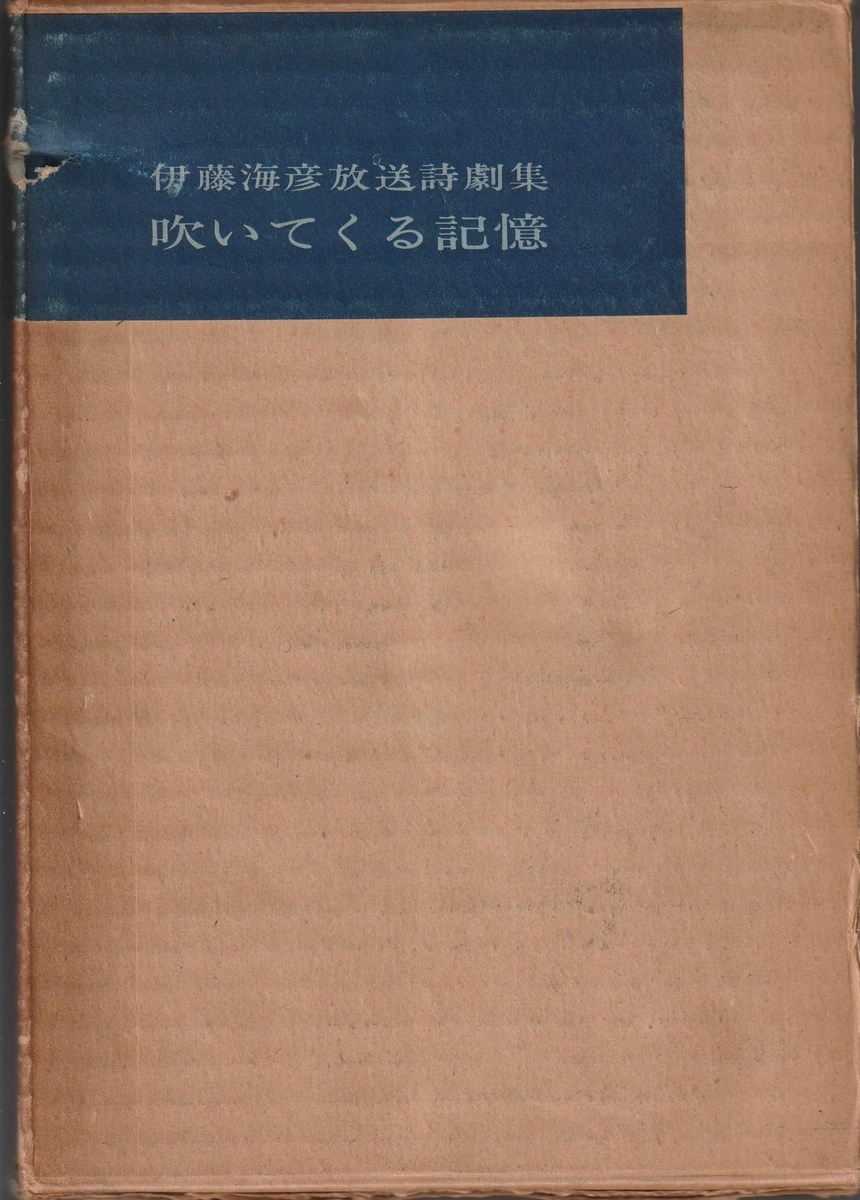2か月ぶりの古本報告です。4月は二つの大きな古本市がありました。
まず阪神百貨店の古書ノ市には、初日の朝、大阪で会社OB麻雀会があり、1時間ほど時間があったので覗いてきました。
オヨヨ書林の出品コーナーからは、
原葵『くじら屋敷のたそがれ』(国書刊行会、20年10月、800円)
小野恭靖『ことば遊びの世界』(新典社、05年11月、500円)
→こんな本が出てたのは知らなんだ。判じ物や漢字遊びなど例が豊富。
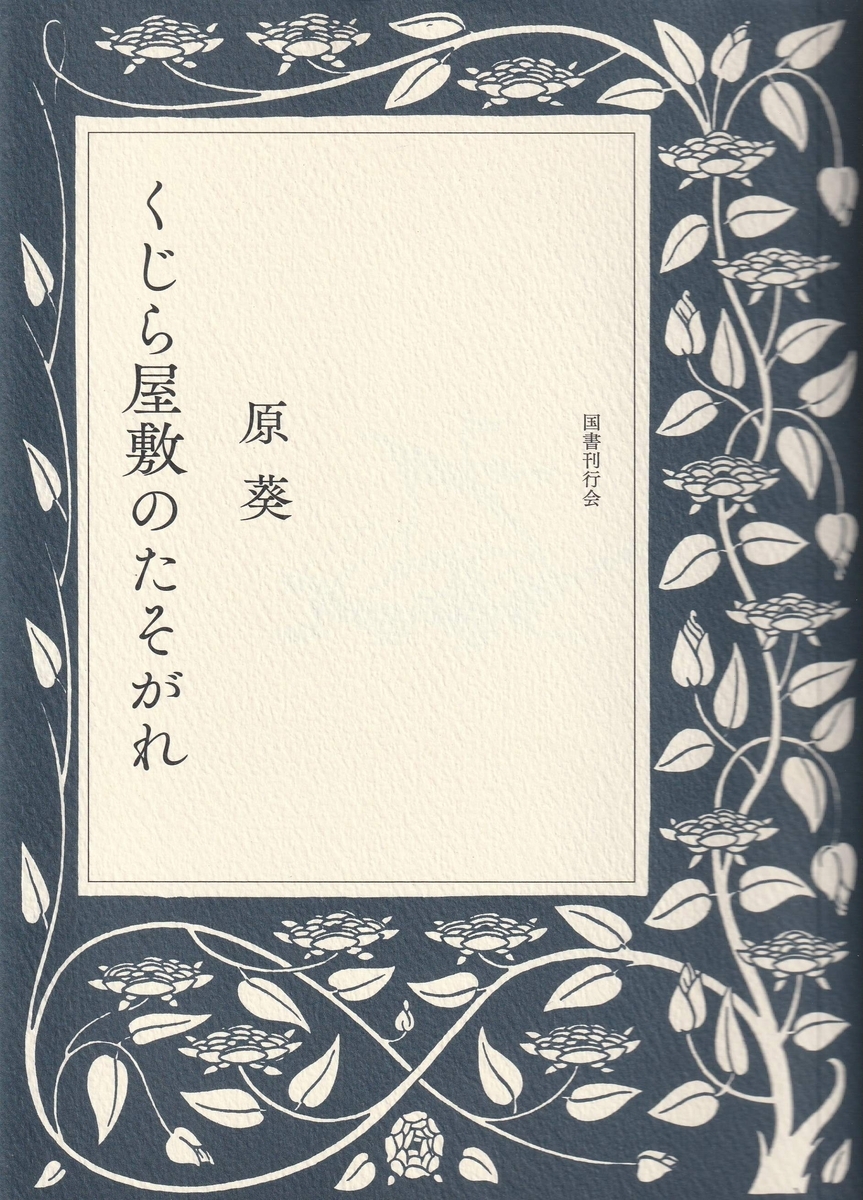
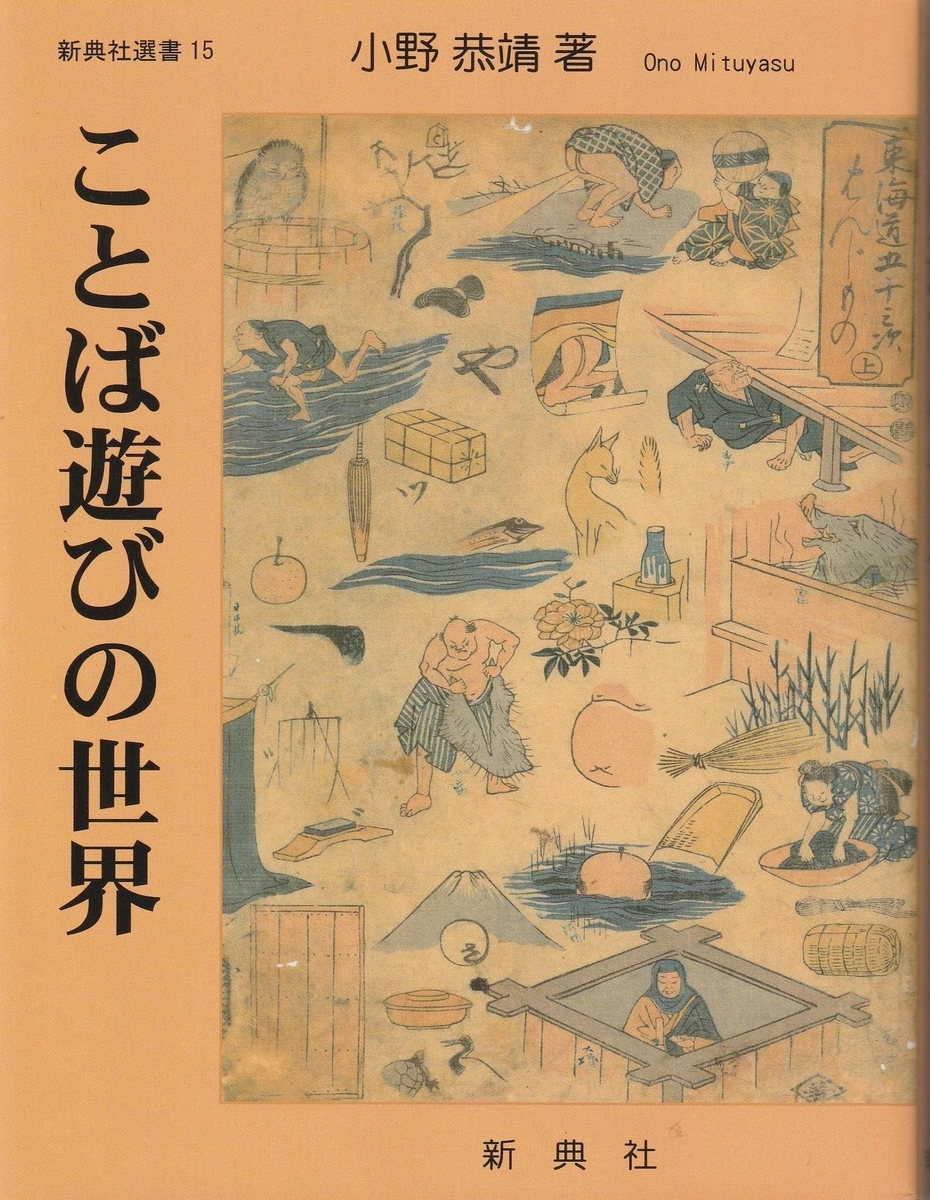
ワールドエンズガーデンからは、
金森修『ゴーレムの生命論』(平凡社新書、10年10月、400円)
関根正雄訳『旧約聖書 ヨブ記』(岩波文庫、92年2月、300円)
→「コヘレトの言葉」と共通しているものがあるとのことで。

大阪市天王寺の春の大古本祭りでは、初日に古本仲間が集まりました。
まず、小町書店の5冊800円で、下記を購入。
村上道太郎『萬葉草木染め』(新潮選書、昭和59年9月、160円)
→志村ふくみの本を読んでいて草木染目に興味が湧いてきた
辻邦生『神さまの四人の娘』(湯川書房、昭和47年12月、160円)
→限定200部中56番
林屋辰三郎『西方見聞録』(筑摩書房、昭和59年9月、160円)
松本和男『詩人 堀口大學』(白鳳社、96年1月、160円)
→定価5000円のきれいな本が!
鈴木大拙『日本的霊性』(岩波文庫、15年2月、160円)



次にしおり書房で下記2冊。
ウィルヘルム=ハウフ塩谷太郎訳『アレッサンドリア物語―ハウフ童話全集Ⅱ』(偕成社文庫、77年11月、200円)
→こんな全集があったのは知らなんだ、つい嬉しくなり。
ウィルヘルム=ハウフ塩谷太郎訳『シュッペサルトの森の宿屋―ハウフ童話全集Ⅲ』(偕成社文庫、77年11月、200円)


池崎書店では1冊のみ。
ポール・ツヴァイク中村保男訳『冒険の文学―西洋世界における冒険の変遷』(法政大学出版局、90年6月、300円)

最後に、100円均一コーナーで、「3冊まで無料」のハガキを持っていたので、下記2冊は無料。1冊は仲間にプレゼント。
栗田勇『神やどる大和』(新潮社、昭和61年3月、無料)
中尾佐助『花と木の文化史』(岩波新書、86年11月、無料)

全部合わせて10冊、1500円。野外古本市は安さが魅力です。
古本屋での購入は、3月に、大相撲観戦で難波に出たついでに、難波天地書房で買った1冊のみ。
堀江敏幸『坂を見あげて』(中央公論新社、18年2月、1200円)
→上に比べるとずいぶん高い

「日本の古本屋」では下記を購入。
熊田陽一郎『美と光―西洋思想史における光の考察』(国文社、86年12月、1650円)
→ほとんど偽ディオニシウス・アレオパギテースをめぐっての論稿。
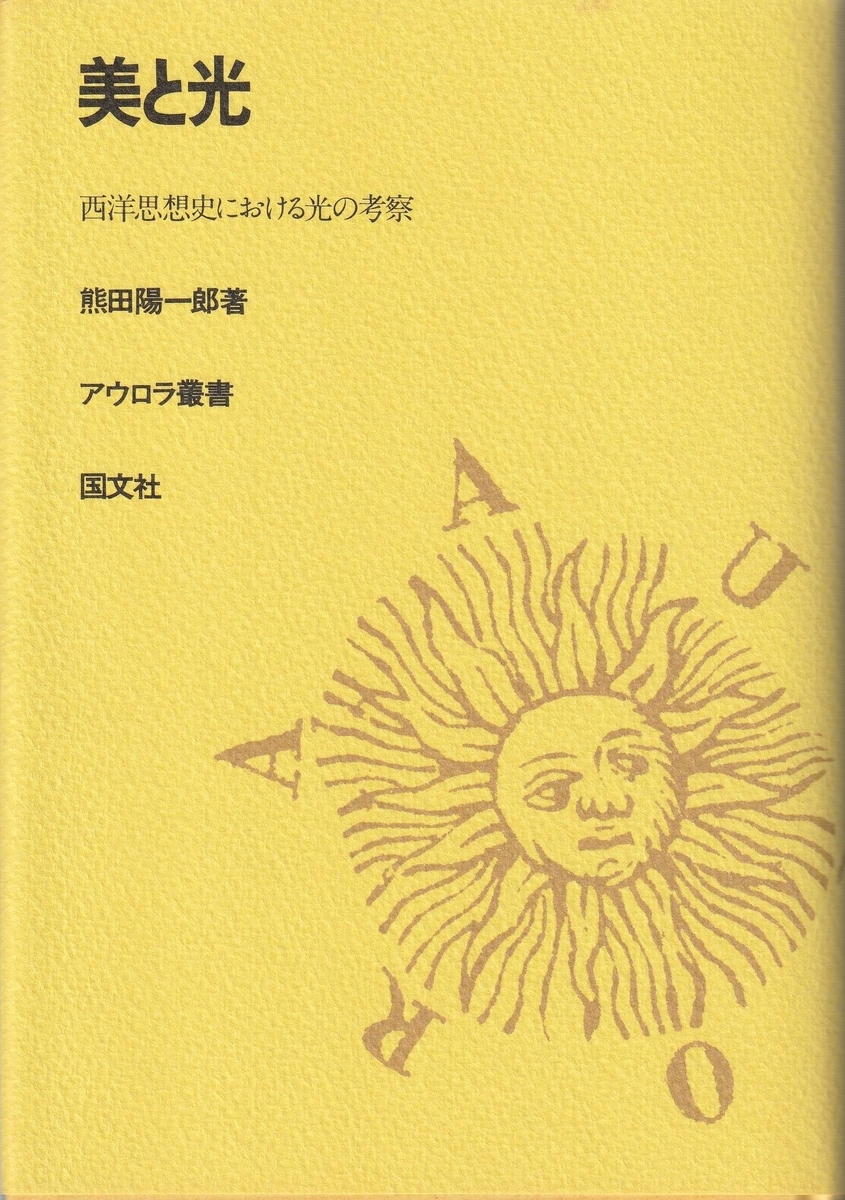
ヤフーオークションでは下記。
伊藤海彦放送劇集『吹いてくる記憶』(思潮社、66年3月、110円)
→500部限定うち337番
アンドルー・ラング生田耕作訳『書斎』(白水社、82年9月、440円)
「europe―MÉMOIRES IMAGINAIRES」(Europe et Messidor、84年6・7月、250円)
→知らない執筆者が多いなかで、Noël Devaulx, André Dhôtel, Pierre Fleutiauxらの名があったので。
PATRICK REUMAUX『L’honorable Monsieur DHÔTEL』(LA MANUFACTURE、84年第2四半期、750円)
→アンドレ・ドーテルをめぐっての随想