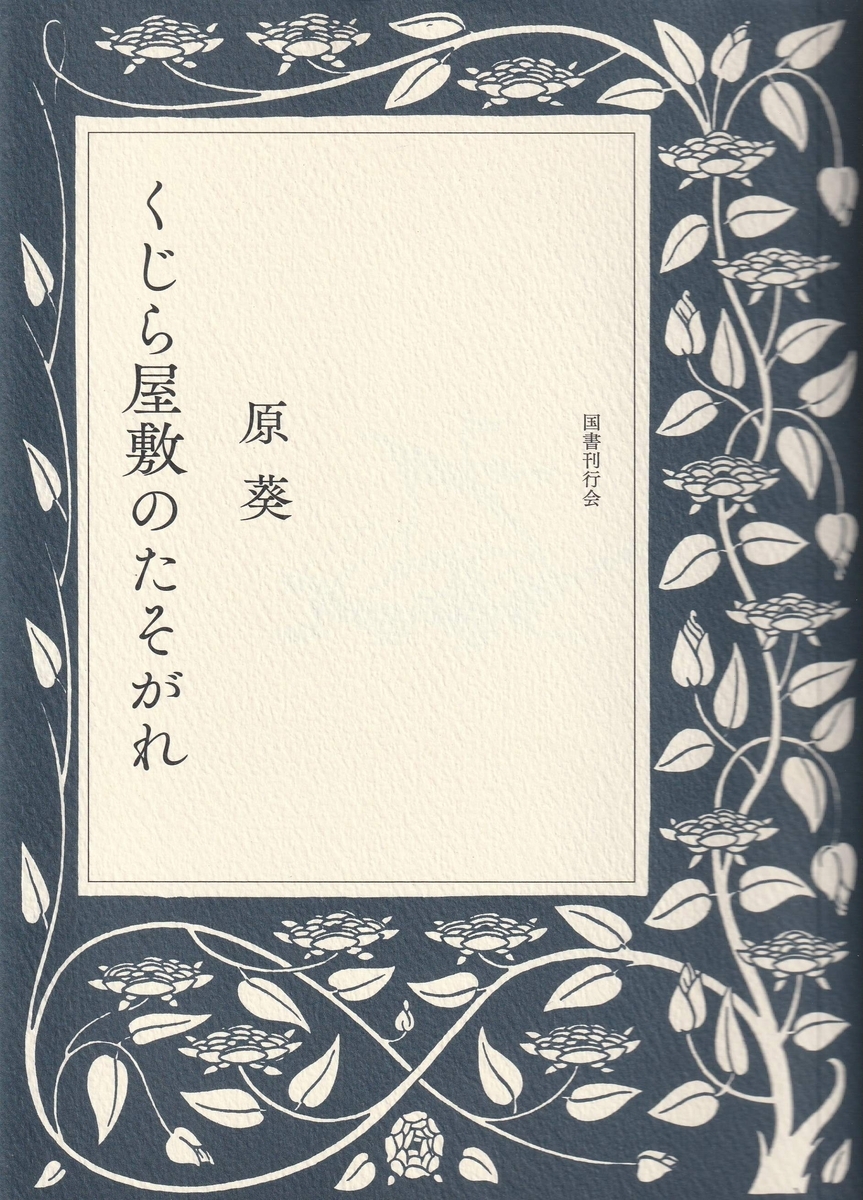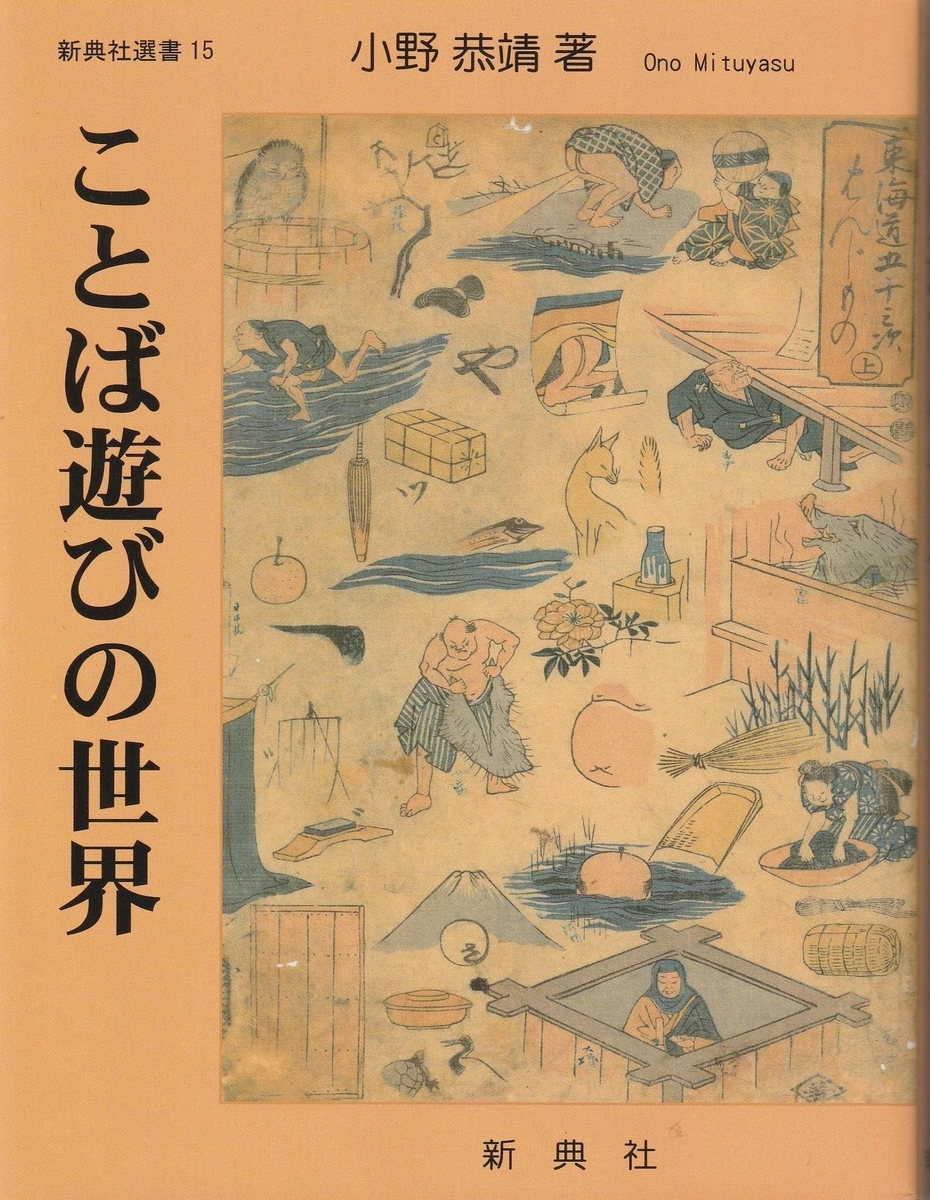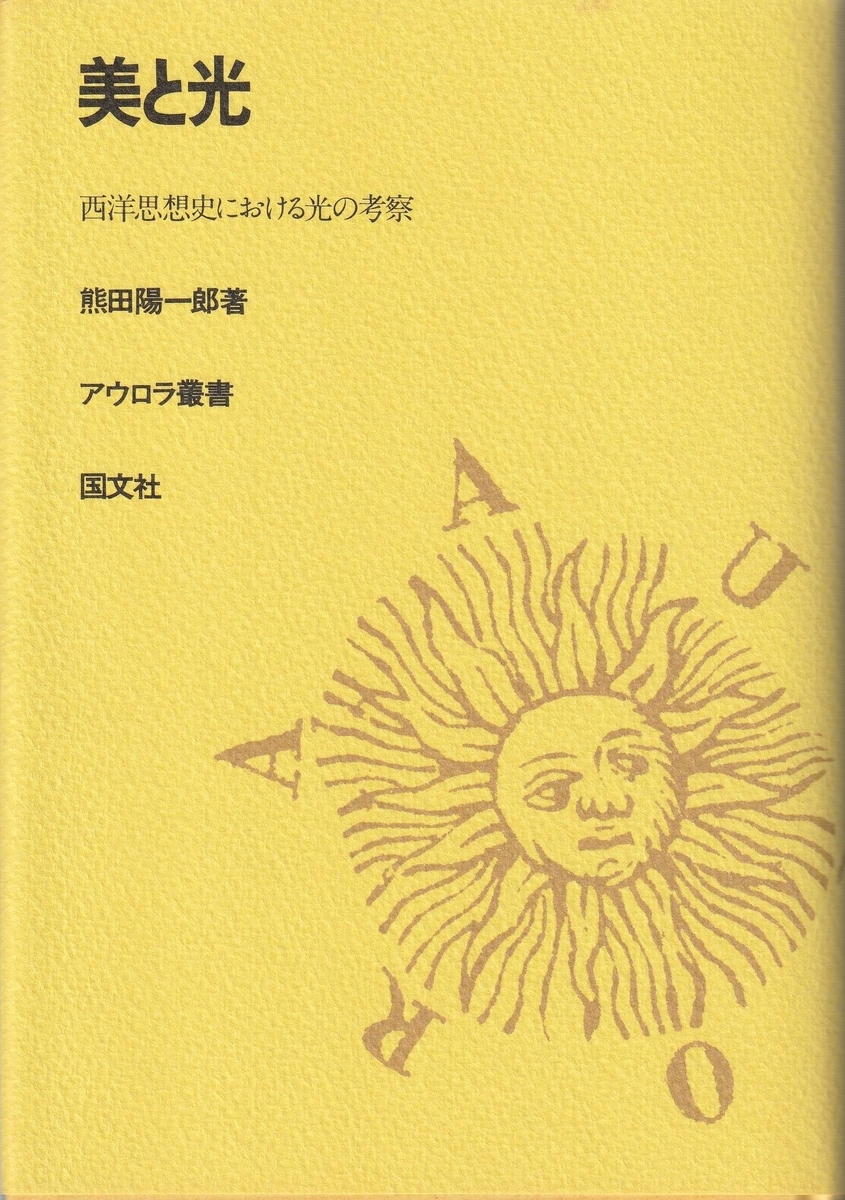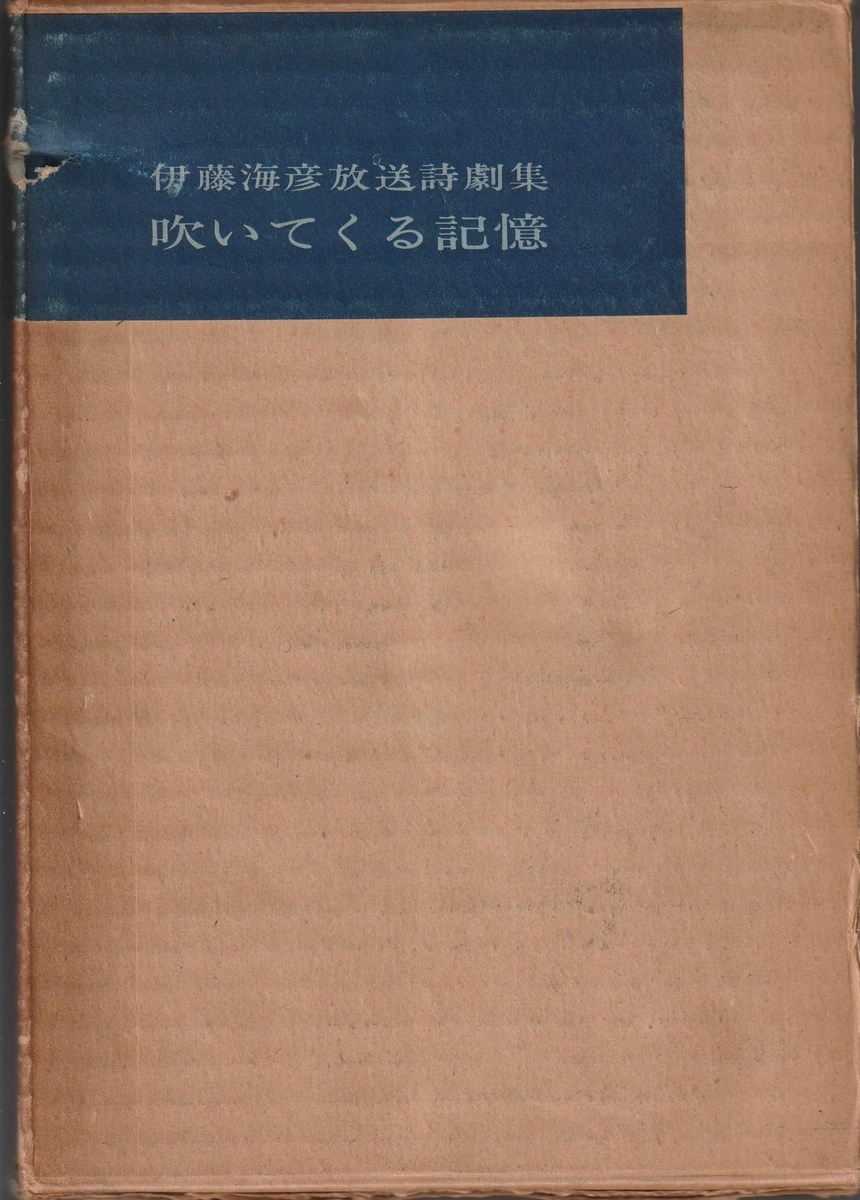Iwan Gilkin『Ténèbres』(Edmond Deman 1892年)のリプリント
5、6年前にこの本の原本初版がオークションで出品されていて、初めてこの詩人のことを知りました。そのとき、面白いと思ったので入札しましたが当然高値で落札できず、bookfinderで検索して、インドから取り寄せたリプリント本がこの本です。送料込みで1164円でした。フランス国立図書館のテキストサービス「Gallica」でも無料でデータの入手が可能です。
後で、Gilkinについて調べてみると、フランス語版のウィキペディアには出ていて、また所持しているフランス語の近代フランス詩アンソロジー(3冊)には、作品がいずれも数編ずつ掲載されていました。が、日本版のウィキペディアには情報がなく、所持している翻訳のアンソロジー(25冊)に当ってみましたら、かろうじて矢野峰人が『世界名詩選』(毎日新聞社刊)のなかでイーヴァン・ジルカンの名前で3篇訳しているのが見つかった程度です。堀口大學や、永井荷風、鈴木信太郎、大手拓次あたりがもっと訳していてもよさそうですが。ちなみに、この矢野峰人篇の『世界名詩選』には、シャルル・ヴァン・レルベルグ、グレゴアル・ル・ロア、アドルフ・レッテなどの珍しい詩も収められています。
過去の読書ノートを検索してみて、フィリップ・ジュリアン杉本秀太郎訳『世紀末の夢―象徴派芸術』のなかに引用されていることが分かり、さっそく本棚から抜き出してみると、読んだ時にはあまり印象に残らなかったのに、全部で8篇の詩が引用されていました。そのなかで、本詩集の作品が、「変容Ⅳ」(『世紀末の夢』p98)、「マギの苦悩」(p177)、「月の光」(p202)、「先駆者」(p300)、「メデューサ」(p304)、「魔術師」(p325)の6篇ありました。
ネットの記事によると、イヴァン・ジルキンは、1858年ブリュッセル生れ、1924年同市で没。カトリックのルーヴェン大学で法律を学んでいる時に、ヴェルハーレン、アルベール・ジローと知り合い、文学の道へ転身。ローデンバッハらとともに、「若きベルギー」を結成し、後にベルギーのアカデミー会員に選出される。数々の詩集、歴史に題材をとった戯曲のほか、オマル・ハイヤームの訳詩もある、とのこと。
本詩集には、全部で31篇の詩が収められ、4節からの短い詩もあれば、4部に分かれ8頁にもわたる長い詩もあります。私がぞくぞくとした感銘を受けたのは、「LA PENSÉE(思念)」、「ALADIN(アラジン)」、「LE POSSÉDÉ(憑かれた人)」、「LA BOUCHE(口)」、「MÉDUSE(メデューサ)」の5篇。次に気に入ったのは次の15篇。「LE MENSONGE(嘘)」、「LE LÉVRIER(犬)」、「CHEZ PUTIPHAR(ポティファルの家で)」、「CLAIR DE LUNE(月光)」、「LE JOUEUR DE COR(角笛吹き)」、「ARBRE DE JESSÉ(エッサイの樹)」、「LA DOULEUR DU MAGE(マギの苦悩)」、「REQUIESCAT(憩わんことを)」、「LA LYRE(竪琴)」、「ÉVOCATION(招魂)」、「SÉRÉNADE(セレナード)」、「TRANSFIGURATION(変容)」、「PRÉCURSEUR(先駆者)」、「LE SORCIER(魔術師)」、「ET ERITIS SICUT DII(そしてあなたは神になるだろう)」。
ウィキペディアでも、ボードレール、ロートレアモンの影響が指摘されていましたが、まさしく世紀末の雰囲気に満ちた詩群です。頽廃、官能、色彩、陰鬱、無気力、悪徳、夢幻・・・。『悪の華』のかなり強い影響があるような気がします。といってもフランス語でまともに読んだ詩集は『悪の華』ぐらいですが。ジャン・ロランの語彙にも近い。
私の理解の範囲ですが、詩に描かれている世界としては、キリスト教的な悪魔の誘惑との戦い(「LA DOULEUR DU MAGE」、「JETTATURA(邪眼)」、「LUCIFER(ルシファー)」)、悪の瘴気のたちこめるおぞましい世界(「SÉRÉNADE」、「MÉDUSE」、「LE SORCIER」)、老いて無気力な諦観の境地(「REQUIESCAT」、「LA PENSÉE」、「DIALOGUE(対話)」)、女主人に隷属する快感の世界(「LE LÉVRIER」、「LE POSSÉDÉ」)、若い裸体の群舞の風景(「PAYS DE RÊVE(夢の国)」、「ET ERITIS SICUT DII」)、月光・陽光の賛美(「CLAIR DE LUNE」、「LUMEN(光)」)、憧れの女性も肌が透きとおれば肉の塊と化すグロテスク(「TRANSFIGURATION」)、苦痛と死と快感の結合(「ARBRE DE JESSÉ」)、唇の赤と芳香の眩暈(「LA BOUCHE」)など。
さまざまな種類の動物の名が出てきました。蛸、白鳥、ノロ、青蛇、朱鷺、蝶々、仔羊、孔雀、火蛇、スフィンクス、鴉、夜啼き鳥、海月、白鳩、梟、狼、蛙、蝙蝠、ハチドリ。植物も、睡蓮、葡萄、菩提樹、グラジオラス、チューリップ、百合、薔薇、梨、杏、スグリ、李、木苺、薊、葦、牡丹、藤、ベラドンナ、海藻、山査子、林檎、毒茄、麻、マンドラゴラ、蔦、椰子、無花果、マンゴー。宝玉鉱物も、琺瑯、エメラルド、青真珠、ルビー、金、象牙、黒瑪瑙、黒檀、珊瑚、アクアマリン、トパーズ、サファイア、オパール、緑柱石、赤瑪瑙、金細工、ダイヤモンド、タンタル石、紫水晶、緑玉髄。色彩用語もたくさん出てきましたが書ききれないので略。豪華絢爛な詩の世界が理解できることと思います。
本来なら私のつたない訳詩をご披露すべきところですが、ジルキンの名を汚してはいけませんので、『世紀末の夢』の杉本秀太郎訳から、本詩集に収められている詩の一部を引用しておきます。
そして紺碧の、エメラルド色の、すばらしい孔雀が、/真珠色の青い尾長鳥が、そして朱色の紅鶴が、/あたり一面、痣のように、ルビーの散っている暑い露台に/しずかに歩いている、黄金の壷のあいだを縫いながら。(「マギの苦悩」)
月の光にまっ白い白鳥が/流れる羽根といっしょに/白い霧のなかを、褐色の水の上を/液状の舟のように滑る。(「月の光」)
みだらな眩暈を 一息に飲みなさい/怪物じみた性交の催淫剤を/乱行と 憎悪と/そして近親相姦的大暴行の血をお飲みなさい(「魔術師」)
何といっても、矢野峰人の古色の訳しぶりが最高です。本詩集掲載の作品ではありませんが、私の所持するフランス語版アンソロジーの二冊ともに収められていたので、たぶん代表作と思われる「LE MAUVAIS JARDINIER(惡しき園丁)」の訳詩の一部を引用しておきます。
怪奇の花匠ら、冬枯の園に来りて/人知れず忌まはしき種子(たね)蒔きゆけば、/茎たちまちに蠢めき出で、泥に塗れし、/泥沼の岸に絡みて、睡める蛇にも似たり。//その珍しく、大いなる恐ろしき花、/眩暈(めくるめ)くほどなやましき香気のなかに、/誇りがに、毒を含みて綻(ほころ)べば、/死は花の夷(えびす)めきたる美の中にあらはれ来(きた)る//(以下略)
今回は、ページ数が113頁と少なかったのに、読むのに難儀しました。ひとつは、この本に限った特殊なことですが、活字のsの字がʃのように細長くなってfと紛らわしく、読みにくかったこと。それからもっとも大きな原因は、やはり詩を読むことの難しさです。文章の主語、述語、修飾句が、時には転倒しながら、行またがり、あるいは節またがりとなって、文脈の理解を阻むからです。単語のもつ喚起力を頼りに、何とか雰囲気だけは味わえますが、詳細はよく分からないまま。再度出直して読む必要がありそうです。