
昨日の3月30日、新宿の朝カルで『揺れる大地』のこと話してきました。まだ、前回話したアンナ・マニャーニのことも書き終わっていないのですが、備忘のため、こちらを少し書き記しておきます。ヴィスコンティの映画を一本ずつとりあげる「その映画の背景にあるもの」のシリーズはこれでひと区切り。次回からは「ヴィスコンティをめぐる男たち」と題してお話しさせていただきます。
さて『揺れる大地』です。今回の個人的な発見(再発見?)は、ヴィスコンティが1941年に雑誌《Stile italiano nel cinema》に寄稿した「伝統と創造」(Tradizione ed invenzione)を読み直したことです。じつはこれ、数年前に書いたエッセイでも引用したものなのですが、今回ヴェルガの『マラヴォッリャの人々』を睨みながら読み直したところ、小さな間違いなどを見つけてしまったのです。そこで、今回新たに訳し直し、以下にアップしておきます。
その前に、ぼくの関心のありかを記しておきます。上記のエッセイでシチリアの映画を追いかけていたときのこと、トルナトーレの『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)に引用されたヴィスコンティの『揺れる大地』のことを考ました。冒頭のクレジットのあとに流れるイタリア語字幕を見て、パラダイス座の常連が首を傾げるシーンです。


この字幕を以下に挙げておきましょう。
I fatti rappresentati in questo film accadono in Italia e precisamente in Sicilia, nel paese di Acitrezza, che si trova sul Mare Ionio a poca distanza da Catania.
La storia che il film racconta è la stessa che nel mondo si rinnova da anni in tutti quei paesi dove uomini sfruttano altri uomini.
Le case, le strade, le barche, il mare, sono quelli di Acitrezza.
Tutti gli attori del film sono stati scelti tra gli abitanti del paese: pescatori, ragazze, braccianti, muratori, grossisti di pesce.
Essi non conoscono lingua diversa dal siciliano per esprimere ribellioni, dolori, speranze.
La lingua italiana non è in Sicilia la lingua dei poveri.
訳しておきます。
この映画に描かれる出来事は、イタリアはシチリア島の、正確にはカターニアから少し離れたところにある、イオニア海に面するアチトレッツァという村で起こります。
映画が語る物語は、世界中の人が他の人を搾取するような国のすべてにおいて、長年にわたり繰り返されているものと同じものです。
家々、通り、漁船、海はアチトレッツァのものです。
映画の俳優はすべて、漁師、少女、労働者、石工、魚の卸売業者など、この村の住民から選ばれました。
彼らが反抗したり、悲しんだり、希望を持つとき、それを表す言葉をシチリア語のほかに知りません。
イタリア語はシチリアで貧しい人々の言語ではないのです。
そんな字幕を前にして、パラダイス座の切符売りの男と常連の住民のふたりは、「なんて書いてあるんだ?」「さあね、俺は字が読めない」「お前もか」というやりとりを交わします。それでも、そのあとに聞こえてくるヴァラストロ家の漁師たちの会話には問題がありません。それはかなり強いシチリア語ですから、イタリア本当での上映ではよく意味がわからず、字幕がつけられたり、最後には吹き替え版もできたそうなのですが、トルナトーレの描くジャンカルドの街の人々には問題がないとわけです。ジャンカルドこれは架空の街で、実際には彼の生まれ故郷のバゲーリアだと考えられます。けれども、はたして彼らにとって、カターニア近郊のアーチトレッツァの漁民の言葉は問題なく理解できたのでしょうか。
この点について興味深い指摘があります。文学者のレオナルド・シャーシャ(1921 - 1989)は、「一体なぜ(ヴィスコンティは)当のシチリア人にとってさえ、部分的にはうまく理解することが難しいほどの俗語(vernacolo)を使うのか」と言うのです。シチリアのアグリジェント近郊の街に生まれたこの文学者でさえ部分的にはわからない言葉は、はたしてシチリア語と言えるのか。そもそも、『揺れる大地』の土台となったジュゼッペ・ヴェルガの小説『マラヴォッリャたち』(I Malavoglia, 1881)において漁民たちの言葉はみごとなイタリア語に書き換えられていて、イタリアの多くの人に理解可能なものになっているではないか。それを『揺れる大地』のヴィスコンティはわざわざ元の理解が難しい俗語に戻している。これは退行ではないか、というのです。
この点に関しては、みすず書房から出ている邦訳『マラヴォリヤ家の人々』(西本晃ニ訳)にも同じ問題があります。標準的イタリア語を、わざわざ日本語の田舎言葉や古語もどきに訳ているのです。例をあげておきましょう。第1章、「格言」を引用して話をするウントーニ親方(Padron 'Ntoni)の描写ですが、とりわけその「格言」の翻訳が、いかにも日本的な昔の格言に訳し直されています。もちろんこれは、あるていど仕方のないことかもしれません。
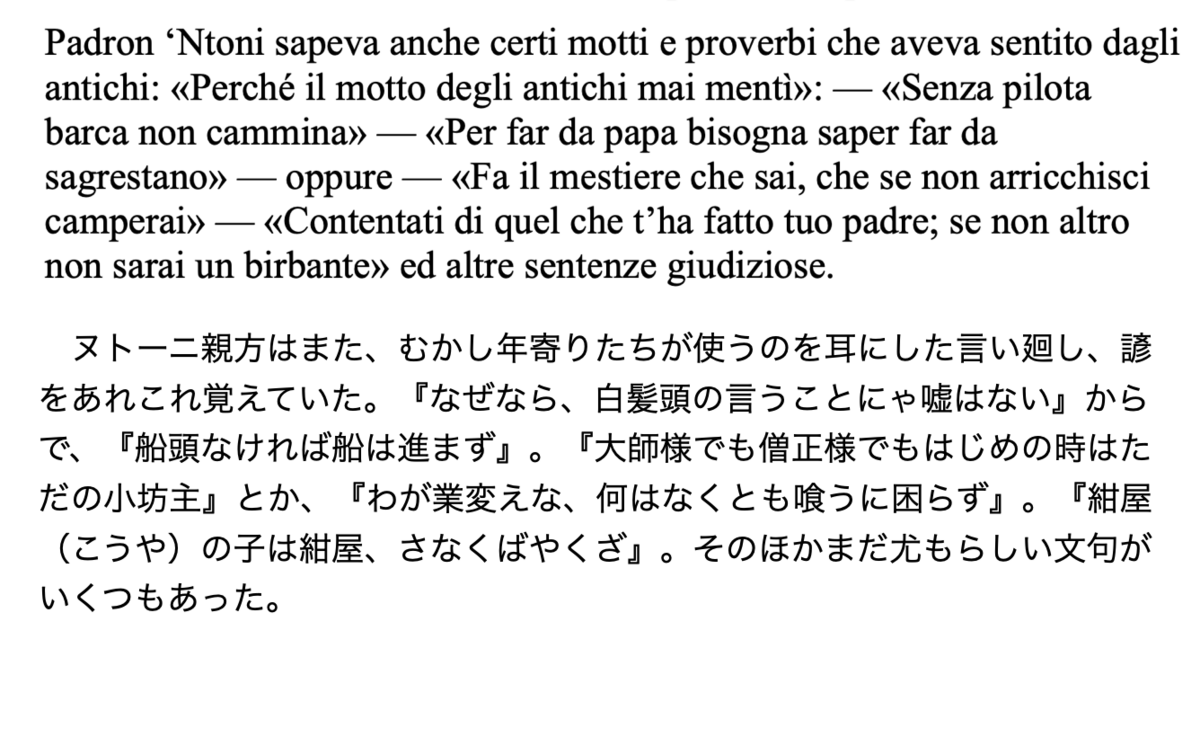
たとえば『わが業変えな、何はなくとも喰うに困らず』の部分です。ヴェルガの原文は«Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai.»。これをシチリアに伝わる言葉そのままに戻してみましょう。
シチリア語:
FA' L'ARTI CHI SAI, SI NUN ARRICCHISCI CAMPERAI.
イタリア語に直訳すれば:
FAI L'ARTE CHE CONOSCI, SE NON ARRICHIRAI CAMPERAI.
ヴェルガの表現では:
FA IL MESTIEERE CHE SAI, CHE SE NON ARRICHISCI CAMPERAI.
「知っている仕事をしなさい、儲からなくても生きてはいけるから」
すぐにわかるのは、ARTI / ARTE / MESTIRE という変化です。イタリア語の「ARTE」は「芸術」「技術」などのことですが、「仕事」という意味ではそれほど使われない。だからヴェルガははっきりと「MESTIERE」という単語を使っています。『マラヴォッリャたち』の仕事は漁師ですから、その仕事は ARTE より MESTIERE のほうがわかりやすい。たとえカターニアの漁民たちが「仕事」を「ARTI」と言っていようと、「MESTIERE」としたほうが通じる。漁民らしさ、方言らしさというのは、この格言の意味そのもの、そして格言を使って道理を通そうとする家長のウントーニ親方の態度で表現できているということなのでしょう。
くわえてタイトルの「I MARALOGLIA」(マラヴォッリャたち)という言葉。小説の冒頭できちんと説明されているのですが、じつは主人公たちの家族は「マラヴォッリャ家」というのではなく「トスカーノ家」。それがなぜ「マラヴォッリャ」(MALE - VOGLIA :やる気がない、なまけもの)と呼ばれるのか。じつはこれ、アーチトレッツァの漁村に特有の「反語」(antifrasi)なのです。実際は「誠実で真面目な海の男たち」(tutti buona e brava gente di mare )なのですが、それをそのまま言うと縁起が悪い。だからあえて真逆の「Malavoglia」(なる気のない奴ら)と呼ぶ。だから、このマラヴォッチャたちが乗っている船の名前が「ラ・プロッヴィデンツァ」(La Provvidenza)というがまずい。それは「幸運」という意味ですから、小説の中では一家にその逆の意味の「不幸」をもたらしてしまうことになります。
方言というのは、あるいは言語そのものは、その表現でなければ伝わらない肌触りがある。けれども、その肌触りを知らない人には伝わらない。伝わるように翻訳すると、肌触りが違うものになる。けれども、うまくやれば意味だけは保持できるかもしれない。だから「マラヴォッリャ」や「ラ・プロッヴィデンツァ」という反語や、「知っている仕事をするのがよい、金持ちになれなくとも生きてはゆける」のような格言は、その意味によってシチリアの一角にある小さな漁村のリアルを、普遍的な意味をもつものとして伝えることができるのではないでしょうか。
ではなぜヴィスコンティは、ヴェルガが苦労してイタリア語に書き換えて言葉を、もとの俗語に戻そうとしたのか。シャーシャにはそこが合点のゆかないところだった。けれど文学ではなく、映画による表現を追求するのなら音がとても大切な要素になります。それはある種の「肌触り」に通じ、ベンヤミンの「触覚的」のもの、つまり映画的なものに接近することになります。おそらく、ヴィスコンティはヴェルガの文学から入って、この触覚的なものを、視覚と音響によって再現したいと考えたのではないでしょうか。
そんなヴィスコンティの目覚めを、ぼくはその「伝統と創造」という文章に読み取れるように思います。これから映画を撮るるのだという決意、これまでにないような新しい表現として、まさにひとつの詩の作品としての映画を目指すのだという野心、そういうものを汲み取れるような気がするのです。ご笑覧。

伝統と創造
文学と映画の関係をめぐる最近の論争のなかで、わたしは自ずと、映画にとって「文学的な」着想に豊かな価値がある信じる人々に与することになった。告白すれば、わたし自身も映画の世界で活動を始めようとしており、映画をただ詩として理解したいという野心があるのだが、そんなわたしの前に立ちはだかる最も大きな壁は、映画原案の通常の作成作業がじつにしばしば凡庸(banalità)と、あえていうなら悲惨 (miseria)から成り立っていると思われることなのだ。あたりまえのことかもしれないが、わたしは何度も自問した。どうして文学には確固とした伝統があり、ロマンスや説話の何百もの形式において率直に純粋な人間の「真実」( verità)がその想像力のなかで実現されてきたのに、映画ときたら、本来なら人間の生のもっとも外面的な意味において、まさに記録の作成者( documentatore) でなければならないと思われるにもかかわらず、観客をささいな色恋沙汰やレトリカルなメロドラマに慣れ親しませるだけで満足している。これはいったいなぜなのか。しかもその結果、同じことを機械のように繰り返し、霊感や創造のもたらす冒険(il rischio dell'estro e dell'invenzione )から観客を遠ざけている有様ではないか。こうした状況にあって、映画の力を心底から信じる者は、自然とその眼差しをノスタルジーをもってヨーロッパの古典文学の大いなる叙述の伝統へと向け、そんな古典作品の数々を今日にあってはおそらくより真実の着想の源泉とみなすようになる。勇気を持って言えばよいのだ。文学のほうがより本物だと。たとえ「映画」には力がなく、あるいは純粋さを欠いているという私たちの主張が黙殺されようとも。
そんなことを考えながらわたしは、あるカターニア(シチリア)の通りを散策して、シロッコの吹く朝方のカルタジローネ平原へと向かっていた。そのときジョヴァンニ・ヴェルガに恋をした。
わたしは、ロンバルディア人の読者としてマンゾーニの想像力が持つ明澄な厳密さに慣れ親しんできたから、アーチ・トレッツァの漁師やマリネーオの牧夫が住む原初的で巨大な世界は、空想的で暴力的な叙事詩の文体のなかにそびえ立つものだった。そんなロンバルド人の目は、もちろん故郷の空も「晴れた時にはかくも美しい」ものだったが、ヴェルガのシチリアはほんとうにオデュッセウスの島に見えた。冒険と情熱の島、イオニア海の荒波に泰然として誇り高く立ち向かう島に思えたのだ。
こうしてわたしは「マラヴォリアの人々」の映画を撮ろうと思った。わたしはこの構想を、一時的な感動でその場限りの思いつきとして見限ることなく、なんとしてもその実現をめざそうと決めた。以来心の内奥から疑いの気持ちが湧いたり、慎重になるべきだとの忠告に動揺したり、どのくらいの困難があるかを考えて躊躇することがあっても、いつだって視覚的で造形的ななリアリティをあの英雄的な登場人物たちにに与える可能性を考えるときの興奮が勝った。なにしろ彼らの象徴の力ときたら、示唆的かつ容易に近づけないものでありながら、抽象的で堅苦しいよそよそしさを持つことがないのだ。さらに、わたしはこんなふうに考えて奮い立った。ごく普通の読者が最初にその表面に触れるだけでヴェルガの小説に可能性を感じて魅了されるのは、この小説の内的で音楽的なリズムによるものだ。だから「マラヴォリアの人々」を映画化する鍵はすべてそこある。映画化の鍵は、あのリズムの魔法を聞き直して捉えること、あの未知なるものへの微かな憧れや、あの「何かがおかしい」あるいは「もっとましであってしかるべき」という気づきを捉えることにある。リズムが、あの運命の数々の戯れの詩の実体なのだ。闇市場のウチワ豆をめぐる悲劇〔バスティアナッツォの死〕から、メーナを打ちのめす〔アルフィオ・モスカとの〕希望のない愛、ルーカの〔1966年のリッサの海戦での〕報われない死、そして最後に絶望して〔村を〕立ち去るウントーニの姿まで、運命は交差しながらも互いにぶつかることがない。
そんなリズムのおかげで、古代悲劇の宗教的で運命的な風格を持つことになるのは、卑賎な日常生活の出来事であり、明らかにろくでなしと社会のくずたちや大した意味もない出来事からできた物語であり、村の「三面記事」 の一編なのだが、それをファラッリョーニに打ち付ける波の単調な音と、ロッコ・スパトゥの無邪気で祝福された歌声が縁取ることになる。この男がいつも誰よりも早く1日を始めるのは、彼だけが運命に与えられた人生を、苦しまず、泣かず、汗も流さずに過ごす秘密をわきまえていたからだ。
不思議に思わないでいただきたい。わたしはこれから実現しようとする映画の可能性を語りながら、海鳴りやロッコ・スパトゥの声、そしてアルフィオが決して止まることなく引く荷車の響きのような、音の要素がとても大切だと訴えている。それには理由がある。もしもいつか「マラヴォリアの人々」を映画にする夢を実現するような幸運と実力に恵まれるときがきたら、わたしの試みをもっとも効果的に正当化してくれるものは、まちがいなく遠い昔わたしの魂を震わせてくれた幻想であるはずだ。おかげでわたしは確信した。観客のだれもにとっても、わたしにとってそうであったように、マラヴォリアのウントーニ親方、バスティアナッツォ、ラ・ロンガ、サンタ・アーガタ、《ラ・プロッヴィデンツァ》のような名前や、アーチ・トレッツァ、イル・カーポ・デイ・ムリーニ、イル・ロートロ、ラ・シャーラのような地名がただその名を響かせるだけで、なにか御伽話の魔法の舞台のようなものが開かれると、そこに言葉や身振りがわたしたち人間の隣人愛(la nostra umana carità)の本質的なことがらを宗教的に浮き彫にするに違いないと。ルキーノ・ヴィスコンティ
1942年2月28日、ミラノにて
イタリア語の原文はこちらを参照のこと。
alla-ricerca-di-luchino-visconti.com
この映画はAmazonプライムなどで簡単に鑑賞できるのですが、ぼくはブルーレイ版をおすすめします。全然違います。まったく違う映画を見るようです。それほど画質が向上しています。
日本語訳はこれ。原文と少し比較したのですが、さすがに意味はきちんと取れているので大変参考になります。日本語でよめる唯一のテキストとして貴重。ただ、いかんせん文体がシャーシャのいう意味で「退行」的。ヴェルガはアーチトレッツァの俗語表現を標準イタリア語としてわかりやすく錬成したわけですから、そこはやはり、わかりやすい現代語で訳し直してほしいところです。
こちらもブルーレイが出てるのですよね。
こっちは 4K UHD ですか。本物の映画がどんどん身近になってゆきますね。
![揺れる大地 デジタル修復版 [Blu-ray] 揺れる大地 デジタル修復版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61WiKDsKDlL._SL500_.jpg)
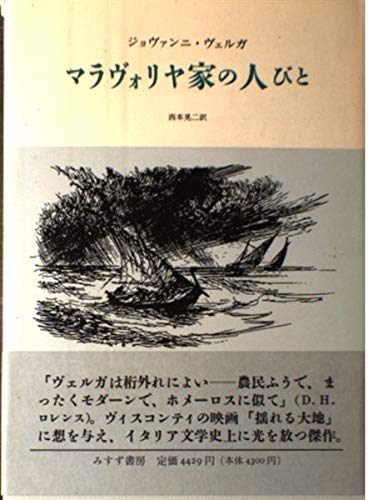



![郵便配達は二度ベルを鳴らす デジタル修復版 [Blu-ray] 郵便配達は二度ベルを鳴らす デジタル修復版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/517qmbutSvL._SL500_.jpg)
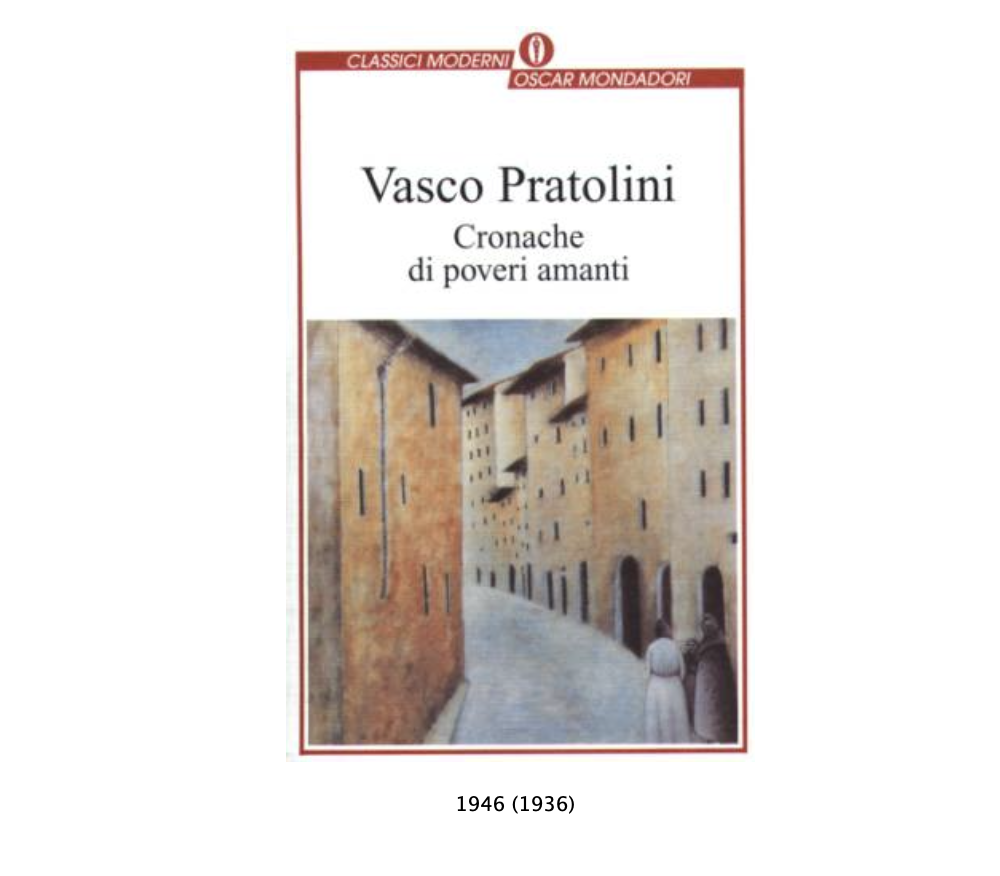

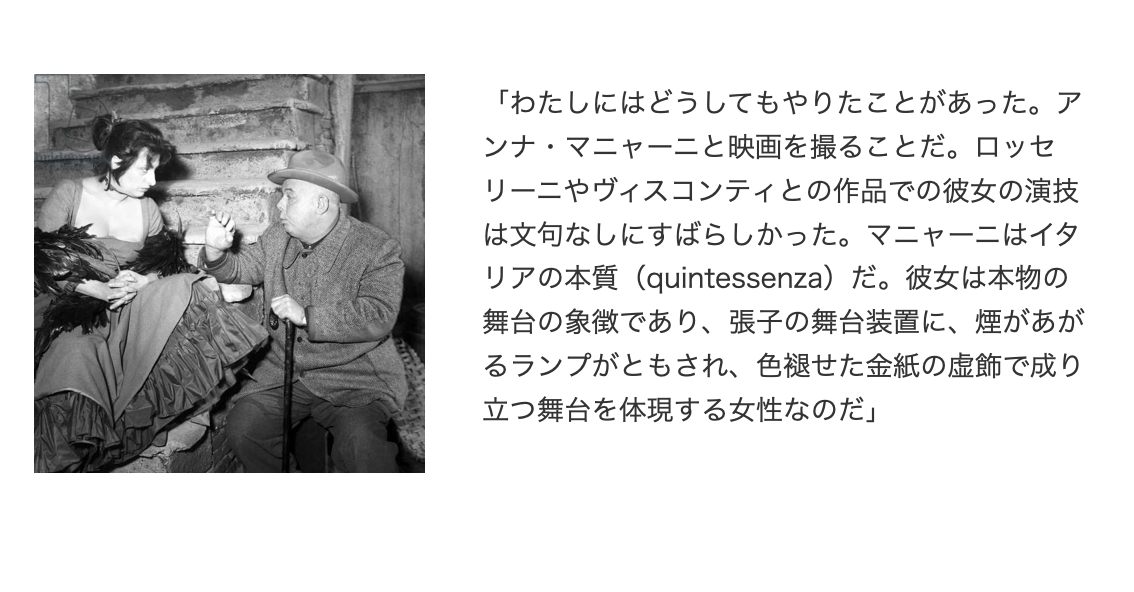 そんななか、
そんななか、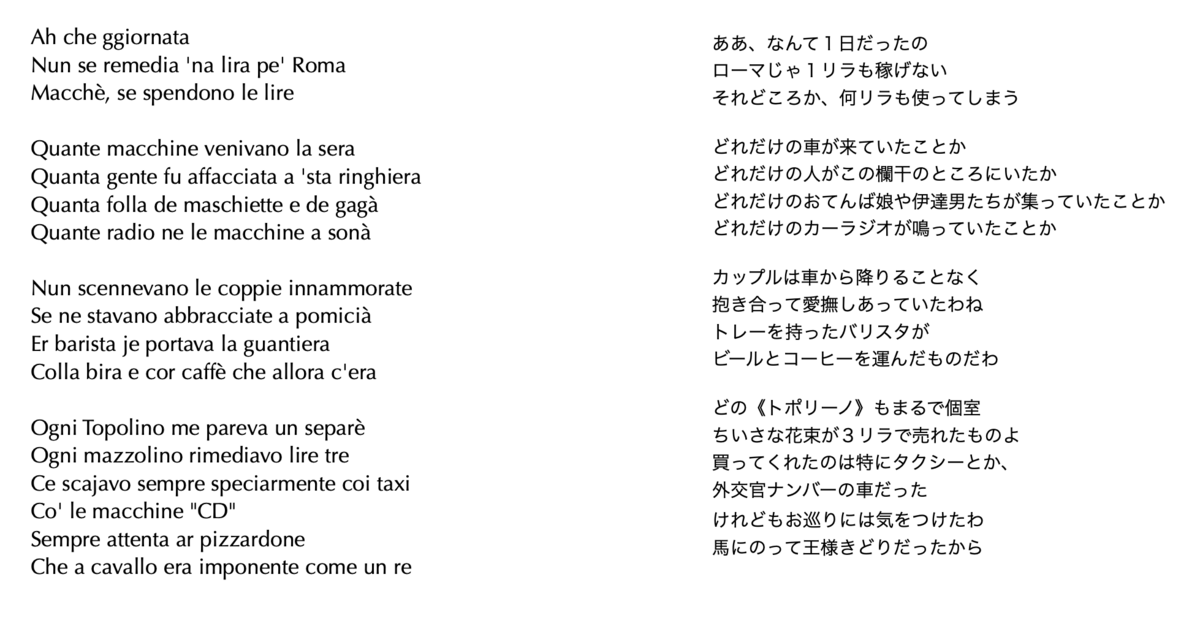
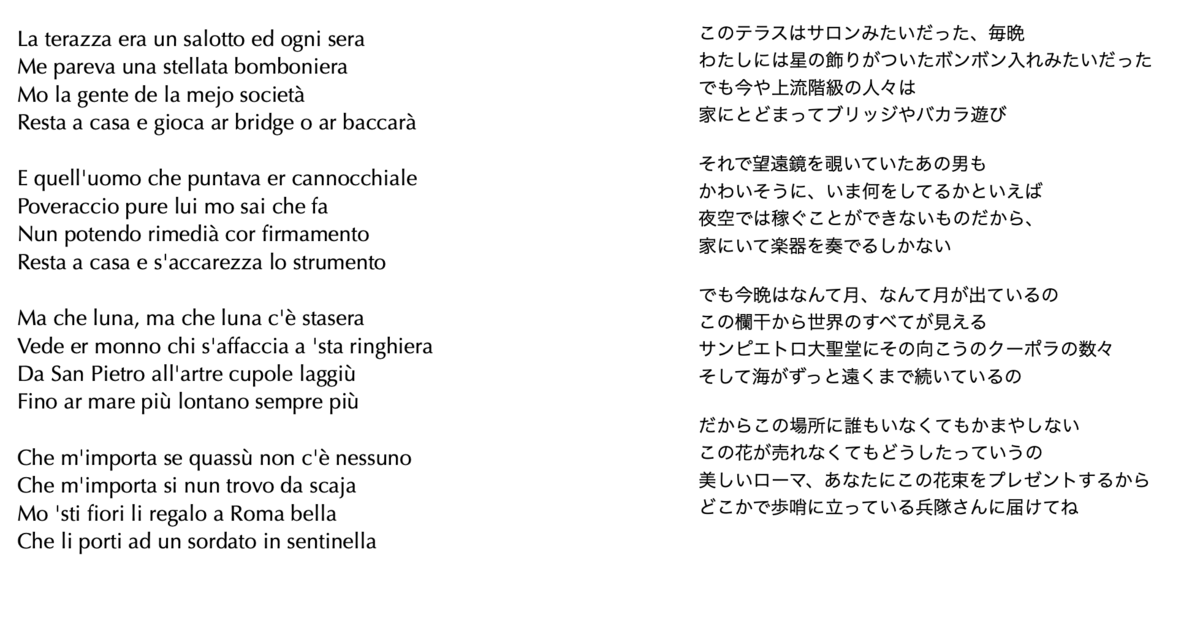 6)象徴としてのマニャーニの叫び
6)象徴としてのマニャーニの叫び
