柴崎友香『ビリジアン』について(質問応答7/25)
以下に。https://t.co/2h72QAYNJx....
— (∵`)<hiroki_yamamoto (@hiroki_yamamoto) 2021年7月25日
続き→https://t.co/F1bmZZ8ypi#マシュマロを投げ合おう pic.twitter.com/7SbgxHFcdg
また、当時、『ビリジアン』についてざっくりとですが書いたものが、Dropboxのなかに保存されていました。
けっこう恥ずかしい感じですが、以下に、そのまま載せます。今ならたぶんもうちょっとうまく言えると思いますが……(柴崎さんについては、あらためて『ビリジアン』を読み返しつつ、最近の作品も含めて論じる機会があったらいいな、と感じています)
※あと、ぼくがむかし編集を担当させていただいた、古谷利裕「わたし・小説・フィクション 『ビリジアン』と、いくつかの「わたし」たち」も、『ビリジアン』を扱ったものとして面白いと思います。http://www.bungaku.net/wasebun/magazine/wasebun2017es.html
=======================
柴崎友香は、短篇集『ビリジアン』のなかで、文末が「~た」となる短い文章を連続して使いながら、過去のいっときを描写する。それは、「~た」が過去の時制を持つことを上手く使い、「~た」で終わる文を多用することによって、過去を何重にもつなげること、さらには今の多重性を含んだ文章群を書き連ねていく表現方法である。
小説では、一般的に過去形を用いることが多いが、それが日常的な意味での過去をそのままに表現することは少ない。なぜなら、小説というものは、あくまで「語られた」ものであり、今その場で「体験されている」ものではないからである。もちろん、現在形や未来形で語られる小説もある。だが、それは「小説とは過去形である」事実の内側からその転覆を謀ったもの、もしくは「書かれる世界においての一般的事実を書き示す」ために用いられたものである。たとえばSF小説で設定を提示する際、その文体は現在形で書かれることになる。
柴崎友香の短編「赤の赤」では、センター試験を受けた日を、そのときの「わたし」の視点で描く。しかし、これには絶えず、「その日を思い出す未来(現在)のわたし」という視点も背景にあり続ける。
教室の前では、ストーブが燃えていた。水色のホースを通ってきたガスが燃え、円柱状の網を赤く焦がしていた。わたしたちの学校よりもひと回り広い教室では、一組の机と椅子に一人ずつが座り、一人が一本の鉛筆を握って、マークシートを塗りつぶしていた。
あとに続く設問自体は簡単だった。哲学者の名前や時代や用語を選び、その数字に対応したところを塗り潰すだけだった。覚えていることばかりだった。
クリスマスから大晦日の前の日まで、わたしは学校に行って、「倫理・政経」というめったに選択する人がいない科目のために梨田先生の補習を受けた。生徒はわたし一人だった。一日目は、眠たかった。一人しかいないので、寝てはいけないと思った。梨田先生が、
「今眠たいやろ、しんどいやろ、帰りたいやろ」
と言ったので、自分が眠っていたことを知った。昨夜家族を救急車で病院に連れて行ったので寝るのが遅くなったんです、と言ったけれど、梨田先生は、
「理由はわかったけど、それは今やらなあかんこととは関係ない」
と言った。そういうことを言う人はおもしろいと思って、わたしは補習を受けたに違いなかった。
あの教室にあったストーブと、この教室にあるストーブは同じだった。同じ色で燃えていて、離れると全然熱くなかった。
マークシートを塗るのは好きだった。くじ引きみたいだと思っていた。問題文をもう一度読んだ。もう涙で滲んだりはしなかった。だけど、善く生きるためにはどうすればいいか、考えなければならなかった。
この短い箇所だけでも、大まかに分けて三つのわたしが存在している。
- 教室でセンター試験を受けているわたし
- 数ヶ月前、学校で補習を受けていたわたし
- それらを思い出している未来(現在)のわたし
基本的には、①の時間の推移が、小説内の現在として、時間は進行する。だが、それによって、本来思い出されているはずの(過去形で表現されているはずの)①のわたしが、さらに過去を思い出してしまう。「あの教室にあったストーブと、この教室にあるストーブは同じだった。」というとき、「この」という言葉遣いからしても、センター試験を受けているわたしは現在の時間を担っており、センター試験を受けている日の時間の経過を体験しているが、しかし次の瞬間、「マークシートを塗るのは好きだった。くじ引きみたいだと思っていた。」という、「センター試験を受けていた日のわたしを思い出すわたし」が出現する。特に「マークシートを塗るのは好きだった。」という文章では、センター試験を受けていた時の過去だけでなく、その周辺の、つまり高校生のころの自分という、非常に広い範囲の過去を扱っている。このとき、センター試験を受けているわたしは、未来のわたしを通過することによって、なかば習慣化された幅の広いわたしのなかの一点として、現在でありながら回想の渦に巻き込まれてしまっているのである。
この激しい記憶の運動は、小説という形態を用いて過去を思い出そうとする際に露出するものだ。小説における現在とは、過去形ではなく、読み手に親しみの持てる時間の、その常駐性にあらわれる。それをよく示しているのが、次の箇所である。
門の前からバスに乗った。どんどん建物が低くなり建物の間隔が広くなって、行き先の違うバスに乗ったことに気づいた、途中で降りた。もう真っ暗だった。空に赤はなくて、住宅地の端の崖の下に街の明かりが見えた。青白い光だった。
駅に着くと、伝言板にわたしの名前が書いてあった。そのあとにもなにか書いてあった。緑色の板に白いチョークで。だけどなんて書いてあったか、どうしても思い出せない。覚えているのは、改札を通るときに一人で笑っていたことだけだ。
「駅に着くと、伝言板にわたしの名前が書いてあった。そのあとにもなにか書いてあった。緑色の板に白いチョークで。」という文章は、過去形でありながら現在である。先ほどの区分で言うと、①のわたしである。しかし、次の文章「だけどなんて書いてあったか、どうしても思い出せない。覚えているのは、改札を通るときに一人で笑っていたことだけだ。」は、この小説には珍しく、現在形で書かれている。この文章のわたしは、③だろう。①のわたしを、③のわたしが思い出そうとして、うまく思い出せない。①は、現在に進行するわたしのようでいて、実際は過ぎ去った(失われた)過去のわたしであることを、小説が思い出す。③のわたしが現在形によって書かれなければならないというわけではなく、①のわたしを現在とする視点から距離を置こうとした語り手のわたしの認知が、文体の時制の変化を生んだ結果、現在形があらわれただけなのである。
こういった、巧みな時制の変化によって、柴崎友香はこの短編の末尾に、以下の様な描写を行う。
電車が止まると、ホームには中学の制服を着たわたしが立っていた。荷物はなにも持っていなくて、ドアが開くと真っ先に電車に乗り込んだ。
電車を降りたわたしが振り返ると、中学の制服を着たわたしがジャニスの横でドアの前に立っているのが見えた。中学の制服を着たわたしは、ジャニスのほうをちらっと見たけれど、ジャニスはまた目を閉じて今度はほんとうに眠ってしまったみたいだった。
わたしは長い階段を降りて改札を抜け、青信号が点滅している横断歩道を走った。
センター試験を受けた日のわたしは、中学生のわたしを見てしまう。これは、先ほどまでのわたしとは種類が大きく異なっている。
現在のわたし(③)が思い出している過去のわたし(①)は失われたわたしであるにもかかわらず推測などではなく、まるで現在のようなはっきりとしたわたしの像を含んでいる。その①のわたしが、中学生のわたしを見る。現在のわたしがもしも、中学生のわたしを思い出したとすれば、そのとき用いられる過去形での表現では、あくまで「思い出しうるわたし」もしくは「思い出しているかいないか曖昧なわたし」となってしまうだろう。小説における過去形は、現在の性質をおびてしまう。
過去のわたしがさらにその過去のわたしを「思い出す」のではなく「見る」という事態は、センター試験を受けた日を書くことによって体験しなおす中で、そのときのわたしを書き換えてしまうことにもなっている。当然のことだが、過去のわたしを「見る」ということは、現実としては考えられないだろう。
しかし、過去のなかのわたしの記憶を再現しているなかではどうか。見間違いなどで強い断定をもって過去を書き換えることはありうる。(さっき見たのはなんだったんだろう、もしかしたら幽霊だったのかもしれない……など)。
この箇所での中学生のわたしは、「~た」を多用することによって、小説における過去形の特徴を過剰に増幅し、その結果、現在ではありえない(もし出現してしまうとしたら、それは回想の形をとってしまう、つまり現在としてのわたしに取りこまれてしまう)わたしを、喪失した過去のままで再現するという、小説を通してでしか不可能な回想方法に行きついたものとして考えられるのである。
レイアウト、平倉圭ダンス=思考講座 第二回、とか(日記)
河野聡子さんの詩集をデザインした時から、デザインとテクストがどう絡みうるのかというのを悩んでいたというか、特徴的デザインを随時やるならそれはテクストに対して少なくとも自らが感じる運動を最大限表現するものでなければならないのではないかしかしそれはなんなのかと悩んでいたのところがいくらかあったのだけれども、しばらくして、そもそも問題設定がそれはまちがいで、デザインがテクストの運動と一対一対応するというかテクストをデザインが翻訳・代表しうると考えること自体がばかなことで、あくまでテクストとデザインは切断していて、しかし切断していながらも様々な物理的要請を介して異なる二つの制作者同士として関係している、という状態である、目指すべきはその拮抗状態の沸騰である、と思うようになった、
その意味で?、視覚詩の営みはダイレクトでデザインにつながるわけではなく、より抽象的というか大枠レベルでの「レイアウトの思想」としてデザインと関係する、または活字の処理という極めて細部の具体性の問題として関係する、と思う。そこを間違うと、視覚詩における活字の配置とテクストデザインにおける配置をダイレクトで結びつけすぎることになると思う(しかしそれを考えていったら、タイポグラフィになっていく、それはテクスト制作者をデザイナーがただただ侵食代弁していくだけだ、というか。目指すべきは代弁ではなく共同制作の環境づくりであり……という)
エディトリアルデザインとタイポグラフィは実作レベルではだいぶ違うんじゃない?、というか、だからこそ、行き交うところを考えていくとより大きな思想レベルの問題にいっておもしろい、のだけれど
2018.2.22
平倉圭ダンス=思考講座
第二回「異鳴の技法」
SCOOL
各々の身体に依拠した魂らを身体の周囲の環境にまで広がるものとして考える、ことで魂同士が異種のままに環境において関係する(それは単一平面に収束する翻訳関係の発生とは異なる)を
意味の過剰(異種同士では物質的接触だけに収束できない、そこに意味が見出されてしまう 逆に言えば私とは異なる魂、意味、が、本来そこにないはずのものでも開いてしまう、そのように私は私を向こう側に投げ出さずにいられない)、身体の大小(ありんこと人間では、物質的接触がそもそもうまくできない、相手があっさり死んでしまう遊びは遊びでない)、物理的環境の共有不可能性(過去の私と遊ぶ、死者と遊ぶ、遠く離れたものと遊ぶ、生息環境が違いすぎて同居できないもの同士で遊ぶ、ことがうまくできない)
を乗り越えるものとして、「環境」という概念そのものを再定義することにつながる、ように、考えていく、先で……
魂を外に見出してしまうことと、私というものの同一性の分散化(かつての私と、先々の私の、あいだの距離がまとわりつくところとしての、この身体)とを、ともに素材としつつ、所与の時空間の近接性も身体の物理的スケールの近接性も欠けたいくつかのものら(私と私、私と死者、虚構と現実、ありんこと人間)を隔てたまま隣り合わせそれ以前にはなかったノイズを生じさせる「新たな環境(新たな近接関係=距離をもたらすもの)」を作る、ということを問う。
というのが、私にとって、「私のレイアウト」であり、「新たな距離」であった。それはかつてテクストとかエクリチュールとかいう言葉で考えられてきたこと、を引き継ぎつつそこに具体的な身体、隔たり、私が私であらざるを得ないことの呪い、を食い込ませつつ共同性へ開いていくことでもあった(一側面で)(急にエクリチュールとか言い始めてるようなのは、いまやってる仕事に関係するのだけれども まあもうたびたびいっているように 紙面の奥でも表面でもなく手前で共に、しかし紙面を用いて思考するには、という考え方がいつからかずっとある 別時空間から画面を通じで手前まで出てきてくれる貞子)
ちょうどいぬのせなか座を立ち上げ、しばらくして1号、2号、を刊行する前後には、平倉さんのblanClassでのセッションを受けていたのも関係し、私において、言語表現を行うこと、私について考えること、自他の死について考えること、を、異種の問題として考える傾向が強められたという側面が確実にあった(これが想像以上に大きかったことをただただ確認する)。
というか、言語表現を行うこと、にどこまで(「文学」などでは決してない)生々しさをもたらせるか、というかもたらすというより生々しいレベルで酷使できるか、が問題であった。そして同時に私は常に、この世界において起こり得た事態を記述するというよりは、制作が次の瞬間どこに向かうべきか、どんな技術を身に積もらせるべきか、にどちらかというと重きをおいて考えずにはいられず、所与と言うよりは事後的に(ダンスが生じるための)環境を作る可能性、あるいはそもそもそのような環境の制作に、(この私が技術を蓄積してしまったところの)言語表現が、デザインが、寄与しうるのかという問題を考えずにはいられず、大江論、2号の座談会テキスト、あるいはその後のパフォーマンスを作っていた。
結局それは、言語表現を、(身体の特異な反応をもたらすような)環境の埋め込みと掛け合わせのための技術として用いるという考え方と、私という現象(あるいは書き直しの要因となるもの)の紙面上での配置関係、が織り込まれたようなところに行き、即興や共同制作の問題へかなりダイレクトにつながっていっていたのだけれども、そこらへんで昨年後半あたりから考えることの時間が取れず結構止まってしまっている。
言語表現がいかに生々しいものとなるか、というとき、例えば2号で扱った、正岡子規をめぐる大江のテキストなどは、言語表現を基点とするものとしては歓喜しそうなものだが――限られた身体、限られた環境、しかしそこでの制作が私の総体、他との関係の総体を記述しうる――その危うさを強烈に感じるところもどこかあり(そんな楽天的でいいのか、可能性を信じていいのか、と……)また同時にそれ以外のやりようもまた自分の中にどこか確実に生まれつつある気がしつつ……なのだった。やはりそこらへんを、ぐっとすすめるテクストを書きたい、荒川ギンズ論がそれになるのかはわからん、土台として必要だが求めているものはもっと雑多になる気がする(あるいは荒川ギンズ論をひたすら雑多なものとして書く、という気も当然捨てられず 書き方の問題)。
総じて聴きやすく、わかりやすく、しかし平倉さんの話をたびたび聞いてきたからかと思ったけれどもhさんも今回はとてもわかりやすかったそうで(前回は難しかった、と)、なおのこと先が知りたいと思い、自らも悩み悩む。
あと、ここ最近捕食関係という言葉をよく耳にするがそれについて、その恐怖は(一部を除き)あくまで一形式にすぎないと私は考えがちで、というのも恐怖といえばやはりジャパニーズホラーという感じなのだが(私は)、あのあたりのホラーのよさは、相手が私を食うことで終わるとは決して思えない、つまり死を受け入れたらそれで終わるものではない苦痛が相手によって与えられうるという事態への恐れであるからで、とはいえ平倉さんの話では最後にくねくねが出てきた、そう、そのような異様な、私とは違うものと、環境を共有した結果、死よりも恐ろしいかもしれないなにかが、予感として開かれるということこそが、異種の極致だろうと感じる。そしてそれを予感として感じることとはどういうことか、が、レイアウトを何らかの形で確定させるものではないか、とも。
あと、やっぱり先日の座談会の続きというか、パフォーマンスとしての座談会をよりいろいろなかたちでやってみたいな、と思った 先日は演劇的要素が強かったけれども、よりレクチャーよりで、やってみたい。が、単一の魅力ある人間による語り、思考の開示、ではない、複数人の集まりの、ゆるやかかつノイズまみれの対話を、だれが見たいだろう?という気も、たいへん、する。それはそこに身を投じてみようと思わせられるかどうかであり、共同制作という苦痛を払ってでも、という姿勢の設計であり、それこそ予感の作成であり、また理解の形式であり……
(しかし場はいくらか恵まれているしプランもいくらかあるが、時間がただただないのだった、
福留麻里×村社祐太朗「隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで」
福留麻里×村社祐太朗「隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで」
伊藤亜紗さんとのアフタートーク含め、全体的にやはりとてもおもしろかった(読まれるテキストと微細な体の動き、照明のあり方、切断され並べられる時間、記述される細やかな物たち、は、全体として、どこか金井美恵子を思い出すような「雰囲気」を作っていて……)また言語表現に軸足を置きつつ身体表現も考えざるを得ない自分というところからも、とても共感するところが多いのだけれど、外枠の部分で、以前見た新聞家「白む」と同様に、若干の違和感があった。
この作品(制作)で目指されているところのものは、テキストといくつかの身体が関係していく中で生じる、テキスト把握の質の強化や、そこに食い込む身体と思考の間のノイズ、フィクショナルな環境や私の掛け合わせの生成、テキストからもいくつかの身体からも匂い立つところの共同性の検分・拡張がたとえばあると思うのだけど、それを徹底する上で、意見交換の場を設けるとかだけでなく、(日本語)テキストの配布、理論構築とその提示、が鑑賞の手前においてかなり必要なんじゃないかと思う。それは、よりわかりやすくしろとかって話というよりは、テキスト・理論配布がなされ共有されたあとに何人もが見る「テキストを読む身体とそれが立つところの舞台」こそが、この作品≒実験の核を明確にあらわし、作品の制作もまた十全に加速させられると思うから。
テキスト制作者とそのテキストを発話しつつ舞台に立つ者が、対話しながら一つのテキストに精緻に向き合いつつ、身体がテキストにおける文章配置=レイアウトを必然化しているところの論理(ありふれた言葉が、そこにおいては多重的なノイズを発してしまうような論理)を、経験の質として確保し、それが身体に(やはり行為のレイアウトとして)生じさせる微細な運動(それはなかなか客観的には計算できず、通常の人間には「私」や「内面」や「魂」として縮減理解され、その身体以外では再現もなかなか難しい)をそのようなテキストにおけるレイアウトの論理の翻訳されたものとして組み立てていく、というところが、ひとつ大きな「見所」としてあるだろうし、そこに対話や「(観客への)聞かせ」を通じた共同制作的側面が生じているところも重要だろう(演劇という表現方法に馴染み深い利点でもあるし、意見交換の場を設けることを重視するところもその延長といえる)。
舞台に立つものがテキスト制作者に言葉による意味の理解(その確定)を強いられるのは、この作品≒実験(と私は呼ぶ)が核とするところのものか、個々の言葉(書き記された文字)が持つ多様性を作るというよりは(それはもう事前に社会において一定程度作られている)、意味の多様性が生じる場自体の多様性を目指すからだろう。つまりそれは環境と、身体、その狭間で観測される(それ自体観測位置としての)私を、制作するということでもある。ゆえに、私の発見という意味でも、私らが共存する環境(ら)の(多重的)構築という意味でも、共同性は欠かせない。
ただそうであるなら、テキストを書く人間が(主に)ひとりであること、それを「わかる」状態をもたらすのが(なかば教師的な立ち位置が)「単一の」テキスト制作者(村社さん)とされる構造をとることは大きな不安材料としてあるだろうし――それはもちろん「実際はそうではない、より複数的である」と言いうるところではあるし、単一制作者が常に障害となるわけではないのて微妙ではある(特にテキストは複数人の制作者をおくことが途端に死人が出そうになるほど厳しい制作環境をもたらすことはやってみればわかる)――それより重要なのは、舞台に立つ者とテキスト制作者の外に、そこで生じる身体のノイズやそれに伴う言語表現の背景としての私や環境の多重性をめぐる実践が、理論とケースともに開かれ、その開かれた思考の参照項として上演が成立するようにすべきではないか、ということだろう。つまり、テキストをもとに試行錯誤している稽古場での実践、そこにおける質こそが、作品として提示されるべきではないか、と……意見交換の場を設けるよりも、テキストを配布し、背景にある理論をしっかり論考としてまとめ提示することが、この演劇形式においては、より前進を加速する手だと思う――でないと、舞台に上がる身体はとても充実した発見を得られる過程として制作が把握されるだろうけれども、観客を巻き込むという観点からいえば、どこまでいっても現状は、なんとなくわかった気になる人を増やすか、つまらんと罵倒する人を増やすか、漠然と話を聞いてなにも感じずおわるだけの者を増やすか、にしかならないのではないか――この上演がそれだけでないのは当然だが、共同体の成立としても実践のあり方としても、テキスト配布+理論形成提示を伴った方が、ずっと徹底されたものとしてありうるのではないか……というかぼくだったらさらにそこでテキストへの書き込みや、身体における上演を通してなされたテキストの書き直しの過程を、きちんと残し、それすらも提示する気がする。それが、目の前に立つ身体を見る目の解像度を上げることに繋がるだろうし、作品制作を通してなされた成果(ある種、身体とテキストに生じた変異や技術)を、実際に制作に立ち会った数人だけでなく、もっと広いところへ開けたかたちで「使う」ことにつながるんじゃないか、と……)。
あと、やっぱり、変な話だけれど、アフタートークで言われていたことの多くが言語表現の話そのものすぎて……たとえば一秒前の私と一秒後の私を同じ私とおかない、という考え方は、言語表現をやっている人間なら、一文ごとに生じる語り手と書き手の激しい運動ならびにそれらのレイアウトを通して、必然的に思考させられるところのものとして馴染み深いだろうし、同時に、ダンスはもちろん、多くの表現方法に生なまま適応可能なところでもあり、それは言語表現が他ジャンルに開けていく上で大きなポイントとなるところだろう(と、少なくともいぬのせなか座ではずっと言っている。「私が私であること」、その素材化、「私のレイアウト」)。
それを、いったん演劇における台本ではなく、あくまで言語表現における質としてどこかで受け止めるべきじゃないか。具体的には、「ここを「が」にすると大きく意味合いが変わる」とか同じ文章でも違った意味あいになる、というのは、テキストを精緻に読み解き書き記すなかで当然身に起こる、詩・小説に限らず言語表現の基礎であるし、日本語の小説は翻訳とちがって厳密ではないから読まないというのは「日本語の小説」だけでなく言語表現という営み全体をあまりに低く見積もりすぎているというか、まずまず不快だった(発言はぼくの解釈もあるだろうので違うかもしれません。違ってたらごめんなさい……)。
インスタグラムとか見ながらテキスト書いてるというのはすごく面白い、と同時にやはりこれも、書く私に還元されないテキスト操作という意味ではそれ自体は新規性はもちろんなく……山田亮太とかのテキストをベースにやったりとかするほうが、自ら書くよりもより徹底されるだろうし……ただ、村社さんのテキストはそれ自体で特異な傾向を持つので、簡単に代替可能と言っているわけではない。そこでなされているところの、言語表現を通した空間の立ち上がり方(と、それを実現するところのテキストの(語り手の/書き手の思考の)レイアウト)と、具体的な身体のあいだの関係性を問うことは、書き手の私に還元されるかどうかという問題とはちょっと違うところで、極めて重要と思う。
なので、総じて個人的には、(これは新聞家さんの「白む」でも思ってTweetしたところだった気が少しするけれど)やっていることはとてもわかるし共感するしおもしろいのだけれど、作品(提示)の形式に関しても、言語表現というものへの接し方に関しても、もっと徹底できるのではないかという気持ちがあった――って、もうほとんど新聞家の表現方法をめぐる話になってる気がするし、今晩上演されたという新聞家の作品『建舞』を見れていないし(※そこではレクチャーもあったらしいから意識的に問題は解決されているのかもしれない……)、そもそもそんな、ぼくなんかが言語表現を代表するかのように言えることではまったくないわけですが……つまりは取り急ぎ「隙間を埋めるのにブロッコリーを使うまで」に関しては個人的にすごく共感すると同時に外枠とアフタートークに関して違和感もあったということです、した
※新聞家「白む」を見たときのTweetを以下に引用しておきます。(2016年7月23日)
新聞家ようやく見れた、『白む』、終わってから台本買いよるおわさんと喫茶店で散々話してる、今も話してる 死後の私を私が語りうるか、というかそのような語りを抱える身体として目の前の身体を見、知覚することができるか、ということに散文が活用される、という感じと受け取った、が、どうか、
テキストにおいて複数の私がリテラルな距離を保って記述される、つまりテキストとは複数の私同士の空間的距離の網目の提示である、としたとき、それをひとつの役者が強引に抱えると、その役者の役柄そのものにテキスト的距離が移植され、役者を見る私はひとつの身体に複数の魂の距離を見ることになる
この私が特権的に立ち過去を思い出すのではないかたちでの私の生成であり、それに向けて、テキストには記されていない「朗読の仕方、身振り」が役者において為される というかおそらく稽古でそのような身振りや朗読法が発明される ひとつの身体がテキスト的距離を抱えるとはどういうことか、が……
試行錯誤されるというか それは、目の前の身体が今悩んでいるように見える、思い出そうとしている、過去の私や未来の私との間の関係性を抱える思考を作り出そうとしている身体が提示されている、と観客が感じることで、この場に立ち上がる(?) それが、今回の場合、3つある(3人の役者がいる)
そこで、3つの身体同士の関係性が生じる余地が生まれる、それは、語られている内容における場の共有を担保として(登場人物や時間の共有を担保として)、ある人の語りの中に別の人が出てくる、ということなどで示される また、さらに、あなた、という言葉が関係性を多層化する
これはおもしろいし、美しさ?を感じるところある、語りの構造自体が感動的だ、
ただ、同時に、それは小説の持つ可能性からどこまで飛躍しているか、という気持ちにもなるところはある、よりよい小説における思考を体感させる方法としてよいという話におさまると惜しい気がする
実際の役者(の身体)を用いること、空間を用いること、でなされる一番の効用は、小説における「語り手の死に得なさ」の乗り越えだろう、テキスト(そのなかで起こる私の内的距離)を抱える身体が明確にそこにあり、場所をしめることで、私の外的距離がさらにリテラルに活用可能であるのは大きい
ここからさらに、その外的距離を活用するという道がある気がする、意図してそこのあたり貧しくさせられてた気がするが、結果、細かな身振りやテキストの複雑さが、ぼんやりとした雰囲気としてしか把握不可能なままに留まらされてる感じは少しある、その結果、美しい、と思えてしまいそうになる感じ
小説における激しい思考法をより激しくする方法として身体や空間をぼくは考えてしまうがそのためには知覚における単位や拠り所を、語りや振る舞いや朗読法だけではなく、空間全体なりなんなりに知覚の宿を設けていかなければ、通常の人間には(小説そのもの以上に)知覚不可能になる感がある、
その知覚不可能さこそがある意味では、一人の人間に複数の私を知覚すること、一人の私が複数の私を抱えること、の難しさでもある、のが難しいところだけれど、そこらへんを分解解体し技術化し共有して思考するモデルを自分は作りたいのだなという省みる感じになってきたな
※福留麻里「抽象的に目を閉じる」に関するTweetも以下にまとめます。「抽象的に目を閉じる」ではテキストもたくさん使われていたのでした。(2017年09月25日)
福留麻里「抽象的に目を閉じる」、魂と法則、私の範囲と行為の従属先の問題を感じた。物理的な動きを見せる(円を描く手など)とも、または身体から読み取れる感情や役柄を見せるか、とも違う、〈私において生じる(異様な物質的外部性をもった)知覚を見せること、がある、しかしそれは表現可能なのか
じっと目を閉じている人、が考えていることは、それを見ている人からすればわからない、が、しかし目を閉じているこの私においては思考は確かに存在しているし、その思考自体もまた運動している。同様に、手をぐっと動かす、その動きの細部に神経を行き渡らせる、自分にとってそれは極度の体験だ、だが
その動きを見ている人にとってその体験は伝達可能だろうか。もう少し先へ。地図を空中に描きながら言葉で説明するその際の身振りは腕をぐっぐっと動かす点で、何も言わず踊っていたときと動きとしてとても近い、が、それは場所を説明するときの身振りだ。私らはなんの動きを見ているのか。
円を描くように動く照明……に向かっていく、照明が近づくと避ける、を繰り返しているのを見るだけでは単に近づいてきたものを避けているだけに見える、が、実際にやると視界を極度に覆い空間を満たす光の強さと近さが、自分の向かう動きを上回り、空間全体が近づいてくるように感じられる。私的感覚
しかしその私的感覚は伝達可能か 物理的に腕を動かすのを他の私が見るように、この私の感覚を共有すること。その感覚を感じる私=観測者とはどこにあり、どの範囲まで広がっているのか。目をつぶっている私の内部に広がる思考と、動きを満たす(動きが従属している)法則が、近づいてくる。
私が腕をぐわんと動かす、それはぐわんと動かすときの感覚に従属し、それを確かめようとしているからだ、ということ。それが、他に共有されること。具体的形態をもたない感覚が、共有される。それはコンテキストというよりは、理解の形式としての身体、言葉、現実、なにより〈私〉だ。
私の行為はどこまで私か。私がスイッチを押すとビルが爆発する。私はスイッチを押しただけであとは導火線やらなんやらが爆破を招いた。だが私が爆破したと言える。そのようなレベルで行為は私に所有されたり、あるいは出来事や現象や事物によって多重的に所有される。理解の形式を介すると。
水が蛇口から出てシンクまで行きつく間の距離・空間に満ちた感情=意思=法則=根拠を探ることが、私がなぜこの行為を行ったかということ、私がなにも身体を動かしていないのに何かを感じ思考していること、私がそれを感じられるが別の場所の私はそれを感じられないこと、へと連なる。
語り、PC、音響、光、本、はそのような感情=意思=法則=根拠の距離・空間を、シンプルに、実験のように、様々な形で展開する。首くくり栲象さんの話をする、そのなかで語られる人物が目の前の身体における私であること、その身体がぴょんぴょん飛ぶことは首くくり栲象さんの話に由来していること、
そのように感じられるという、行為に対する理解の形式について思考する手立てが与えられること。おそらくは(?)目の前の身体の私が過去に語ったらしい声、その背後から聞こえるキーボードをタイプする音、実際に今ここで打つキーボードの音、は、言葉の所有者を過去の特定の瞬間の私に位置づける。
空間の中に、過去の私、今の私、が折り重なった状態で、いまこの身体が腕を動かしている、その腕の動かしはどこに従属し、なんの法則=感情=意思=根拠で動いているのか。それはどこに位置していて、それを感じている観測者である私はどこにあるのか。同様にそれはもちろん、
腕の先、足の先、身体の輪郭、等などを基点とする動きの生成においてもそう、腕の長さが軸になって動くこと、においてその動きはどこに法則=感情=意思=根拠を持ち、それはどのようなかたちでここに広がっているのか。行為における私、が網の目を何重にも作る。そしてそのなかで、
その理解の形式のなかで、じっと目をとじる身体がある、そしてそれを見ている私がいる。私は目を閉じ思考していない。が、ここまでの動きと音と語りと光らが各々で法則となり、行為の由来となり、〈私〉を分有された状態で、そこに目を閉じた身体があるとき、その思考が時空に広がって感じられる。
そしてそれは、そのような「私」という、理解の形式を作ることでもある(かもしれない)。そしてまた翻って(余計に?)言えば、目をとじる身体を見る形式を作ると同時に、何かを見ている身体を見る形式を作ることでもあると言えば、一周回って冒頭の、音に満ちた空間を見るばかりの身体にかえっていく
踊りと言語表現は、いずれも異様に〈私〉が、表現の素材や形式としても、立ちはだかってくる気がする モノに委ねきれない ある意味興味深いのかもしれないのは、これが即興ではなく少なくともある程度の構成(記譜?)を持っていること その構成もまた、ひとつの法則=感情=意思=根拠を持つだろう
作品そのものを見るのかコンテキスト優先か、というのはほぼ区別なく、特に私というものは表現・理解の一形式であり、特定の表現形式においては特に、石ころの硬さや絵の具の質や画面の枠のように、強い抵抗と主体性とをもって制作者・知覚者ともへ迫る
オブジェが複数の知覚の束として機能すること、言葉が精神を織り込んだオブジェとしてあること、しかしそのような言葉で作られた詩が決して強い作者性を持っているわけでもないこと、〈私〉がひとつの素材として編集・配置され、世界/事物/私/経験の持続・結合・分断が検分されること (瀧口修造)
2017_09_15
世間?があんまりにもわかってないし友人の優れた書き手が評価されず他の表現形式とも繋がらず消えていく感があったし新人賞とか既得権益との運任せ勝負みたいでわけわからんくて批評書き始めた感もいろんな理由のうちの微かな1つとしてあった気もするけどまあもうその役目は6割終わったという気持ち。
いったん批評を書くことで、小説では突破できなかった圧の域を超えでることを目指したところはあったけど それはもう文体レベルで解消されたと感じる 小説の文体、と一般に言われているものは、語りにおける虚構の力が強すぎるところがある 当然場合によるし、一度突破すると小説は圧倒的に強いが。
なんでも書けるはずがないのに小説は中途半端になんでも書けるようになりすぎで、それは書き直しを強いてくる文章相互間の圧に関係してくる し、さらにいえば〈私が私であること〉と〈思考における論理〉や〈論理そのものへの信じ〉とのあいだの関係にも関わる、という感は少なからずある。
テキストを共同制作するときや強力に圧のかかった身近な文章へと草稿を書き直しているときの、わけのわからん地獄のような書き直し過程は、16.17.18のころは、自らの感覚と言葉の音(リズム)によって行われていた。けど、19.20.21になって語りと世界の地と文法(身体)の組み換え可能性を強く意識するようになった時に、書き直しの地獄さを強いる何かがいったん自分の中で相対的に薄れてしまった感がある それは、感覚や音・リズムに由来した書き直しが、人にほとんど伝わらないような(物語性のない?)テキストを自らが作ることへの意識に由来してもいた。
あるいみ「人に伝わるものを書こう」という意識は強迫観念めいて19.20.21の自分にあった それはベタに読み手の確保などにも関係していたが、人間が読み書くことそのものへの介入がいかに可能か、小説という一定量のテキストを持続的に読み書くとはどういうことか、現実とは何か、という問いこそが根幹であった ゆえに異様なテキストであるにもかかわらず比喩ではなく一種の現実の記述として読めるSFのテキストに惹かれたことがあった。
そしてぐるっとまわって、批評を一度書くことが、音や言葉のリズムに代わる書き直しの地獄さのトリガーを獲得することとして立ち上がり、さらにそれは共同でテキストを書くことや人間にとっての論理の問題や、さらにはくるりとまわってあらためて音やリズムの問題を引き連れてきた。
そうして今あらためて詩や小説を書くとはどういうことかを考えたい。が、ゆっくりだろう。
(※ポップさや読みやすさ、を、簡単に語り、それに対抗するものとして難解さや(ひどい意味での)詩的さ、を置くことは、軸のレベルで弱いし、読み書く私の問題がそこに絡まずテキストのレベルだけでどうこうなると考えることも、また弱い。し、自分がそれであることに気づかない人もいる感がある 知らん)
2017_6_23-25
一昨日、ステム・メタフィジック研究会 ミシェル・セール『作家、学者、哲学者は世界を旅する』を一冊ぜんぶ、やる時間 大変ありがたいというしかない時間で終始頭が沸いていた ひとりでは不可能な方々のつながり方、さらに自分の手元の問題意識や微かな技術と密着する手立てが見つかる慄きがあった 打ち上げでの上妻さんの、使えるか使えないか、という考え方に共感した などなど……
朝、家に帰って、昨日夜、いぬのせなか座の次号のための座談会の1つ(政治、場所、ホラー、詩)について話し合い 幽霊のオブジェクト性や貞久秀紀についてなど(も) その流れで『ほんとにあった! 呪いのビデオ』51を見る。かなりよいもの多かった。
以下、粗いままメモとして並べておく。(こういうときTwitterでは長くなりすぎるから、自分はこうしてほとんど更新しないがいつまでもブログを持ち続けているのかと思う)
===============
『ほんとにあった! 呪いのビデオ』51
「空中楼閣」は、山奥のありえない高さに、明るい窓があらわれる。貸別荘のノートに子どもの筆跡で書かれた地図→窓のなかで手を振る子どもと親の影→そこで殺され遺棄されたという子ども、という連鎖には個人の目的がほとんどない。ありえない場所同士の隣接関係。それをゆるく繋ぎ記述する霊と観察者。
「溶怪」は、アップにされた顔の不気味さとそれがただ溶けていく時間がよい、そのよさは撮影者の不在(携帯電話に勝手に入っていた)に大きく依る。「中古ビデオ」や「井戸」など、映像そのものが呪いを具現化するという正当な「呪いのビデオ」的あり方。徹底すると『POV〜呪われたフィルム』になる。
徹底すると、というか、モンタージュや撮影主体が人間の身体に依存しなくなる過程を、『POV〜呪われたフィルム』は、疑似ドキュメンタリーの、撮影者が物語内に人物として位置づけられる状態から、丁寧にカメラと場所関係を増やしていき、結果としてカメラだけが自律する過程を描いている。
カメラだけが自律してあるというと、監視カメラ系は根本的にそういうものだ、が、ちょっと違うのは、カメラが幽霊を外から眺めているか、それともカメラそのものを幽霊が所有するか、だ。ただそこに写ってしまう、というのは、「呪いのビデオ」ではない。カメラは幽霊から切り離されている。
例えば「ベッドの下 開かずの部屋」では、ベッドの下にカメラを置いておくと写ったもの、とされるが、幽霊が最後、カメラに迫ってきてカメラが倒れる。ここではカメラは幽霊と切り離されているがゆえに攻撃される。ふたつは所有関係にない。
一方、「シリーズ監視カメラ 古本屋」は、ブックオフ的な場所に急に後ろ歩きで和服の女の人があらわれる、それをふたつの監視カメラが別角度から捉えるが、どちらにおいても後ろ姿が見えてしまう。これは噂には聞いてたけどかなりよい。こうすることで監視カメラも「呪いのビデオ」化する感覚があった。
ふつう幽霊は、それを見るものの内部が外部環境に投影されるかたちであらわれる。幽霊はそれを見ている人に取り憑くことで、見られ、現れる。「一緒に見ていた」(『鬼談百景』)でも、教師がグラウンドを見るその場所に幽霊が立つ。あちらを見ればあちらにいるし、こちらを見ればこちらにいる。飛蚊症みたいなもので、幽霊の位置は見るものによって変わる。
ここから「一緒に見ていた」では、「私が教室の窓からグラウンドを見おろす→霊がいる→見るたび場所が変わる→後ろを振り向く→霊がいる→いなくなる→グラウンドにまたいる→遊んでる学生が霊にぶつかってなんだこいつって感じになる→私の背中に霊が張り付く→肩に手をかけられしばらく霊とふたりでグラウンドを見る」という流れをたどることで、霊が環境への私の内部の投影というものから、複数のエージェントに接触可能なオブジェクト性を帯びて存在するものとなり、その上で、私は霊と視線を共有し、環境を見つめることになる。私が所有していた霊は、私を所有する。そのために、私とは違うパースペクティヴが、霊と学生との物理的接触というかたちで導入される必要があった。
もうすこし細かく。最初、私のパースペクティヴに依存していた霊は、見るたびに異なる場所に存在するものだった、けど、それは自律できていなくて、あちらに立つ霊とこちらに立つ霊、は、それを見る私の持続のあり方をなぞるばかりだった。霊が偏在しているとしたら、それは、私の持続が偏在しているからである。
しかしここで、学生が霊にぶつかる。霊が、私とは異なるパースペクティヴから知覚され、複数のパースペクティヴを束ねるオブジェクトと化す。それまで霊を束ねていた「私」という同一性から、霊が別の同一性を確保し、自律した。結果、次のシーンで、私の身体が霊の身体にぶつかることになる。私は肩に手をかけられ、霊とふたりで、先ほどから霊があらわれていた(私が見つめ、霊をそこへ投影していた)空間=グラウンドを見つめる。
私と霊は、対等に視線を奪い合う関係となり、さらには私の同一性(複数のパースペクティヴを束ねる私のありよう)が、私の背後にいる霊に包摂されるまでに至る。グラウンドを見下ろす私のパースペクティヴが、幽霊に奪われる。私が見る場所に幽霊がいる(どこを見るかは私の自由であり、さらに方方にあらわれる幽霊の偏在のじくざくを統合するのも私である)という状態から、見るということ自体が幽霊に所有され、私がその媒体となるような状態への、移行。
このとき、グラウンドには、幽霊が存在する必要はもうない。ただ見るだけでいい。風景、世界、地が、それ自体、幽霊化する。幽霊によって、複数の私のパースペクティヴが編集される。新たなモンタージュ。これが、「呪いのビデオ」化、私と世界の再編成である。
こうしてようやく「シリーズ監視カメラ 古本屋」にもどると、そこでは複数のカメラが、同じ幽霊の背中を捉えていた。通常の時空間だとそれはありえない。異なるパースペクティヴから見れば、見えはそれぞれの位置からのものになるだろうから。逆に言えば、このとき、どこから見ても同じ背中を見せる幽霊は、ふたつの異なるパースペクティヴを、束ねるための論理として働いている。
そして重要なのは、幽霊のいる古本屋の空間が、カメラの位置に応じて見えを変えているという当たり前のことが、上記の事態の背景に貼り付いているということだ。もし古本屋の空間が、幽霊の見え(背中)に引きづられていたなら、映像は、ただ単に、同じひとつのパースペクティヴからの眺めとしか知覚できなくなる。幽霊は、古本屋の空間から自律している。むしろ、2台のカメラの側が、古本屋の空間に依存し、お互いを分離している。パースペクティヴは環境に埋め込まれることで互いを分離し、霊はそれらを、同時性のもとで統合することで、環境から自律する。
そしてそれは、霊が、2台のカメラの映像を交互に見る視聴者の鏡像でもあることを示している。ここにいながら、こことは別の環境からの刺激に反応し、思考・行動しうること。異なる時空間・環境を配列・レイアウトする、新たな同時性・隣接性の論理としての魂。
背中を見せ続ける霊を経て、霊がいなくなった古本屋の映像がふたたびしばらく映るとき、映像のなかに霊が写っていなくても、2台のカメラの映像を交互に見るこの私の内部に、霊の論理は埋め込まれている。環境から自律しつつ、しかし環境の配列・レイアウトに依存して自らの「束ね」性を表出してもいる。霊自身が所有する時空間の自己表出=「呪いのビデオ」は、人間とは別の魂を「私」に宿らせ、新たな時空間・環境の配列・レイアウトの論理を制作する過程(修行?)としてある。
(追記、よく考えるとこの古本屋の霊は、クザーヌス『神を観ることについて』で語られている、どこから見てもこちらを見ているようにみえる神の像、と同じ構造かもしれない。つまりその先にあるのは、神は私という個別なものだけを見つめながら、同時に世界すべてを見ており、私は神の類似であり、しかし神から自律して自由を持っている、というような、ひたすらに矛盾が矛盾なまま同居した状態だ。私は私という個別のパースペクティブにいながら、同時に神という、全体のパースペクティブともつながっている、その関係。となると重要なのはやはり、「汝は汝のものとなるべし、そうすれば私さえも汝のものとなる」という神の言葉か。
以下、大江論(いぬのせなか座1号)の註より。
クザーヌスは、神が《あらゆる願望において願望されるあの真理》となる根拠として、人間に対する神の把握不可能性をあげる。《もしも眼差しが視覚によって満たされることなく、耳が聴覚によって満たされることがないのであれば、知性は知性認識によってはもっと少なくしか満たされないのだからです。それゆえに、知性を満足させて、それの〈目的〉となるものは、知性が知性認識するものではありません。しかし、また、知性が全く知性認識することのないものも知性を満足させることはできません。ただ、知性が知性認識としてではなく〔何らかの精神的な引き上げにおいて〕洞察するものだけが、知性を満足させることができるのです。つまり、知性が認識する知性的なものが知性を満足させることはなく、知性が全く認識することのない知性的なものもそれを満足させることはなく、むしろ、十分に知性認識されることはとうてい不可能であるほどに知性的であると知性自身が知るもの、これのみが知性を満足させることができるのです。それは、ちょうど、次のことと同様です。すなわち、飽くことなき飢えをもっている者を満足させるものは、彼が一口で呑み込むことができるようなわずかな糧ではなく、また、彼の手が届かないような糧でもなく、彼の手が届くものであって、かつ、たえず呑み込んでも決して呑み込み尽くされることがない糧だけです。このような糧は、呑み込まれても減るということがなく、つまり無限であるのだからです。》行為にともなう時間経過をはらんだ無限の把握不可能性。神はそこで、《無量で無尽蔵な宝庫》となる。それは、先に触れた「汝は汝のものとなるべし」という言葉の直後に、クザーヌスが《あたかも自分自身の贈りものであり、あらゆる希求に価するものが納められている無限の宝庫であるかのようにして》神を享受するのだと語っていたことからも明らかなように、私による神の所有と矛盾しない。《あなたの偉大さについてのこの最も聖なる無知は、私の知性が最も強く求めている糧なのであり、もし私が自分の耕地にこのような宝庫を見出したならば、直ちにこの宝庫を自分のものにしてしまいたいほどのものなのです。
おお、豊かさの源よ、あなたは、私の所有によって把握されることを望みつつ、同時に把握されえない無限なものとしてとどまることを望んでいます。》そして、この所有が、私による類似の創造を通して浮き彫りとなる自己愛を拠り所としているのである。《われわれは、自己の存在を分有しそれに附随しているものを愛するのであり、われわれの類似を大事にするのです。なぜならば、われわれは或る像において自己が表現されるならば、われわれはそれにおいて自己自身を愛するのだからです。〔…〕私によって創造されたように思われる類似が、実は私を創造する真理であり、その結果、少なくとも、どれほど堅固に私があなたに結び付けられるべきかを私は理解することになるのです。なぜならば、あなたにおいては愛されることが愛することに一致するからです。つまり、もし私の類似としてのあなたにおいて、私が私自身を愛さねばならないのであれば、あなたが私をあなたの創造物であり似像として愛して下さるのを観て、私は愛することに大いに結び付けられるのだからです。》こうして、知性によっていつかは把握されることが示されつつもその行為の無限性において把握され切ることのないなにかに対する知性の営みが、私による私に類似した私の制作となり、それがさらに自己愛において逆流し、私という構造そのものの制作へと、まるで円環を築くようにつながることが明らかになる。
また、これは大江論でもとりあげたしいぬのせなか座1号の扉ページに一部改変して引用したりもしたが、荒川+ギンズ『意味のメカニズム』でも次のような点をめぐる話があった。
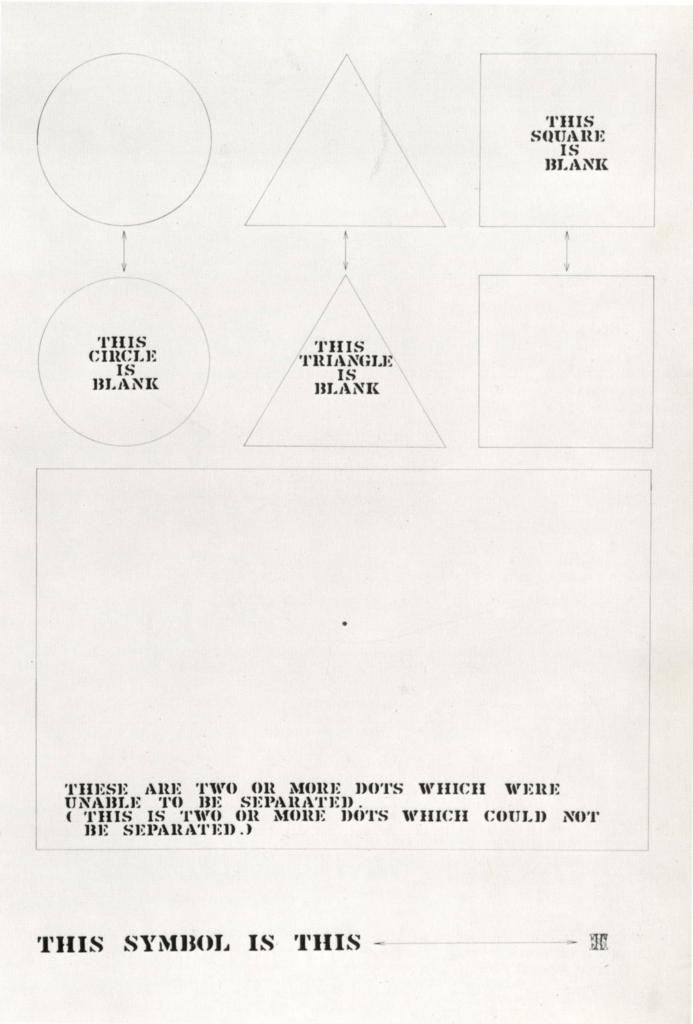
ギンズの荒川論には、複数の矛盾した知覚をレイアウトする絵画を軸とした共同制作の議論があるけれど、それは今すぐには出てこないし、話が錯綜しすぎる。)
===============
ミシェル・セール『作家、学者、哲学者は世界を旅する』は、フィリップ・デスコラによる四分類をベースにしているが、そのなかでも特にアニミズムとアナロジズムの関係が気になった。
アニミズムは、《あらゆる存在のうちに同一の魂が見出されるが、それらはめいめい独自の身体を纏っている》という考え方で、アナロジズムは《実在するものはすべて異なっており》、《無秩序で離散的なもののうちに可能な関係を発見することに、精根を傾け》る考え方とされる。分類としては、アニミズムは、自然が一つで魂が複数というナチュラリズムの考え方と、アナロジズムは人間同士の相違や関係を動植物の相違から理解するトーテミズムの考え方と、それぞれ対応するかたちで定義されるけれど、議論が進むなかで4つは混淆するように用いられていく。
トーテミスト的な構成要素は分類のための諸方法に霊感(インスピレーション)を与えるし、アニミスト的な構成要素は、進化や「大いなる物語」へと駆り立てるし、ナチュラリスト的な構成要素は、主体による対象の認識に必要なものを整えるし、アナロジスト的な構成要素は、とてつもない相違を微細な類似性によって絶えず架橋することになる。
この4つの分類が混淆することではじめて記述可能(思考可能?)になる領域が出て来る感じが、読んでいてとてつもないのだけれど、そのなかでも特にアニミズムとアナロジズムに関してメモしておきたい。
まずアニミズムについて、
私たち異類、アニミスト人間は、われわれを観察する民俗学者たちがいうには、生物たち、植物や動物たち、さらには生命がないと言われる事物までもが、私たちと同じ魂を持っており、同じ内面性、同じ習慣や文化、意図や感情を持っているところで生きている。私たちを唯一区別しているもの――それはもろもろの身体(Corps)であり、その分厚い球体が私たちを隔てているので、他者についての私たちの知覚は、それによって影響を受けるのだ。私の身体が私に垣間見させるのが、人間の魂を授かった狼や犬や魚なのだとすると、それら三つの動物は、私をどのように見るのだろうか?――人として見るのか、魚として見るのか? それはアニミストたちの文化による、と学者たちは語る。それらの文化が、それによって身体を具体化し、物質化し、重みを持たせ、詳述する文脈(Intensité)によるのだと。
動物と人間は、異なる身体を持っているが、同一の魂を持ち、お互いを自分のパースペクティヴから見ている。これは言い方を変えれば、身体さえ変われば、人間は狼や犬や魚と区別がつかなくなるということでもある。ゆえにアニミズムは、《変身(メタモルフォーズ)なくしてはあり得ない》ものとされる。《おのおのの身体が結局のところ衣装であるなら、衣服を取り替えるついでに裸体性、魂を垣間見ることもできるし、他のものたちが自分や私たちを、正確にはどう見ているかも垣間見ることができる》。
ここまででもすごくおもしろいのだけれど、セールはさらにここから、プルーストについて語る。人びとは、プルーストによる記述(有名なマドレーヌや紅茶のくだり)について、《それを素朴にも、鐘の音で餌を思いだして犬がよだれを垂らす、パブロフの実験のような粗雑な経験だと思ってしまう。そこで本当に失われているのは何だったのだろうか?》そうしてセールは以下のプルーストによるテクストを引用する。
私は、失われてしまった者たちの魂が、何か下位のもの、動物や、植物や、動かざるもののなかに囚われていると考える、ケルト人の信仰をしごくもっともだと思う。それらは、私たちがその樹のそばを通りかかったり、彼らが囚われているものを手に入れたりする、滅多にはない日がくるまで、実際に失われている。その時、それらは身ぶるいし、私たちに呼びかける。するとたちまち私たちはそれらに気がつき、魔法がとける。私たちによって解放され、それらは死に打ち克ち、戻ってきて私たちとともに暮らすのだ。
これに対してセールは言う、
水薬から雲がただよってくる。これが、古代ケルト人たちが崇拝していた種類の、動かざる物の魂なのである。作家が探し求める失われた時は、おそらく幼少期のものだ。――しかし、彼はそこにもっと隠れた時代のものを見出しており、それが失われ、囚われている場所すら明言しているのである。記憶の内部の暗い最深部に降りてゆき、語り手は奇妙で、奥深くに忘れられた、アニミスト的な諸文化に特有の行動やカテゴリーを再発見するのだ……
プルーストによる上記のテクストは、極めて言語表現的、特に小説的なスタンスだ。小説は常に自らを構成する多量の文章を束ねるものとして、語り手を立ち上げてしまう。「私」というものが、あまりに露骨に居座りつづける。だからこそ、記憶やポリフォニーが問題になるし、私小説的というものをどう扱うか(組み替えるか)が異様に重要になる。……という話は繰り返ししてきた、何を書いても並べても死なずに残り続ける強力な持続・統合機関としてのこの私をどうするか――それが、小説を制作する上でなにより根本的な問題としてある。その上であらためて考えると、プルーストのテクストは、私が私以外のものものに私を貸し与えるあり方としてまっとうすぎるくらいだ、私が私であるという強力な持続・統合の座を、事物に貸し与える営みとしての、小説。
プルーストの上記のテクストを、セールはアニミズムとして語っている。プルーストは身近なものばかりをひたすら書きながら、それが結果的に私と事物のあいだの変換可能性としての《アニミスト的な諸文化に特有の行動やカテゴリー》を探っているという。そのとき、この私がどうすればほかの私(犬、狼、魚、石)に使用可能な私になるか、の具体的操作法を考える上で、(全体がすべてひとつの魂にのまれていくような感覚から逃れつつというのであればなおさら)問題はやはり身体ではないかという気持ちが芽生える。魂を縛る身体をどう考えるか。私は、この身体から容易には逃れられない。セールもベルクソンの名を挙げながら言っていた、《あらゆる地域において、人々は身体(物体)が、連続的でより大きな魂を局限するものであると語っており、そのようなものとして生き、考えているからである。身体(物体)だけが、生命の持続に不連続性を刻むことができる。――ベルクソン自身が、そう語っているのだ。》
ここで、ようやく、アナロジズムについて。セールは、アニミズムとアナロジズムのあいだの関係を、メタモルフォーゼと所有−憑依の関係として記している。
メタモルフォーゼがアニミズムを特徴づけるのと同じように、それゆえ所有はアナロジズムを表す。私を構成する諸部分は、実際には私から離れ、広大な世界のうちをあちらこちらさまよっている。世界のもろもろの事物は、それ自体また、動き、旅をする諸部分によって構成されており、その諸部分はあちらこちらで、私も含めた他の人物や事物のうちに身を落ち着けることができるのだ。いわゆる悪魔的な憑依(Possesion,所有)の話をする前に、私たちはこうした構成と解体にもうしばらく注意を向けることにしよう。
私はこれらのばらばらな諸要素から作られており、私の人格はいわばその綜合だが、私に特に結びついた要素は何もない。それら諸要素のおのおのは、出たり入ったりできるし、おもむろに別の人間に入り込んで、そののち自分(モワ)というものを作り上げるのに役立ったりするのだ。メタモルフォーゼによってプロテウスは獅子に、豹に、猪や蛇に、菩提樹にすら変わり、水や風に変化する。所有(Possesion)は、一人の人間を解体し、他の諸要素によってふたたび作り上げる。そうした諸要素は、他者から、他者たちからやってくるのかも知れず、他者や他者たちに属したままなのかも知れないのである。
私は考える、ゆえに私は他者である。それが身体のうちに入り込むまで、この他者の周り、この他者の方に集中し、焦点を合わせること。まさしく狂気(Aliéné)である。なんということだ! 人は自分から外に出たものだけを創造する。もしそれが外に出たのなら、それはそこに入り込んでいたのでなければならない。私の魂が、あらゆる思考するものたちのなかで、幾つもの声で語ることができるのは、こんな風にしてなのだ!
私は考える、ゆえに私は彼らの思考である。私は彼らを愛する。彼らは私の招待客(オート)(Hôte)なのだ。――私にとり憑き、私を貪り、私の肌でふたたび温まる招待客なのである。それを望んでいたのは、私なのだろうか、彼らなのだろうか? そんなことはどうでもよく、彼らは私にとり憑いていたのだ。望まぬ者たちが、望まぬ者を受け入れた(Inviti invitum immiserunt)。
船乗りたちのメタモルフォーゼは、一対一である。――一人の人間が多数によってとり憑かれること。
外部の、事物たちの無限の多様性、その万華鏡とその諸関係の交錯するネットワークは、その叫びたてるカオス、無秩序−秩序を、主体の内面に投影する。この主体は、世界とまったく同じように、幻聴とバックグラウンド・ノイズの耳を聾するような混沌のとりこになっているのだ。
わたしのうちには、無数の思考が蠢いている。
私のもろもろの断片からは、駆ける群れが外に出てくるのだ。
所有−憑依とメタモルフォーゼ。「私は考える、ゆえに私は他者である」という観点からだと、先のプルーストのテクストも、所有−憑依の問題として言えるような気がしてくる。ただ、問題はより複雑でなければならないのだろう。他者と私のあいだの関係ではなく、爆発的な蠢きのなかで沸々と私ないしはオブジェクト双方での「束ね」、持続、統合、が同時多発的に生じる。その収縮拡散の運動単位そのものを並べることによって見出されるレイアウトこそが、扱われなければならない。だからこそ、難しい。というのも制作は常にこの私を伴ってしまうから。いや、それを抜きにして、制作そのものを自律させることも考えられる。
話は逸れるがいぬのせなか座の鈴木一平とぼくとのあいだで常に議論になるのはそこだ。鈴木は、私をより分散していく方向へいくことを考える(ように、粗い話だが、ぼくは感じている)。作品に対して結果的に私の比重は低くなるように考えられる。このあいだ「抽象の力」展を見に行ったが岡崎乾二郎さんの言ってる職人についての話もそうだ、職人は自らの技術をうまく言語化できないが素材と接するなかで自然と高度な制作が可能になってしまっている、そこでは私というものはさほど重要ではなく、身体と素材のあいだの制作行為こそが重要で、それがほぼ自律している。一方ぼくは、私というものを抜きにして制作を語ることは常に不可能と思ってしまう。この私をどうするか、いかにこの私を使用するか、が、結局はどんなときも最大の問題になってしまう。
ただ、それらに違いはない、というところまで考えを進められる気が最近はずっとしている。小説よりかは、詩や演劇をベースにしてその考えが出てきている気がする。詩を私のレイアウトとして使用する方法をもっとしっかり理論化できないか。荒川+ギンズは、「私が私であること」のような、相容れないものをひとつに束ねてしまう作用をブランクと呼んだが(本当はもっと複雑な話)、それをさらに彼らはブランクスと複数形で度々呼んでいる。この複数を、どのように、この私が制作において実践するかが、大きな問いだ。アニミズムとアナロジズムがどう違うのか、その微妙なわかりづらさ(プルーストのテクストを、アナロジズムと呼んではいけないのか?)は、この私をどこまで引き摺るか、に関わるような気がする。いや、引き摺ってもいいのだが、よりメディウムの側で生じる魂のようなものを、過剰に用いて、この私を組み替えていき、組み替えた私同士をさらに並べる、その並べ方こそが前面化するようなものとして考える必要がある。
小説はその点では、あまりに長すぎる、かもしれない。よりシンプルに、レイアウトの論理をスパッといくつも提示していく必要がある気がしている。これは、それこそ、より複数人で同時にばらばらに使用可能な「「私」のレイアウトの論理」の提示、だ。プロトタイプ? 俳句の切れの問題や、改行詩の問題、藤井貞和の『自由詩学』の議論などを思うと、ぼくはまだ詩についてきちんと理論を提示しきれていないと感じる。
(ここまで考えて、クザーヌス『神を観ることについて』における、この私だけを見つめながらすべてを見つめている神と私のあいだの関係、を思い出した あれを、今考えるとどうなのだろう?)
以下の、「共に−揺れ動く(Co-agitation)」あり方は、限りなく魅力的だ。
思考(Cogitatio)とは、実際のところ共に−揺れ動く(Co-agitation)ことでないとしたら、一体何であろうか? 何千もの数の羊の群れの目も眩むような無秩序を、一人の羊飼いが、彼だけで支配したり導いたりできないし、動かす(agere)こともできないというのだろうか? このラテン語は、実際に動物たちを導くことを指しており、それらが他の多くの動物たちと集められるので、動揺(Agitation)が生じ……そのため管理(gerer)するのは難儀なのだ。そう、思考は私の生涯を通じて、絶え間なく私に、そのカオス的で、満ちあふれる、輝かしい、不調和なバックグラウンド・ノイズを……眩暈を与える。よろめき、つまずき、震えて、私はそれによって大地に倒れ、茫然とし、昏睡する。大河と乱流、歓喜よ。
(ここでやはり、大江『水死』における、語り手が別の身体へと移行するきっかけとしての大眩暈=詩の飛来、を思い出してしまう)
セールはアナロジズムをめぐって、構成、とたびたび言う。
これらの部族にとっては、物質的もしくは非物質的な、ばらばらで未規定なものの集まりがある。このような混乱のなかで生き残り、行動し、思考するために残されているのは、絶え間なく構成に努め、したがってそれらの差異を架橋するのに適した無数の関係を探し求めるという、骨の折れる義務である。
精神と感覚が、無数のばらばらな感覚を統一する、関係の組み合わせ模様のうちに運び込まれている。少なくとも詩人は、言葉と象徴を通じて、そこで私たちに構成物(Composition)としての、ある秩序を理解させようとしている。
アナロジストは、隔たった夜と光のただなかに諸関係を描きだす。彼は、まさに《混淆した(Confuses)言葉》のうちに《暗鬱な、深い統一》を探索する。『悪の華』のためにこの花束を作った者を、構成者(Compositeur)と呼ぼうではないか。
結局は、この、構成のありかたを模索することになる。重要なのは、中心のないネットワークみたいなものではなく、複数の私がそれぞれ固有な全体像を奪い合い、所有しあい、憑依しあうような、そういう状態を成立させる、共同性の論理を作ること。並置と、統合が、交互に折りたたまれたような作品を、論理として提示すること、か。
以下の箇所は、アナロジズムへの飛躍可能性のように、も、読めるかもしれない。
人が隣人を彼自身のように愛さねばならなくなっていらい、そしておのおのが自分自身の魂を救済しなければならなくなっていらい、みずからを見つめる真率な個人を描いた、聖パウロの自伝や聖アウグスティヌスの『告白』いらい……少しずつ、彼らの還元不可能な独自性が、全世界に満ちあふれるようになった。――それはアナロジスト的な文化のもう一つの名前である。そこではおのおのが決定し、みずからに配慮し、サバイバルし、みずからを救済し、自律的で、個性的で、異なっており、自由で……もろもろの特異性は、超越的な諸関係によって架橋されているのだ。聖人たちのコミュニオン……結局のところ、この宗教について、それが厳密な一神教であるのか、それとも本当の多神教なのか、誰が判断できるだろう? というのもそれは、同時に一であり三である三位一体を教えているのだから。
ここでの、三位一体の登場の仕方、に、なぜか異様な生々しさと自分にとっての迫りを感じてしまう。いぬのせなか座「座談会4」で、共同性について次のように書いた、《この私における技術の蓄積や歴史性や内省による思考の突破などを所有とは別のかたちで考えられないか。複数の身体の交感状態と、私が私であることにおける過剰さの、はざまを考えるときに、たとえば幼い頃の私を今の私と対等に見つめるように、風や波を私と対等に見つめ、それに反応して自らの現在の行為を形成していく。そうしたところで初めて、従属の問題は、なぜこの人に従属するのかというような、自由意志の問題から離れる。と同時にそれは魂や、私が私であることを否定するわけではない。
外部の環境からは導かれない行為が、ある身体において生じたとき、それをブラックボックス的な心の問題に回収させず、あくまで行為は環境と身体の交わりにおいて生じると考えるのなら、その行為は、身体が目の前に物理的に属している環境とは別の環境に従属したと考えるべきである、といったアイデアを、「いぬのせなか座」2号の序文で飛躍とともに記しましたが、このレベルでの魂、自由を肯定するものとして、微細な主体たちの教育関係はある。私が過去の私の記憶に従って振る舞うように、相手の身振りにあわせて振る舞う。それは外部環境への即物的な反応であると同時に、身体における環境の掛け合わせの能力に従った自由な行為でもある。そこでようやく、誰かの指示に従う、振り付けられることを、奴隷的なものとしてではなく肯定する、ということが生じる。》還元不可能な独自性が満ちた世界において、ばらばらなまま、共同で制作するための、セールの言うところの超越的諸関係(ここで、諸、がついていることが希望だ)、それにこの私はどう寄与するだろう? この私は不要だ、厄介だ、とは言ってはいいが消去まではいきたくないしいくべきでない。
それで言うと、「この私」における「この」について、以下の箇所は根幹であるように思えてしまう。
事物は私たちのなかを循環し、私たちの家に住みついているだけではなく、私の身体を作るために私に潜り込んでいる。私の思考が、困難ではあっても、この時間の幅を理解するだけでなく、私の身体を作るために私に潜り込んでいる。私の思考が、困難ではあっても、この時間の幅を理解するだけでなく、私の身体は宇宙とともに生まれたこれらの構成要素によって形作られ、ゆっくりと偶然的に、われわれの惑星とともに構成され、生物たちの進化にも寄り添い、そこに根を張り、そこに生きているのだ。ここにあるのは細部が同時的(シンクロニック)な三つの記憶の場所である。私の環境は、私の身体を構成している事物たちによって構成される。――それらは、同じ年代に由来しているのだ。私はここにこそ、あたらしい環世界(Umwelt)を発見する。あるいは、もっと言えばここでは、世界−内−存在のハイフンが物質化されているのである。私はそこで存在が何なのか知らないし、私はそこで世界が何なのか知らないが、私の細部は、その諸関係を辿っている。途方もなく古いがしかしあたらしい、あらたな文化の身体はみずからのうちに、古くて途方もない(Formidablement,巨大な)世界を見出すのである。
ブレーズ・パスカルを訂正しよう。――空間も時間も、肉体を飲み込んでしまうのではない。それらは肉体を探査し、形成するのであり、肉体はそれらを測り、それらを音節で区切る。このような持続を直観することが難しいので、しばしば途方に暮れてしまう私の思考にほとんど勝るくらい、そうしたことをやってのけるのだ。宇宙は私を粉々にする(écraser)のではなく、その細部のあるものたちが私を横断する(traverser)のである。逆に、私の何十年来の春は、これらの同じ客体的な細部に絡みあっており、そうしてそれらを特異化しつつ、主体化している。いわゆる非人間(ノン・ヒューマン)である古い自然の無数の細部を人間化することによって、この第五の文化はあたらしい人類再生(Hominescent)を生じさせるのだ。それは、自然契約を調印するのだろうか? それどころか、自然契約がおのずと受肉したのが人類再生なのだ。
ここにある、「同時的(シンクロニック)な三つの記憶の場所」、「世界−内−存在のハイフンの物質化」は、忘れられない。なによりここには、この私とこの身体を使用する根拠が記されているように感じる。この私とこの身体の、諸関係を、主体化し、それを用いて「非人間(ノン・ヒューマン)である古い自然の無数の細部を人間化する」。これが、「自然契約がおのずと受肉した人類再生」に繋がる。こうした、この私の心身への圧のかかり方、肯定、のためにアナロジズムやアニミズムがあったようにさえ思えてしまう。ほぼ誤読だろうが。
===============
ここから、貞久秀紀の最新詩集『具現』について考えたい。が、体力も時間も尽きたので、ひとまず引用だけをしておく。
「推移」
知らなければ瑠璃鶲だとわからなかった鳥が
細かなうごきで現われてきえた
この岸べにみずいろにうち寄せる
漣のゆるやかな音できこえてくる水のいろをみるまでは
想い起こすことのなかった藪なかの枝づたいにわたしが行き
ふだんとかわりなく前方をもつきょうの道に
「例示」
きょう、やぶ道をきてひとつの所に立ち
それがこの岩であるときはみえずにいる雲が
おなじ岩の台座から
きのうの曇りぞらにとりわけ陰がちにかたまり
光につよくふちどられて
山の真上のかぎりあるちぎれ雲のすがたにまで
高められ親しくながめられたことは
その日そこに湧きいでたただひとつのことがらとして
指折り数えることができる
「この岩を記念して」
この細道はいずれひとつの岩に当たり
岩がゆくてを塞ぎ
かたわらに迫る崖からゆるみでて
道に来ていた
それは近づくにつれはじめて目にうつり
すぐさまそれが前方に横たわる岩であることを
知らせるとともに
今しがた来たことの証しに土をつけているかのように
埋もれていたところに湿った土や
樹木の細く白い根が絡みついていた
ある日ひとりの口のきけない友が食卓について
食事をしていたとき
わたしがこの友といて食事をしていたようにこのときもわたしはひとつの岩に近づき
そこからのぞむことのできる
岩のおおまかな姿をながめていたが
そのころ
わたしはこのうごかずに目の前にある岩にうでをのばし
土や根や
岩の外であるところから自然とそれに触れた
昨日も鈴木一平と話したが、貞久秀紀さんを分析する上で頻繁に口にされる(阿部嘉昭さんが提案したところの)「減喩」は、ある場所そのものを立ち上げる技術だ。「知らなければ瑠璃鶲だとわからなかった鳥」という言い方をすることで、あるいはひとつの詩まるごとを使ってその鳥がいた場所を、そこに至るまでの私と場の継起を記述した上で記すやりかたをとることで、「道に鳥がいた」という記述において生じる統合のあり方から、道と、鳥と、私を、それぞれ切り離し、その上でそれらを並べることに成功している。
「この岩を記念して」の岩もそうだが、こうした技術によって、物も生物も時間も、それぞれが固有の場所を持ち、それらが相互に入れ子になりながらレイアウトされている。そしてなによりこれは、散歩する私の身体的持続が素材となって制作されている。決して、単なるばらばらではないのだ。この私が、この環境を歩き、この岩に触れる。その貧しさが、決定的な世界の構成の論理を記している。ここからひとつの「私」をめぐる理論を、考えたい。当然それは、ホラー映画や政治について考えることでもある、と思える。
というような話を、7月17日には自分はするのではないか。
http://bigakko.jp/event/2017/inunosenakaza