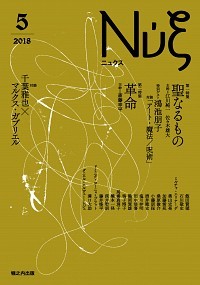江川純一・久保田浩編『「呪術」の呪縛』(下)リトン、2017年。
第一部 呪術概念の再検討
鶴岡賀雄「「呪術」の魅力:「永遠のオルタナティブ」の来歴と可能性についての試論」
「マギア」を人類学的・宗教学的分析概念としてではなく西欧精神史の構成要素として見て、古代ギリシアから、中世神学、ルネサンス、近世キリスト教、現代芸術に至るまで、マギアの位置づけを跡づける。
そこでは、マギアがつねに、公共宗教や哲学といった正統的な知や生き方に対して、劣位に置かれた人々による代替行為として位置づけられる。しかし、この民衆の低級知は正統知でないがゆえに、かえってそれを批判的に超える超高級知ともなりうるものであった。
近世神秘神学における神的/悪魔的/自然的という三分法が、人類学・宗教学における宗教/呪術/科学の三区分に改鋳されていったのではないか、という指摘はなるほどなあと感じ。また、世間的・民衆的な低級知たるマギアがつねに物を介するというのも、フェティッシュとの関係で興味深い。
「神秘主義」概念の検討については別稿に譲るとされているが、その「別稿」とはこれですね。→
鶴岡賀雄「「神秘主義」概念の歴史と現状」『東京大学宗教学年報』vol. 34、東京大学文学部宗教学研究室、2017年、pp. 1–24。
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/47687#
なお、本論文の中で、サラマンカ大学の学士アマドール・デ・ベラスコが持っていたグリモワール(魔術の指南書)をめぐる事件の話が出てくるが、最近、魔術のことを考えすぎて、先日、江川さんから「grimoireとは魔術書のことなんですよ」と教えてもらう夢を見た。
山崎亮「社会学年報学派の呪術論素描」
ユベールとモースの「呪術論」は混乱に満ちた論文であり、その一因として呪術のアポリア(呪術は私的なものであるが、社会的な性格ももつ)が挙げられる。この混乱を理論的に整理したのがデュルケームの聖理論であるが、ユベールとモースは納得していなかった。
江川純一「「magia」とは何か:デ・マルティーノと、呪術の認識論」
イタリア宗教史学におけるマジーア概念を、特にエルネスト・デ・マルティーノの『呪術的世界』とその後の転回にしたがって明らかにする。宗教学において一般的に、「呪術」は「宗教」のネガとして語られがちだが、宗教史学はこの対比・対立を認めない。
デ・マルティーノは『呪術的世界』において、呪術的世界は「自分の魂の喪失の危機とそこからの解放」という実存のドラマによって根拠づけられるとして肯定的に評価したが、この世界を歴史的時代であるとしたがゆえに、進化主義的宗教論と見分けがつかなくなってしまった。
「呪術的心性と原始的心性を混同している」という師ペッタッツォーニらの批判を受け、デ・マルティーノは後年、「呪術的世界」という想定を取り下げ、神話ー儀礼の結合物としての「呪術ー宗教現象」を探究するようになる。
注にある、「今後、20世紀の宗教学思想を振り返るときには、ペッタッツォーニ、デ・マルティーノ、エリアーデのトライアングルによる、神話ー儀礼的技術としての「呪術ー宗教」の考察が軸となるであろう」という指摘が興味深い。
なお、A. C. ハッドンが報告したボルネオのトゥリク族の男の話(ある男は鉤形の石を頑なに手放そうとしなかった、その石は魂が自分の身体を去るのを引き留めているのだという)がラトゥールのファクティッシュのようで面白い。
第二部 事例研究:古代~中世
渡辺和子「メソポタミアにおける「祈祷呪術」と誓約:「宗教」と「呪術」と「法」」
なかなか論争的ですごい論文であった。一言ではまとめづらいが、アッシリアの『エサルハドン王位継承誓約文書』(ESOD)の構成や文法を分析することで、誓約と儀礼、「言うこと」と「すること」の宗教的な結びつきを考察する。
アッシリア学者の重鎮オッペンハイムは、西洋人として祈りと儀礼が結びつくことに耐えられず、「メソポタミア宗教」は書かれるべきではない、とまで言う。また、ESODの誓約と儀礼という形式こそが、契約(誓約)宗教としての一神教の成立と後のキリスト教の成立にも影響を与えたという。
高井啓介「その声はどこから来るのか:腹話術の魔術性についての考察」
叙述がトリッキーで面白い。腹話術が古代の神学者たちによって魔術として扱われ、近代に脱魔術化していった過程が示される。旧約聖書サムエル記上の「降霊術」がギリシア語に翻訳される際にἐγγαστρίμυθος(腹話術)と訳されたために腹話術の魔術化が始まった。
降霊術が腹話術と見なされることで、腹話術師は腹の中に悪霊をもつことになり、霊媒は魔女扱いされるようになる。しかし、腹話術の魔術性を否定し、単なるトリックだとしたのが、『百科全書』で数学に関する項目を多く書いているジャンバプティスト・ドゥ・ラ・シャペルの『腹話術』であった。
山本伸一「カバラーにおける神名の技法と魔術の境界」
ユダヤ教のカバラーにおいて、正当な呪術と禁じられた魔術の境界は不分明である。このことを15世紀のカバラー文学、ルネサンスの自然魔術の影響下のカバラー、18世紀のエムデン=アイベシュッツ論争という3つの事例に即して考える。
15世紀スペインのカバラー文学の共通点は、主人公であるカバリストが終末とメシア来臨を促すために悪魔を追放しようと立ち上がるも、悪魔に騙されて取り逃がしてしまい、逆に魔術に手を染めた悪人として非難される、という物語。中2っぽいというか、『進撃の巨人』(デビルマン)フォーマットだなと。
青木健「ゾロアスター教神官マゴスの呪術師イメージ:バビロニア文化の影響と呪術師イメージの由来」
マゴスには「呪術師」「神秘主義の達人」「放蕩」といったイメージが付与されるが、ゾロアスター教の神官の職能を検討してみると、実態は王朝に仕える官僚であり、吉凶暦や蛇占いといった副業の方がイメージの形成要因となったと考えられる。
青木健『古代オリエントの宗教』は、渡辺論文の注で、紀元前2世紀から13世紀までのオリエントの宗教史を扱うものなので、「書名と内容が一致していない」と批判されていた。
毛利晶「古代ローマにおける凱旋の儀式:トリウンプスに関する最近の研究動向を中心に」
ローマで戦争で勝利を収めた将軍が行う凱旋の儀式トリウンプス(triumphus)。そこでユピテルの扮装をする凱旋将軍の役割は神か王か。近年の論争を踏まえて、著者は元々ユピテルの儀式であったものが後に将軍自身を讃える儀式へと変化していったと推測する。
凱旋式挙行の要件が、①命令権(imperium)、②鳥占権(auspicium)、③軍隊指揮(ductus)、④幸運(felicitas)の4つだったというのが、統治(王)・呪術(宗教)・軍事の三権が一人に集中しているようで興味深い。
野口孝之「近代ドイツ・オカルティズムの「学問」における「魔術」」
19世紀後半から20世紀初頭に展開されたオカルティズムにおける「魔術」の位置づけを、キーゼヴェッター、エスターライヒ、シュティルナーという3人の思想を中心に検討する。
ドイツの代表的なスピリチュアリスト、カール・ドゥ・プレルの概念das transzendentale Subjektを「超越的主体」と訳しているけど、「超越論的主観」では。このドゥ・プレルの理論を援用するキーゼヴェッターはオカルティズムをGeheimwissenschaftと呼び、先人としてスウェーデンボルグを挙げている。
ちなみに、スウェーデンボルクを批判したカントの『視霊者の夢』の第一部第二章のタイトルはgeheime Philosophie(オカルト哲学)である。
寺戸淳子「「呪術ではない」祭儀:「秘義」としての聖体拝領」
大変勉強になった。キリスト教の「聖体拝領(聖餐)」「実体変化」「神秘的肢体」といったややこしい話を基本的なところから丁寧に教えてくれるので、これらの神学的議論に関心がある人におすすめの入門的論文。
12世紀に「実体変化」の教理が確立したのと同時に、「神秘的肢体」(Corpus mysticum)論も確立していった。Corpus mysticumは元々、食べる方の「聖体」を意味していたが、秘義的ニュアンスがよろしくないため、それまで「教会」を意味していた「キリストの体」Corpus Christiと呼ばれるようになった。
12世紀に「実体変化」の教理が確立したのと同時に、「神秘的肢体」(Corpus mysticum)論も確立していった。Corpus mysticumは元々、食べる方の「聖体」を意味していたが、秘義的ニュアンスがよろしくないため、それまで「教会」を意味していた「キリストの体」Corpus Christiと呼ばれるようになった。
逆に、教会はCorpus mysticumと呼ばれるようになった。つまり、聖体と教会の呼び方が入れ替わったのである。この教会を指す「神秘的肢体」がやがて法人のような擬制的人格一般を指すようになっていった。カントーロヴィチぽいなと思ったら、カントーロヴィチが参照されていた。
佐藤清子「19世紀合衆国における回心と「呪術」:チャールズ・G・フィニーの新手法擁護論とその批判を中心として」
きわめて明晰な論文。19世紀アメリカの第二次大覚醒の時代を代表する牧師フィニーは「新手法」と呼ばれる礼拝方式を導入して革新をもたらしたが、それは回心を意図的・合理的に促す手法であり、限りなく呪術に接近していく。
フィニーはスコットランド啓蒙思想の影響の下、自然法則の学習・応用という方法論を採用し、自らの回心の方法を「科学」あるいは「哲学」であると称した。他方で、呪術・宗教・科学の三区分で知られるフレイザーもまた、同じくスコットランド啓蒙の思潮に影響を受けていることは興味深い。
フレイザーは呪術を稚拙な科学であるとしたが、もし仮に「回心」を心理学的な技術によって達成できるようになったとしたら、それは科学なのか呪術なのか。実は科学と呪術の区別は、その知識や技術の程度の差異によるのではないのではないか。
フィニーの「祈り」についての議論も面白い。回心は聖霊の働きによるが、人間は聖霊をコントロールできないがゆえに、回心も究極的には神に委ねられている。しかし、フィニーは回心と聖霊の間に「祈り」という人間の行為を介入させる。とはいえ、人間は祈りによって神を操作できるわけではない。
フィニーによれば、祈りはそもそも聖霊の働きによって可能になるのだから、祈ることができること自体がそれが叶えられる可能性があることの証拠となる、という。ここには、祈りのアポリア(祈りは効果があるならば、祈りにはならず、効果がないならば、祈る必要がない)を解く鍵があるように思われる。
久保田浩「近代ドイツにおける「奇術=魔術」:奇術とスピリチュアリズムの関係に見る〈秘められてあるもの〉の意味論」
19世紀ドイツで機械仕掛けの奇術を行う奇術師は、トリックを説明(klaeren)可能なものとしながら、それを驚嘆すべきものとして提示する者であり、スピリチュアリストの種明かし(erklaeren)をして詐欺を暴く啓蒙(Aufklaerung)の意義も担っていた。
奇術師がスピリチュアリストを科学的に暴いたり、宮廷からお墨付きを得た「宮廷奇術師」が登場したりと、『鋼の錬金術師』が好きな人にお薦めしたい論文。スピリチュアリストが、奇術師は本人も気づいていないけれど実は霊媒であり、本人が奇術だと思っているのも霊媒現象なのだと主張する話が面白い。
井上まどか「ロシアにおける呪術概念の検討」
前半が現代ロシアの事典や概説書における「呪術」概念の分析、後半が16世紀に編纂された『百章』における「呪術」の用法について。「準備的覚え書き以上のものではなく」という著者の言葉通りの文章であった。
『金枝篇』の著者名が「D. D. フレイザー」となっていて、目を疑った(ロシアだとJもGもDなんですか)。それ以外にも本書は誤植が非常に多い印象。上巻目次のタイトルからして既に間違っている。
西村明「呪術としてのキリスト教受容:ミクロネシア・ポンペイ島を中心に」
最終章でいよいよ真打ち「マナ」登場。ミクロネシアのポンペイ島における宣教でキーワードとなった「マナマン」から、マジックワードとしての「マナ」概念の歴史的形成の議論へ。
まず、宣教師は植民地主義的視点で現地の宗教的・呪術的実践を裁断するが、しかし、その視線は一方向的なものではなく、現地民もまた、自分たちの価値体系の中にキリスト教を位置づけて理解する。ポンペイ島で、二つの異なる価値体系を通訳した概念が「マナマン」であった、という話が面白い。
さらに後半、この「マナマン」(ミクロネシア)と同族語である「マナ」(メラネシア・ポリネシア)という概念が辿った数奇な運命が論じられるが、これも面白い。
「マナ」とはそもそも、コドリントンが『メラネシア人』(1891)において初めて学術的議論に導入した語で、その後、超自然的力を指す普遍的な概念として人類学・宗教学で多用されていった。しかし、コドリントンが現地調査したモタ島とバンクス諸島は、当時、ポリネシア人と宣教師の影響を受けていた。
メラネシアの「マナ」が形容詞や動詞としての含意があったのに、ポリネシアでは名詞として用いられた。メラネシアの宣教師たちは先にポリネシア語に通じていたために、「マナ」を名詞的に理解してしまった。こうして、コドリントンがやってきた頃には、既にバイアスのかった「マナ」となっていたのだ。
このように、「マナ」とは、ポリネシアとメラネシア、現地民と宣教師、そして世界各地の多様な宗教間といった、異質な価値体系を通訳=通約する概念として強力な力をもつようになっていったのである。異質な体系の間の界面に生じる通約的概念という意味では、「フェティッシュ」にも似ているように思う。