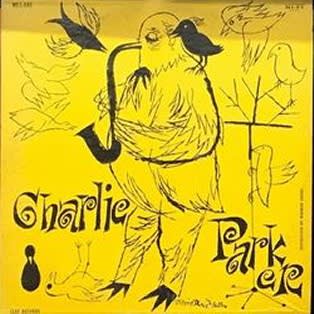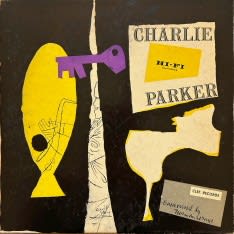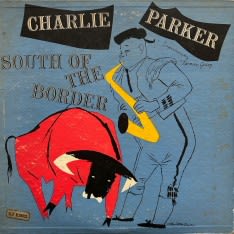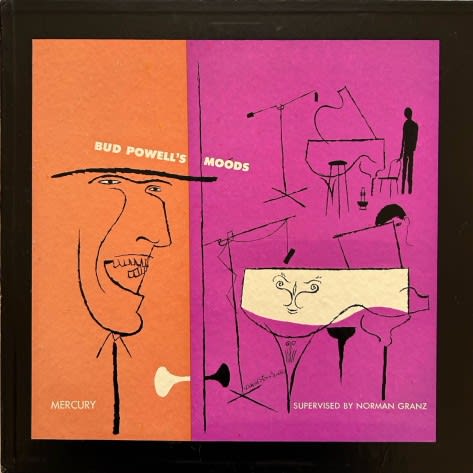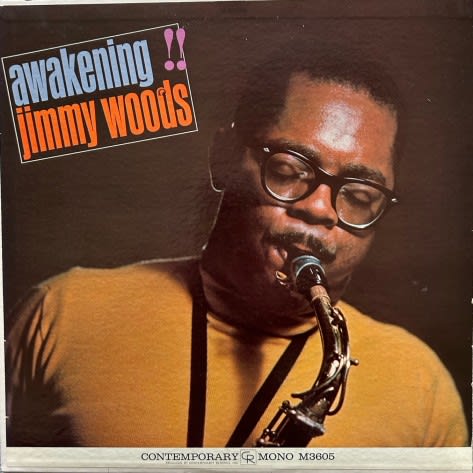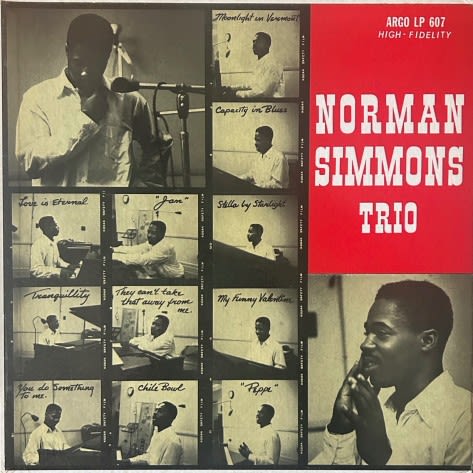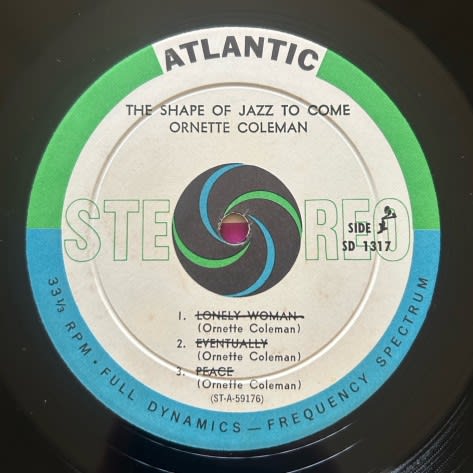Milt Jackson / In A New Setting ( 米 Limelight LM 82006 )
繊細で上質でブルージーなミルト・ジャクソンは、意外とワン・ホーンがよく合う。本来であればそういう持ち味を味わうにはシンプルな構成の方が
良さそうなものだが、管楽器が1本入ることでその分音楽に幅ができるからかもしれない。リード楽器でもあり、和音楽器でもあるこの不思議な
音色を持つ楽器はある時は背景として、ある時は相方として管楽器に寄り添う。その理想形の1つがミルト・ジャクソンのアルバム群の中にある。
マッコイ・タイナー、ボブ・クランショウが参加しているところがいかにも60年代だが、メインストリーム・ジャズながら音楽が古臭くないところが
こういうメンバーに依るところなんだろう。でも、音楽が60年代の箍が外れた感じはなく、しっかりとメインストリームに漬かっているのは
ジミー・ヒースという中庸のサックス奏者のおかげだろうと思う。誰一人尖ったことをやろうとはせず、ミルト・ジャクソンという大物を立てながら
足並みを揃えて演奏を進めていく。
静かな楽曲ではマッコイのピアノの音色が美しく、まるでコルトレーンの "Ballads" のような雰囲気があるし、マイナー・キーのアップテンポな
楽曲ではまるでルパン三世のサントラかと思わせるような粋な演奏を聴かせる。そんな風に、このアルバムは何より音楽が素晴らしい。
おそらくはロックの影響か、各楽曲の演奏時間が短く設定されており、途中でフェイド・アウトするような編集を施されたものもあったりして、
もっと聴きたいという気持ちを搔き立てながらもダレることなく小気味よくサクサクと進んでいき、これも悪くない。
頑固な50年代のジャズに固執することなく、もっと軽やかにステップを踏むような感じが何とも爽快で、それでいて注意深く聴くととても高度な
演奏力に支えられていることがよくわかる、素晴らしい内容だ。ライムライトはいいレコードを作った。このレコードは私のお気に入り。