この本の原題は「Ripley Under Water」。リプリー・シリーズの第2作が「Ripley Under Ground」(邦題『贋作』)と似ていて、じっさい、その内容も『贋作』から引き継いでいて、まさに「続編」という感じ。ただ、『贋作』(「Ripley Under Ground」)ではじっさいにリプリーはいっしゅん、地中に埋められてしまう展開があり、タイトルに偽りはないのだけれども、この『死者と踊るリプリー』(「Ripley Under Water」)ではリプリーが水中に入るということはない。そもそもリプリーは、このシリーズの中で何度も「水が苦手だ」ということが語られていて、「Ripley Under Water」だとイコール「リプリーの死」みたいなことを考えてしまう。
ただ、この作品では川の水の中に(『贋作』のとき、リプリーに殺された男の)死体があったわけで、Under Waterといえばこの死体のこと、もしくはこの作品の「悪役」的な存在で、さいごに自宅の池で溺れて死んでしまうプリッチャード夫妻のことになるだろう。
それにしても『死者と踊るリプリー』とは、またずいぶんとひねった邦題をつけたものだと思う。
今回の作品、けっこうたっぷりとリプリー夫人のエロイーズが登場して、お得意のフランス語をいっぱい聞かせてくれるし、それ以上にリプリー家の家政婦のマダム・アネットの出番が多く、けっこう重要な「証言者」になったりもする。リプリーらの住まい「ベロンブル」周辺の隣人らも登場するし、そういうところでは、トム・リプリーの普段の日常生活がいっぱい描かれていた、といえるだろう。こういうのがけっこう、つづけて読んできた読者にはうれしいのだ。
そして今回、リプリーの味方となって共に行動してくれるのは、『贋作』に登場したロンドンのギャラリーのエド・バンベリー。ロンドンからベロンブルにやって来てしばらく滞在し、リプリーの心強い「相棒」になってくれる(って、この二人の描写がやっぱり、そこはかとなく「同性愛」っぽいわけだ)。
トム・リプリーは、ベロンブルの自宅屋敷で庭の手入れやハープシコードを練習したり、絵を描いたりして日々を送っていた。プリッチャードという名の不快なアメリカ人夫婦が近郊に転居して来て、『贋作』でマーチソンを殺害したリプリーの犯罪を暴露しようとする。
夫のデイヴィッド・プリッチャードは当初、かつてリプリーが殺害したディッキー・グリーンリーフのフリをしてリプリーに電話する嫌がらせをした。彼はベロンブルの写真を撮り、そのあとリプリーとエロイーズのタンジールへの旅行をつけて行ったりもする。タンジールのバーでリプリーはプリッチャードと喧嘩になりもする。フランスに戻ったプリッチャードは、マーチソンの遺体を探すために地元の川底を浚い始める。
過去の犯罪が暴かれるのを恐れたリプリーは、マーチソン殺しの経緯を知っているロンドンのギャラリーに連絡し、エド・バンベリーに来てもらう。
ついにプリッチャードは白骨死体を発見し、リプリーの玄関先に骸骨を捨て置く。リプリーはその白骨を、エドに手伝ってもらってプリッチャード家の外にある池に遺棄した。プリッチャード夫妻は水しぶきの音を聞いて外に出て調べ、池にある白骨死体を見つけて引き上げようとし、転落してしまう。泳げない夫妻は共に池で溺死してしまう。警察が捜査して夫妻の遺体の他に白骨死体も見つけるが、それはもう過去の事件の手掛かりとなることはないだろう。
いつものように小説はトム・リプリーの一人称で書かれているが、今までのシリーズ作以上にリプリーが「過去の犯罪」の露呈を恐れ、怯えて不安に囚われるさまが書かれる。
また、いつもであればまさにトム・リプリーこそが「犯罪」を犯し、それを隠蔽しようとする展開になるのだが、今回はまず動くのはプリッチャード夫妻の存在であり、リプリーの方が「あいつらは何をしようとしているのか?」と推理することになり、それがリプリーの抱く「不安」を増幅するようでもある。
おそらくはリプリーもまた、いつものようにデイヴィッド・プリッチャードへの「殺意」を膨らませるようではあったが、そのような事態に陥る前に、プリッチャード夫妻の方で自滅してしまうわけだ。そういう、ひとつの作品として、「最後の詰め」は相当に甘いというか、「ご都合主義」に思える展開もあるが、まさに「ハイスミス作品」としての「不合理な展開と不安感」には満ちていた。
しかし、これで「トム・リプリー・シリーズ」もおしまい、というのは寂しいことだ。
最後に、この本の冒頭にはパトリシア・ハイスミスによる「献辞」が置かれているのだけれども、それが今読んでも興味深いものだし、ここに書き写しておきたい。
インティファーダやクルド人たちの
死者と死にゆく者たちへ、
いかなる国であれ、抑圧と闘い、勇敢に立ち向かって、
自らの信念をつらぬいているばかりか、銃弾に倒れていく者たちへ。
まず、「インティファーダ」とは、アラビア語で「蜂起」を意味する言葉で、 イスラエルに対し「反占領の闘い(インティファーダ)」を続けるパレスチナ民衆のことを指すのだが、1987年にガザ地区で起きた「蜂起運動」を、「第1次インティファーダ」と呼ぶ。ハイスミスの献辞は、この「第1次インティファーダ」に捧げられたもの(「第2次インティファーダ」は2000年に始まり、2005年に沈静化した)。
「クルド人」についての言及は、この本の刊行される1991年に、イラク北部のクルド人地区(南クルディスタン)で起きた当時のフセイン政権に対する反乱のことが言われているのだろう。この反乱は失敗に終わり、大量の難民を生み出すことになったのだ。
わたしたちは今なおガザ地区で起きていることを知らされているし、クルド人難民は現在の日本で「クルド人排斥」の動きとなっている。
30年以上の月日が過ぎても今なお、パトリシア・ハイスミスのこの「献辞」の訴えてくるものは大きい。


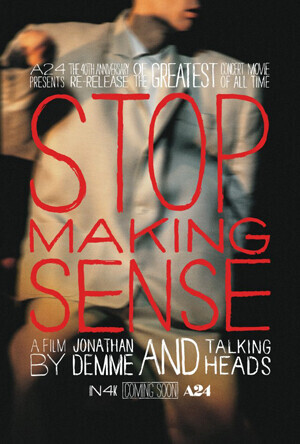




![危険なメソッド [DVD] 危険なメソッド [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Xr1cO77TL._SL500_.jpg)
