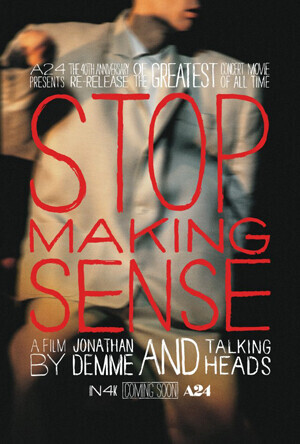「かたつむり観察者」(The Snail-Watcher)
食用かたつむりを観察し、飼育するようになったピーター・ノッパードの「悲劇」。
ハイスミス自身がかたつむりの飼育を趣味としていたことはよく知られていて、英語版Wikipediaには、かつて彼女は「レタス1個とカタツムリ100匹が入った」「巨大なハンドバッグ」を持ってロンドンのカクテルパーティーに出席したこともあったという。
この作品にも出てくる、かたつむりのセックスについては、わたしも「虫」のいっぱい出てくる映画『ミクロコスモス』のなかで紹介されていたのを観たことがある。
‥‥全身が粘膜ともいえるだろうかたつむり同士が、ぴったりとからだをくっつけ合って、ヌメヌメとお互いのからだのうえを愛撫するように這い回るわけで、粘膜=性感帯だという通念で解釈すれば、それはいかほどの快楽になるのだろうと想像すると、ほとんど気が遠くなりそうになった記憶がある。
この短編も、そんなハイスミスの「かたつむり観察」の成果が書かれていることだろう。かたつむりのセックスの描写は、ハイスミスの観察したものの記録だろう。
主人公のピーター・ノッパードはかたつむりを飼うようになってからは仕事の業績も上がるのだが、その後「かたつむりの繁殖力」におそれをなしてか、かたつむりを飼育する書斎に二週間も足を運ばなかった。そしてピーター・ノッパードが意を決して書斎に入ってみると‥‥。
ハイスミスのいつもの長編とは異なり、これは「怪異譚」とも言えるものだろうけれども、ラストのピーター・ノッパードを襲う恐怖は、やはりハイスミスならではのものだろう。
「恋盗人」(The Birds Poised to Fly)
主人公のドンは、しばらくのヨーロッパ滞在からニューヨークへ戻ってきた。帰ってきてから、ヨーロッパで付き合ったロザリンドのことが忘れられず、「愛しているから結婚してくれ」との手紙を出した。「ニューヨークへ来てほしいが、望むなら自分がヨーロッパへ行ってもいい」とも。
それから毎日のように郵便受けをのぞくのだが、ロザリンドからの返事は来ない。「性急すぎたか」と思うこともあったし、「彼女も気もちの整理がつかないのだろう」などと好意的に考えるドン。
そのうち、自分の住まいのとなりの部屋の郵便受けが郵便物であふれていることが気になり始める。どうやら隣人は部屋にずっと帰っていないのだろう。ついには「ロザリンドからの手紙は間違えてとなりの郵便受けに配達されたのではないか」と思うようになり、となりに届いた郵便物をチェックすることになる。その中に、女性から隣人に宛てられた手紙を見つけ、ドンはその手紙を開封して読んでしまう。
そこには、「あなたと別れてからもあなたのことが忘れられない。もう一度会っていただくか、返事を書いてくれないだろうか」という内容だった。
ドンがロザリンドに書いた手紙に似ていると思ったドンは、その女性が隣人から返事をもらえないことに同情し、なんと隣人の名前でその女性に手紙を出してしまい、近くの駅で会うことを約束してしまう。
ドンの行為は、そこに自分のロザリンドへの思いの反映があるだろうが、「いたずら」ではすまされない、一線を越えた行為ではあるだろう。
このあとどうなったかは書かないでおくけれども、ハイスミスならばこの発端から、充分にハイスミスらしいヤバい長編を書くこともできただろう。
「すっぽん」(The Terrapin)
ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』の中で、この短編のことがちょっと語られて、なんだか有名になってしまった作品。というか、『PERFECT DAYS』のおかげで、この『11の物語』はずいぶんと売れたようだが。
主人公のヴィクターは11歳。母親とふたり暮らしらしいが、母親がいつまでも自分のことを「子供」扱いすることにうんざりしている。いつもピチピチの短いズボンとひざ下までの長靴下を履かせ「フランスの6歳ぐらいの子供」みたいで、学校でもバカにされる。ヴィクターは実は母親に隠れて心理学の本を読んだりもするのだが、母親はいつまでもヴィクターにスティーヴンソンの『子供の詩の園』から暗誦をさせ、いつも人にはヴィクターのことを「まるでねんねなんですよ」などと言う。ヴィクターがつい「無念無想」などということばを使ってしまうと、「おまえ、頭がおかしいんじゃないの?」となる。要するに、まるで子供のことを理解しようとしない母親なのだ。
ある日、母親が来客用のシチューをつくるために、生きたすっぽんを買ってくる。さいしょは自分のためにすっぽんを買ってくれたのかと思ったヴィクターだが、料理用と知ってがっかりする。「このすっぽん、友だちに見せにいってもいい?」と聞くのだが、もちろん「ダメ!」といわれる。そして、ヴィクターの目の前で、お湯を沸騰させた鍋の中にすっぽんを放り込むのだった。鍋の中のすっぽんは口を開け、いっしゅんヴィクターをまっすぐに見て、熱湯の中に沈んでいった。
ヴィクターは「あんな殺し方しなくっていいじゃないか」と言うのだが、母親は「知らないの? こうすれば痛くないのよ」と言う。母親は反抗したヴィクターの頬をしたたかに叩いたのだった。
すっぽんの死ぬさまを思い出したヴィクターは涙を流し、そしてある行為を決意するのだった‥‥。
この前に読んだ『死者と踊るリプリー』でも、リプリーがロブスターを熱湯に入れる場面を見たがらないという描写も出てきたし、ハイスミス自身、こういう「熱湯で生き物を殺す」ということをヘイトしていたのだろう(何年か前、スイスではロブスターなどの甲殻類を生きたまま熱湯でゆでる調理法がじっさいに禁止された)。
ヴィクターにとって、「すっぽん」がすべての理由ではなく、ただ「きっかけ」にすぎなかっただろう。
単に「じっさいの暴力行為」でなくっても、「子供のことを理解しない親」というのは、充分に「DV」をはたらいていると言えるだろう。
「ヴィクター」の中に「自分」をみる子供という存在は、今でもけっこういることだろう。

![生きる LIVING [DVD] 生きる LIVING [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Jn2Y8EmkL._SL500_.jpg)